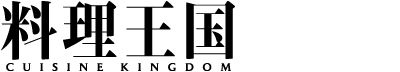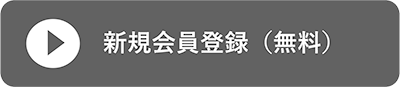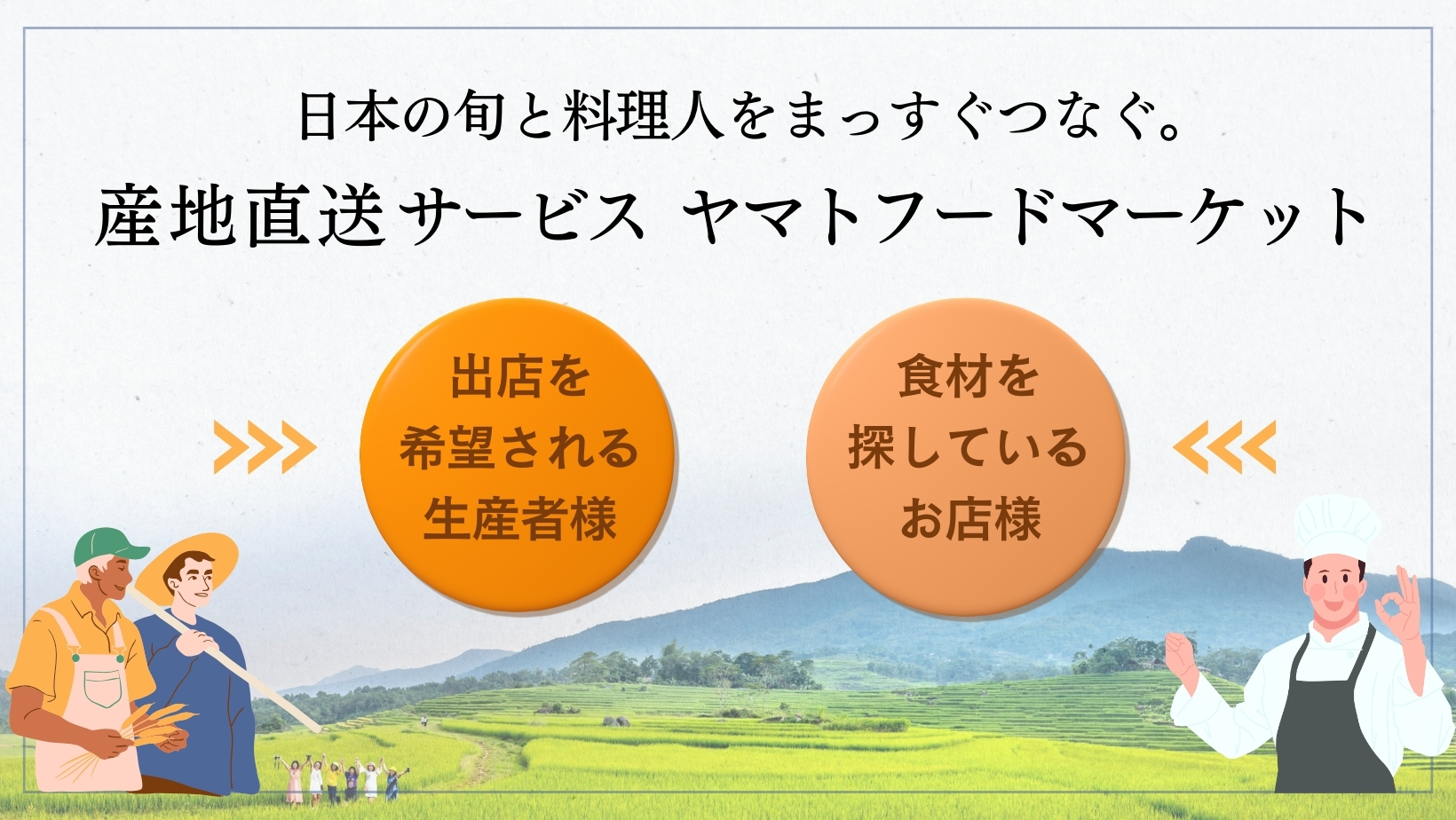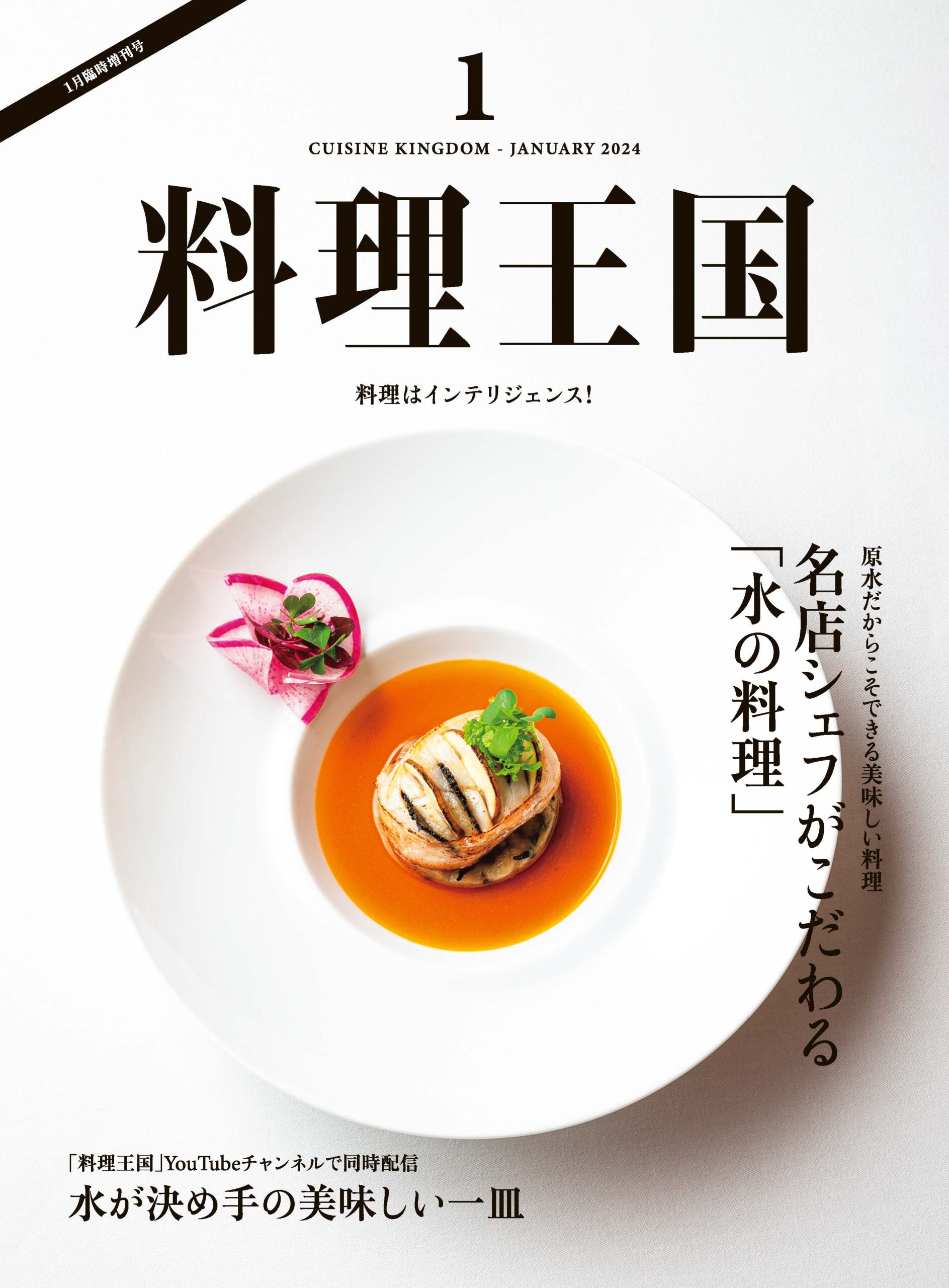【帝国ホテル】歴代料理長の血と汗の結晶

日本の繊細さに学び、日本の食材に挑んで伝統に新しさを重ねていく
田中健一郎さん 帝国ホテル
日本のフランス料理を語る上で、帝国ホテルは外せない存在である。 1890(明治23年)、海外の賓客を迎えるホテルとして開業。日本の迎賓館としての使命を、帝国ホテルは果たし続けてきた。それはむろん、レストランも例外ではない。フランス料理はヨーロッパの正餐。その流れをくむ帝国ホテルのフランス料理は、開業当時ですら、「パリはここにもある」といわしめる水準を保持していた。
それをさらに推し進めたのが、フランスへの留学生の派遣である。昭和初期の留学生の派遣は、旅費も滞在費も大蔵喜七郎社長のポケットマネーでまかなわれ、
留学生の俸給は全額会社から支給された。八代目の料理長、石渡文治郎氏もその例にもれず、近代フランス料理を確立したオーギュストエスコフィエが晩年まで料理長を務めたパリのホテルリッツで修業。そのフランス料理を、帝国ホテルの厨房に持ち込んだ。
帝国ホテルの料理は歴代料理長の血と汗の結晶
「エスコフィエの流れをくむフランス料理。その伝統は今も変わりません。もちろん、お客様の嗜好や時代の変化によって、ソースにもバターではなくクリームを使ったり、動物性のフォンから植物性のフォンに変えたりはしています。でも、軸はブレません。帝国ホテルの料理は、歴代料理長の血と汗の結晶ですからね。そう簡単に変えるわけにはいきません」と、田中健一郎第十三代料理長は語る。それこそが、フランス料理の王道を歩む料理人の矜持なのだろう。
「帝国ホテルのお客様が望まれる料理を提供する。私は常に、帝国ホテルのお客様のほうを向いていたい」
気軽に流行を追うのではなく、愚直ともいえる姿勢で旨さとゲストの喜びを求め続けてきた。それが「帝国ホテルの料理」。第十一代料理長、村上信夫氏の跡を継いだ田中さんのなかにも、その精神は脈々と生き続ける。

肉の目利き役ブッチャーのいる厨房
そうした料理への誇りと誠意を物語る存在が、帝国ホテルの〝厨房〞にいる。肉の目利き役、ブッチャーである。取引先が届ける肉を、すべて吟味する。そしてときにはノー」を突きつける。仕入れた肉は、熟成庫でいい状態になるまでドライエイジング。一方、食べ頃になった肉はブッチャーによって部位ごとに切り分けられ、各調理場へ渡される。「納入業者は肉のプロ。でも、料理のプロではありません。ブッチャーは調理師免許をもっている料理人であり、肉の目利きでもある。カットして納入された肉と、ホテル内でブッチャーが切り分けた肉とでは、自ずと料理の出来が違います」
帝国ホテルには、ブッチャーと同じような食材の目利きが、魚にも野菜にもいる。通常は納入業者に任せてしまうような作業を、今なお自分たちで行う。見えないところに人手と手間暇をかける。これもまた、帝国ホテルの帝国ホテルたるゆえんである。
後継者を育て、料理を後世に伝える
帝国ホテル東京だけでも、料理人と呼ばれるスタッフは350人を越える。田中さんは今、その頂点に立つ。「一人の料理人としては、もっとおいしい料理を自ら作りたいと思う。旨い料理を食べたあとの幸せそうな笑顔を、たくさん見たい。でも同時に、きちんとした後継者を育てていかなければならないという思いも強い。帝国ホテルの料理の味を後世に伝える。それこそが、今の私に課せられた使命だと考えています。もっともこれは、帝国ホテルに限ったことではありません。調理場に限らず、ある程度の年齢になったら、次世代へ自分のもっているものを伝えていくことが大切なのではないでしょうか」
伝統にあぐらをかかない。料理長の視線は、帝国ホテルとそのレストランの未来を見据えている。

Kenichiro TANAKA
1950年東京生まれ。1969年、帝国ホテルに入社。2002年、取締役総料理長兼調理部長に就任。東京、大阪、上高地で400人以上の料理人が働く厨房の総責任者である総料理長職は、故村上信夫氏に続き2代目。2009年6月、調理部長職を離れ、総料理長職に専念。2012年4月より現職。
山内章子=取材、文 星野泰孝=撮影
本記事は雑誌料理王国221号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は 221号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。