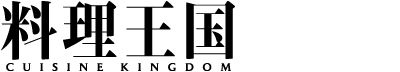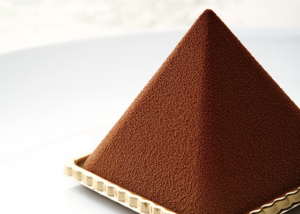ヌーベル・キュイジーヌの鬼才「アラン・サンドラス」からはじまる。フランス料理の輝かしい系譜

パリのある美食家の体験談――。「パスカル・バルボ氏がシェフを務める『レストランアストランス』のリード・ヴォーが素晴らしかった。称賛したら、バルボ氏曰く、『僕は何もしていません。火入れの匠、アラン・パサールに教わった通りです!』。次にパッサール氏の店『アルページュ』に行くと、黄金色のリード・ヴォーが運ばれてきました。これこそ理想のリード・ヴォー、と思ったら、パッサール氏は、『僕じゃないですよ。すべてをムッシュ・アラン・サンドランスに教わりました』。
そして最後に、サンドランス氏の店『ルカ・カルトン』で最高のリード・ヴォーをいただきました。外はカリッと黄金色。中は乳白色で、口の中でとろけるようでした。『誰に教わったのですか?』と聞くと、彼は一瞬たりとも躊躇わずに『リード・ヴォーですか?私です』と答えました」。
サンドランス、パッサール、バルボという3人の革命児
「ヌーベル・キュイジーヌの天才」とも「鬼才」ともされるアラン・サンドランス氏がこの世に送り出した料理とシェフの数は無数だ。「アルページュ」のアラン・パッサール氏、ホテル「ジョルジュ・サンク」のクリスチャン・ルスケール氏、「ホテルリッツ」のクリストファー・アッシュ氏、アルザス地方マーレンハイム「ル・セール」のミシェル・ユセール氏(「KEI」の小林圭さんの師匠)。
パッサール氏も同様に、著名な料理人を育てている。中でも一番有名なのはもちろんパスカル・バルボ氏だが、ほかに「セプティーム」のベルトラン・グレボー氏や「ダヴィッド・トゥータン」のダヴィッド・トゥータン氏が目立つ。バルボ氏の厨房の卒業生は、東京「レストランカンテサンス」の岸田周三氏や去年オープンした「ル・セルヴァン」のタティアナ・レヴァ氏、スエーデン「ファーヴィケン」のマグニュス・ニルソン氏などが、国際的にも認められている。
サンドランス、パッサール、バルボ――3人の共通点は、オーナーシェフとしてオープン1年以内に一ツ星を、10年以内に三ツ星を獲得したこと。マスコミに「スターシェフ」ともてはやされることを拒む、それぞれの時代の「革命児」であった。1985年、サンドランス氏は大繁盛店「アルケストラート」を手放すと、1963年から2年間修業したことのあるパリのマドレーヌ広場に所在する老舗高級店「ルカ・カルトン」を買収し、同店のシェフになる。「アルケストラート」は弟子のアラン・パッサール氏が買い取り、「アルページュ」と改名する。
「アルケストラート」時代のサンドランス氏が歴史に残した料理のひとつに「フォワグラとキャベツ」がある。何が革命的だったのか、今の料理人は疑問に思うだろう。当時はキャベツのような安価な野菜に大美味のひとつフォワグラを合わせ、おまけに蒸すことなど、まったく論外だったのだ。
母、増井和子の著書(『パリの味』1985年文芸春秋刊行)によれば、「フォワグラはキャベツに包んで蒸してある。フォワグラのロールキャベツ。あるいは皮をキャベツに、具をフォワグラに置き換えた蒸ギョウザと例えてもいい。ソースのないフランス料理。ギョウザは、口に含んで噛んだ時、汁があふれる。固形物を食べているはずが口に含むとトロッと液体。キャベツは脂をよく吸うし、脂とはとても合う。考案者のサンドランス氏に脱帽だ――」。
アラン・サンドランスが起こした3つの革命
フランス料理界で「ムッシュ」と呼ばれるサンドランス氏が起こした革命は3つある。
ひとつは料理における革命。「素材に忠実な料理」「食材を活かす料理」といったフレーズは、現代の料理人には聞き飽きた言葉だが、「アルケストラート」がオープンした60年代後半はたいそう斬新だった。間もなくヌーベル・キュイジーヌの到来。先駆者フェルナン・ポワン氏に次ぎ、ミシェル・ゲラール氏を始め、ポール・ボキューズ氏、トロワグロ兄弟、アラン・シャペル氏、ロジェ・ヴェルジェ氏たちがフランス料理を劇的に変えた時代だ。そしてアラン・サンドランス氏。厚めに切り分けたテリーヌ、蒸したフォワグラや燻製の鮭。料理は塩で決まる。最高のゲランド産の塩(フルール・ド・セル)を数粒仕上げに。今なら当たり前のようなこの仕上げが革命的に新しかった。
さらにサンドランス氏は、「甘い(スュクレ)」と「塩辛い(サレ)」をきっちり分けていた当時のフランス料理のルールを破る。代表的な料理が、古代ローマの美食家「アピシウス」に捧げた「アピシウス風の鴨」だ。中世やルネサンス以後は忘れられていた「甘い」と「辛い」が両立する料理。
トゥール・ダルジャンの「鴨のオレンジ風味」など、限られた果物と肉の組み合わせしか知らなかったフランスの料理界に、いきなりこってりと甘い、ロゼに焼いた鴨を突き付けた。この甘味をフランスではまだ珍しいクミン、コリアンダー、コショウの大きな粒にまぶして食べさせる。
ヌーベル・キュイジーヌに、実は日本が大きな影響を与えていたことも忘れてはならない。サンドランス氏は何回も中国を訪れて中国料理に感心しながらも、魅力は感じなかったと言う。彼は、人間と自然とが強く結ばれた日本、小さな野菜でも大切に使う日本、魚を生で食べさせる日本、に魅了された。70年代後半にサンドランス氏は「アルケストラート」で「ソーモン・シズオ」を出す。辻静雄氏への敬意を秘めたこの鮭料理は、醤油風味のブールブランソースで仕上げてあった。醤油やワサビなど、日本の食材をフランス料理に初めて使ったのもサンドランス氏だ。
ふたつ目はワインとの革命的マリアージュ。60年代末のことだった。ミシェル・ゲラール氏が来店し、ひと言発した。「アラン、君の料理はすばらしいんだが、ワインがなんとも、まずい」。深く傷ついたサンドランス氏は、ワインに取り組み、80年代にワイン学者のジャック・プイゼ氏と出会う。87年には史上初の「ワイン・ペアリング・メニュー」を提案。各料理に合わせて、違うワインをグラスで提供したのだ。
三ツ星をミシュランに返上したビストロノミーの発案者
トゥレーヌ産の山羊チーズとヴヴレのドライな白ワインとのマリアージュは、「チーズには赤」と決め付けていたフランス社会で、ちょっとしたスキャンダルになった。今や「チーズに白ワイン」はクラシックだが、サンドランス氏の時代は革命だった。結果、サンドランス氏は、優秀なソムリエにも神のように尊敬されたのだ。
3つ目はミシュランへの挑戦。2005年、サンドランス氏はパリの高級老舗三ツ星店「ルカ・カルトン」をいきなり「リーズナブルな美食店」に改装し、フランスの料理界を騒めかせた。その日、「ムッシュ」は30年近く保持した三ツ星をミシュランに「返した」。
ひとり100ユーロのリーズナブルな食事は大ヒットし、店の売り上げは3倍に増した。ヒラメでなくサバ、仔羊はカレ(あばら)でなく肩肉。新「ルカ・カルトン」は高級食材の代わりに安くておいしい食材を食べさせる。実に、今日の「ビストロノミ―」の前身だ。
この系譜の次の世代は戦後に生まれたアラン・パッサール氏だ。パッサール氏、ピエール・ガニュエール氏、ミシェル・トロワグロ氏、アラン・デュカス氏、つまり戦後50年代生まれの著名な三ツ星シェフの中で、アラン・パッサール氏は独特な立場にいる。彼はメンバーの中で唯一、パリ以外に店を持たない。他のシェフたちは東京や香港などに店を開いたが、彼はパリに1軒だけだ。「弟子たちと一緒にいたいから、他の街にレストランをオープンしないんです。調理場に何時間も立ち、弟子たちに素材の選び方や切り方、手の動かし方、正しい動作のひとつひとつを見せることが、グランシェフの仕事だと思っています。それが楽しい」と語るパッサール氏。彼は15年ほど前、自分の料理が限界にきたことに気付いた。肉のロースト職人として腕を磨いてきたが、肉を使い尽くした感じがしたのだ。

料理人としての精神、エレガンス、完璧の追及、を受け継いだ
「今度は野菜に挑戦する。肉の代わりにニンジンを皿の主役にするぞ」と決心したパッサール氏は、パリから2時間ほど離れたサルト地方に農園を作った。「三ツ星シェフの気まぐれ」と笑われもした。フランス料理の柱は常に肉で、野菜はあくまでも二流食材だったからだ。周囲からは、「三ツ星を失うぞ!」と忠告された。しかし、「野菜のメニュー」は、やがて肉好きのフランス人にも絶賛され、三ツ星も保持した。パッサール氏はまさにパイオニアと言えるだろう。
彼はまた現役の巨匠の中でも驚くほど「子分」が多い。そのうちのひとりパスカル・バルボ氏は、「『アルページュ』を卒業する時、レシピをたくさんもらったわけじゃないんです。それよりも大切な、料理人としての精神、動作のエレガンス、完璧の追及、そういった根本的なことを受け継ぎました。ほかでは誰も教えてくれないことです」と語る。
サンドランス氏から数えて3代目に当たるバルボ氏は43歳。つい最近まで厨房外では、「シェフ」と呼ばれることさえ拒んでいた。2007年に三ツ星を取得した時に一番驚いたのは本人だったと言う。
そんな彼は、01年、誰よりも早く、料理をコース1本に絞ることを決めた。「オープン当時は、ちゃんとアラカルトもあったんです。でも、食材の管理が大変で、無駄も多くて困った。そこでクリストフ(共同経営者のクリストフ・ロア氏)が、『ひとつのコースだけにすれば?』と言ったんです。僕は度胸がないから最初は怖かったんですが、ゲストはこの方法をサプライズとして、かえって楽しんでくれました」
バルボ氏もパッサール氏と同じように、「毎日、厨房でみんなと仕事をすることに喜びを感じている」。だから、彼の店の卒業生もまた、毎日コツコツ料理を創る。自営の小さな店ばかりだ。ヨーロッパ各地、アメリカや南米、アジアやオーストラリア、世界中で「アストランス」の卒業生が自分たちの手で料理を作っている。わずか43歳のシェフの弟子たちが、世界中に広がり、独自のレストランのシェフであることは、今までになかったことだ。
「反抗」と「わがまま」、世界中の素材を料理にぶつける度胸のよさ
サンドランス氏、パッサール氏、バルボ氏。3人ともパリに1軒の店しかない。私には、この3人がフランス料理の独特な系譜を描いているように見える。12年、フランスの週刊誌「エクスプレス」は、「アラン・サンドランス、フランス料理の反抗者」と題した記事を掲載した。フランスでは「反抗」することは良いことだ。おとなしく「はい」とばかり答える者よりも、「いや、違う」と反論する人間のほうが評価される社会なのだ。その社会が生んだ3人の革命家。それがフランス料理の輝かしい流れを形成している。
アラン・サンドランスは、啓蒙時代以来侮られていたスパイスを、フランス料理に戻した。新時代を開拓しながら、古代ローマの美食、中世やルネサンスの古書をとことん研究し、フランスの美食家を驚かせた。
ロティシエ(肉を焼く料理人)だったパッサール氏は、その経験を野菜に生かし、肉のように野菜を扱ってグルメたちを驚かせた。
バルボ氏がフランス料理に与えた影響は、「国際性」ではないだろうか。2000年から約8年の間に彼が掘り起こした世界の素材には、シトロン・キャヴィア、ユズ、鰹節、ブラジルの唐辛子、昆布、タイカレー、シシトウ、枝豆、タジェットの花など、ほかにもさまざまなものが挙げられる。世界中の素材を独自の料理にぶつける度胸のよさも評価に値する。エスコフィエがパプリカを「唐辛子」と呼んだくらい「辛味」に慣れていないフランス人に、唐辛子主体の料理を作ったのもバルボ氏だ。
もっと言うなら、3人の一番の共通点は、「わがまま」かもしれない。マスコミや世論を無視して、自由に料理を創る。ただしこの「わがまま」は、完璧な技術や創造性に裏打ちされている。だからこそ、輝かしい系譜を成しているのである。

料理作家・評論家 増井千尋
本記事は雑誌料理王国259号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は259号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。