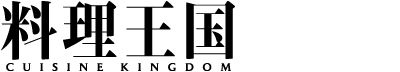「コート・ドール」にはなぜ厳しい時代を生き抜く力があるのか?(後編)

シェフがこだわっているルール、斉須イズムって何ですか?
特に難しいルールなんかないですよ。人にも自分にも誠実であること。人間なら当たり前のことですね。「コート・ドール」ならではのルールというと、1日3回の掃除。まず、朝の仕込み後の食事のあと、ランチタイムのあと、夜のサービスのあと。これは「ヴィヴァロワ」のペイローさんから受け継いで、「コート・ドール」をオープンした時からずっと続けています。「掃除」とひとことで言っても、決まりごとがあって「ここはこれで拭いて、そこにはこれを使って」と、掃除道具についても細かい。「1日に3回も掃除することに何の意味があるのか」と言う人もいるでしょうが、僕は「清潔で整理整頓されていることは、仕事をきちんと遂行するための基本」だと思います。穏やかな気持ちで料理をすることも大切かもしれません。
1981年、僕はベルナールさんと一緒に、パリに「ランブロワジー」をオープンさせ、二ツ星をいただきました。すばらしい料理人だったベルナールさん。仕事上のことで何度かぶつかったこともありますが、僕は彼のおこった顔を一度も見たことがなかったですね。パリの三ツ星店「ヴィヴァロア」で修業し始めた頃、「本当に自分はここでやっていけるのか」と不安でたまりませんでした。プレッシャーに押しつぶされそうになった僕を救ってくれたのが、実は「掃除」でした。一般には人が手を出したがらない作業、そんな作業の中に、苦しさを乗り越えるヒントがあり、心を落ち着かせてくれる何かがあるものです。ただ、僕は12年間フランスで働きましたが、「掃除」を嫌がらずにする「いい人」で終わるつもりはありませんでした。だから、掃除は誠心誠意しましたが、僕はフランスでは「いい人」ではなかったと思います。フランスの表面だけをかすった「フランス帰り」には絶対なりたくなかった。
パリでは、たぶん東京でも、勤勉なだけでは生き抜けません。愚鈍なだけでは使い走りで終わってしまう。必要な時に必要な力が出せる料理人になること。ちゃんとしたステージに上げられたらきちんと力が発揮できる。だけど、普段は無色透明。「コート・ドール」では、先輩も後輩も関係なく全員で掃除をします。毎日大掃除をしているようなものですが、毎日続けたらそれは大掃除ではなく、普段の掃除になる。この考え方は、仕事や人生にも応用できます。大変なことや面倒なことでも毎日コツコツ続けていたら、それは「特別」ではなく「日常」になる。その積み重ねがやがては大きな力になる。だから僕は、誰に見せても、どこを切り取っても恥ずかしくない日常を送ろうと心掛け、それをスタッフにも勧めています。

レストランが10年もてば奇跡といわれる時代をブレずに生きるには
振り返ると、「ランブロワジー」のベルナールさんはじめ、さまざまな人の顔が浮かびます。助けてくれた人、認めてくれた人――。「コート・ドール」の最初のオーナーは、のちに「札幌コート・ドール」を開いた方で、その後、僕がオーナーシェフになる時に、「他所でやるならここでやってはどうですか」と言っていただいた。それがなければ、僕の人生は変わっていたでしょう。このような恩人たちのことを思う時、僕にも、後輩たちにチャンスやメッセージを与える役割があるように思います。伝えたいことはいろいろありますが、若い人たちには、ぜひ海外で研鑽を積んでほしい。僕が渡仏した頃とは違って、今は海外との交流も盛んですから、「わざわざ外国に行かなくても」と考える人もいるようです。しかし、実際に自分の肉体で確かめなければわからないことがたくさんあります。うちにも、2年半ほどフランスへ修業に行って帰国したばかりのスタッフがいますが「シェフから聞いていたことを肌で感じとってきた」と言っています。
ちなみに僕は、フランスで日本人としての欠点を知りました。日本の調理場では、みんな仲良く、できるだけ波風を立てないように仕事をするのが普通でした。しかし、フランスで「仲良く」なんて思っていたら、利用され、いいように使われて終わってしまいます。やりたいことも、不満も、口に出さなければわかってもらえません。フランスでは、スタッフ同士が議論し合います。たとえ口論になっても、不仲になることはありません。むしろそうやってお互いを知るきっかけを作るのです。「イエスかノーかをはっきりと。物事を説明する場合は、まず結論を先に言う」。これは海外生活で困らないように、僕がスタッフに言い聞かせていることのひとつです。海外では日本人としての長所にも気づかされます。勤勉で努力家。日本で身につけた技術は世界でも通用します。相手への細やかな気配りも評価されるでしょう。
「語学ができない」と尻込みする人もいるでしょうが、何とかなるものです。「おいしいものを作っていればお客さまが来る時代は終わった」と言う人もいます。エンターテイメントを重視したり、若くして食のプロデュースへの転身を考えるシェフもいると聞きます。もちろんそれも選択肢のひとつですが、くれぐれも時代に流されすぎないようにしてほしいです。長く続けなければ見えてこないこともあります。バブルがはじけてみんなが右往左往していた時、僕はひたすら自分でいました。時代におもねり、策を練った人たちがむしろ消えていった現実も、僕は見ました。


Masao Saisu
1950年、福島県生まれ。18歳でフランス料理の世界に入り、73年に渡仏。「オーベルジュ・ド・カンカングローニュ」「ヴィヴァロア」「タイユバン」などの名店で腕を磨き、81年ベルナール・パコオ氏とパリに「ランブロワジー」をオープンした。その後、帰国し、86年には「コート・ドール」の料理長に就任。92年からオーナーシェフを務める。
民輪めぐみ=インタビュー 上村久留美=構成 依田佳子=撮影
本記事は雑誌料理王国2018年9月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は2018年9月号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。