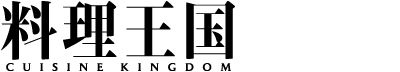「コート・ドール」にはなぜ厳しい時代を生き抜く力があるのか?(前編)

僕は夢想家。
だから、僕の考えを具現化してくれる信頼できるチームが大切なんです
「コート・ドール」 斉須政雄さん
変化し、多様化し、個性的に趣向を凝らしたレストランが人気を呼んでいる。一方で、何十年もスタイルを変えず、それでもトップを走り続ける店もある。東京、三田の「コート・ドール」。オーナーシェフの斉須政雄さんは、いまや都市伝説といってもいいフランス料理の匠だ。老いも若きも、プロもアマも「惹かれるシェフ」に挙げる「斉須政雄」。人は斉須さんの何に惹かれるのだろうか。
多くの料理人が憧れる「斉須政雄」を自己分析すると……
ひとことで言うなら「ドリーマー」かな。「コート・ドール」が開店して32年。シェフを続けていると、料理だけでなく、人生について意見を求められる場面も多くて、雑誌などで僕の言葉や姿を目にした人は、「堅苦しい」という印象を持つ方もいるようですが、心の中はすごく自由なんですよ。どうしても「料理ひと筋」というイメージがついて回るんですが、僕自身は、「どこを切っても料理人」という人にはなりたくない。
趣味もあります。音楽はクラシックからポップス、ロックまで聞くし、ライブも大好き。ポール・マッカートニー、エルトン・ジョン、ビリー・ジョエル、サラ・ブライトマンのライブにも行きました。時々、こんなに子どもじみた68歳はいないんじゃないかな、とも思います(笑)。自分自身のことを分析するのは難しいですが、20代から、「こんな人になりたい」というモデルはあったんです。渡仏した際に修業した三ツ星店「ヴィヴァロワ」のオーナー、クロード・ペイローさんです。
掃除をとても重視した人で、オーナー自ら率先して行っていました。また、ペイローさんは、ものの扱いもとてもていねいで、真心がこもっていた。だから「ヴィヴァロワ」の厨房にあるものは、無造作に置かれた鶏ガラさえも美しくおいしそうに見えたものです。お客さまが「今日の料理、おいしかったよ」と言うと、その人を厨房まで連れてきて「この子が作ったんですよ」と私を紹介してくれる。そんな気配りのある人でした。ペイローさんに出会って初めて、僕は「自分はこういう人になりたかったんだ」と気づかされました。あれから40年以上経ったんですねえ。まだペイローさんには及びませんが、彼の境地に少しでも近づきたいという気持ちは変わりません。
「コート・ドール」にはなぜ厳しい時代を生き抜く力があるのか
「コート・ドール」が続いているのはなぜ? と言われても、僕は料理しているだけですしねえ。調理、サービス、ソムリエなどのチーム力でお客さまに喜んでいただけているからでしょうか。支配人やソムリエとの付き合いは長くて、支配人の松下さんとは30年。ソムリエの大園さんも13年ほど一緒でしょうか。松下さんは言う。「シェフはおいしいものを作ってくれればいい。僕らはシェフの料理がおいしいから、それを運び続けたいんです」。
調理場の若者は、店に食べに来た上で応募してくれた子が多い。実際に働いてみたら、失望しているかも知れませんけどね(笑)。僕は「理論」ではなく「皮膚感覚」で調理するタイプだから、調理場の僕は、「安心して付き合えないタイプ」かもしれません。最近の若い料理人 は、セオリーで理解しようとする人が多いでしょう。たとえば調味料にしても、何を何グラム使ったかを計測して、数値化して固定したい。僕はそれを裏切る。決していじわるしているんじゃなく、昨日の正解が今日の正解とは限らない。料理ってそういうモノだと僕は思う。それを理解できない人にとって、僕は「安心できない人」になってしまうんです。理由を噛み砕いて説明したり、僕なりに努力しているつもりです。スタッフが僕から何かを吸収したいと思っているように、僕も彼らには、頭脳や手足の一部となって助けてほしい。その相互協力がうまくいって、お客さまが満足してくださることが我々の喜びであり、誠意だと思います。その誠意を忘れない限り、「コート・ドール」でいられるかなと思っています。

ゲストも自分自身も飽きることなくひとつのスペシャリテを長年続けられる秘訣は何ですか
「斉須政雄」という人間は、とても臆病で無器用な人間なんです。今日上手にできても、明日も同じようにうまくいく保証はないと思っている。だから、同じ料理を長年作り続けていても、「飽きる」という余裕はないんです。続けなければ、あっという間に転落するのでは、という不安は常にある。もちろん今もあります。ですから、料理を作り上げたそばから、また同じ料理が作りたくなる。少しでも早く確認したいのです。
飽きない理由はほかにもあって、同じ料理だからといって、まったく同じ作業をしているわけではなく、野菜も魚も、ここ何年だけとっても、味わいや産地は変化しています。もちろんお客さまの嗜好も少しずつ変化しています。だから、微妙にではありますが、レシピも変化しているんです。「繰り返すこと」こそが不安の解消、などと言うと、マイナスの印象を与えそうですが、僕が30年以上同じ料理を作り続けているのは、もちろんそのひとつひとつに愛着があるからです。そう、何よりそこが大切。
「赤ピーマンのムース」は、パリの「ランブロワジー」のベルナール・パコオさんのスペシャリテでした。赤ピーマンの皮をむいたり、焦がしてみたりして試行錯誤の繰り返し。「こう料理すると、こんな結果が得られて、お客さまを喜ばせることができる」と、リアルに感じられたのもこの料理。添え物だったピーマンを、堂々たる主役に抜擢したのも、当時としては衝撃的でした。だから、これはもう、僕の財産なんです。「野菜の蒸し煮」も、28歳から40年間大切に作り続けている料理で、これを作らなかった期間があるとすれば、それはフランスから帰国する時の機内くらいです(笑)。

裏漉しして生クリームと合わせた赤ピーマンのムースはなめらかな舌触り。最初は赤ピーマンの「ガスパチョ」からスタートし、「ババロワ」へ、そして「ムース」へと変化させていった。

Masao Saisu
1950年、福島県生まれ。18歳でフランス料理の世界に入り、73年に渡仏。「オーベルジュ・ド・カンカングローニュ」「ヴィヴァロア」「タイユバン」などの名店で腕を磨き、81年ベルナール・パコオ氏とパリに「ランブロワジー」をオープンした。その後、帰国し、86年には「コート・ドール」の料理長に就任。92年からオーナーシェフを務める。
民輪めぐみ=インタビュー 上村久留美=構成 依田佳子=撮影
本記事は雑誌料理王国2018年9月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は2018年9月号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。