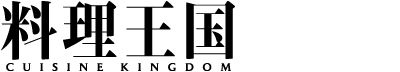国内外のトップシェフが考える、これからの美食のかたち

県を挙げて「ガストロノミーで復興を」とシェフと生産者、地域が一丸となって個性を表現しようとしている岩手県にて、2020年10月26~27日にわたり、「三陸国際ガストロノミー会議 2020」が開催された。登壇した国内外のトップシェフたちの言葉からは、これからの美食の方向性が見えてきた。

生産地を抱える地域のレストランから日本の豊かな食文化が見えてくる
生産者を守り、日本の食を守る。
2019年の開催に続き、2回目の開催となった「三陸国際ガストロノミー会議 2020」。前回と大きく異なり、コロナ禍を受けて海外シェフはオンラインでの参加となった。1日目の特別講演に登壇したピエール・ガニェール氏は、2016年に岩手を訪れている。講演では、岩手の食材の素晴らしさについて触れ、「コロナ禍で人々が関係性を築くのが難しい今こそ、レストランが必要とされている時。創造性を持ち、工夫する力を養い、絶対に諦めてはいけない」と訴えた。また、彼の下で17年働き、現在、東京店を任されている赤坂洋介氏は「ガニェール氏は食材ひとつひとつの味わいを丁寧に確かめて料理を生み出すだけでなく、生産者の生活をどう支えられるかを常に考えている」と語った。美食の原点でもある食材。海外との航空便も減り、あらわになった自給率の問題も含めて、国内の生産者の重要性は増す一方だ。
さらに、「ここでしか食べられない食」が求められている今、地域の特徴ある食材を生み出し、生産者と共に美食文化を生み出していくことは非常に重要だ。京都で15代続く懐石料理店「瓢亭」の当主、髙橋義弘氏は、「京野菜も、昔から味がよかったわけではない。今から35年ほど前、父・英一など、京都の料理人たちと若手生産者がいっしょになって、おいしい野菜を研究した結果、今のような味わいになった」と語った。
地元食材を使うことで、新しい美食を生み出したシェフもいる。「開業当時、ハーブを買うお金がなかったから、地元の野草を摘んで使ったんです」と笑うのは、父親の借金を背負いながらも、2000年に山形県鶴岡市にて「アル・ケッチァーノ」を開店した、奥田政行氏だ。地元の食材を生かせる料理は何か。庄内の気候や土壌、海流など、地域の特性を徹底的に研究し、地域食材の味わいを分析して辿りついたのがイタリア料理だった。地元食材の味や香りのチャートを作り、現在のスタイルにつながっていった。飲食店が衰退すれば、日本の一次産業が衰退する。料理人と生産者が高め合い、食文化を作り上げようと呼びかけた。

料理は、もはや皿の上だけのものではない
「地方が持つ資産は、皿の上だけのものではない」と語ったのは、チョコレートの販売を通して、ペルーのカカオ生産者を支援し、長野県・軽井沢で「ラ・カーサ・ディ・テツオ オオタ」を営む太田哲雄氏だ。標高3500mのペルーのモライ遺跡の側にある、ヴィルヒリオ・マルティネス氏のレストラン「ミル」を引き合いに出し、「標高が高いと、肉に焼き色がつきづらく、パスタもなかなか茹で上がらない。そんな地域に合った調理法を工夫していた」と振り返り、岩手の環境でしかできない料理を考えてみてはどうかと提案した。また「ここでは食後のコーヒーは豆の生産者が直接淹れるなど、皿の上のおいしいだけを追い求めず、地域ぐるみでその地域らしさが表現することもできる」と語った。
レストランでこそ、 新しい文化を生み出せる
「地方に人が呼べるレストランを」という、師であり、現代バスク料理の第一人者、ルイス・イリサール氏の言葉に従い、35年前、北海道函館市に「レストランバスク」を開店したのが深谷宏治氏だ。当時スペイン食材が容易に手に入らず、逆にそれが、地元の豚肉で生ハムやパンを自ら作り、手に入らない西洋野菜は畑を作って無農薬栽培するというスタイルを生み出した。レシピを「共有」することで食の都として成功したサン・セバスチャンに倣いシェフ同士の情報共有を計り、11年前から「世界料理学会 in Hakodate」を開催するなどの活動を行なっており、「学び合い、高めあう」文化作りに貢献している。
文化は自分たちの文化に
誇りを持つ事から 国内外のシェフをつなげ、壇上でナビゲーター役としても活躍した、岩手県田野畑村「ロレオール田野畑」の伊藤勝康氏は、
元々千葉県の出身だが、移住した岩手県の自然に心底惚れ込み、地元の山菜やきのこ、野草などに詳しい。「地方は食料自給率が高い上、いざとなったら、山に入って、自分の食べるものは自分で採集してやっていける。地方にはそんな強さがある」と語った。かつて自然の中で生きてきた人間の、生物としての本質的な強さだ。
自然に目をやると「多様である」という事は、種のセーフティネットでもある。地方の「らしさ」の追求を継続していくことが、ひいては日本という国の強さにも、つながっていくのではないだろうか。

こちらの記事もおすすめです!
text 仲山今日子
本記事は雑誌料理王国2021年2月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は2021年2月号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。