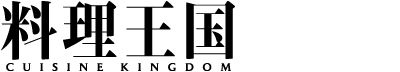名匠のスペシャリテ「割烹 小田島」小田島 稔さん

時代を超えて愛され続ける名匠のスペシャリテがある。
和食でワインを楽しむという新しい食文化を開いた「割烹小田島」の小田島稔氏と、その代名詞「フォワグラ大根」。
和食とワイン。このマッチングこそ私の世界
前菜としてお出ししている「フォワグラ大根」が誕生したのは、1980年代のことですから、30年以上もこのひと皿を作り続けていることになりますね。70歳を目前にした今のほうが、「優しい味」になったと言われるお客さまもいらっしゃいます。余分な味付けはいっさいしない。食材を生かしきることが、「優しい味」につながるのでしょうか。
この献立が誕生した当時は「前衛」と騒がれました。割烹なのにワインをおき、食材としてフォワグラを使った板前は、私が最初。とはいえ、フォワグラと大根の組み合わせは、フランスから帰国後に独立し「クィーン・アリス」を展開したフレンチの石鍋(裕)さんのほうが、私よりも一足早かったと思います。
石灰岩の土壌が多いフランスでは、日本のようなみずみずしい大根は育ちません。ニースあたりでは黒っぽい大根をサラダに使うくらいです。フォワグラと大根の組み合わせは、日本ならではのことです。
和食の私が、なぜワインをおき、フォワグラという食材を選んだのか。それは、若き日のパリでの強烈な実体験に根ざしています。24歳のとき、パリにあった和食屋「たから」で働くことになりました。ここの芦部たくみさんというオーナーがすごかった。信州の出身でイノシシ料理に精通していた。フランスはジビエの国だから、日本のイノシシで勝負をかけたんです。繁盛しましたね。
第1次日本食ブームのはじまりです。女優のジャンヌ・モローと別れたばかりのピエール・カルダンも、ときどき現れ贔屓にしてくれました。国際ペンクラブの会合でパリにいらした作家の川端康成さんは、ホテルのベッドでは寝られない、とパリの和食屋の座敷に泊まられた。
私はワインに魅せられ、憧れの白ワインを造り出すシャトー・オー・ブリオンを訪ねるなど、ワイン修業に明け暮れました。そして、「マキシム」で食したフォワグラの何と美味だったことか。アロハシャツを着たアメリカの老夫婦などが、涙を流さんばかりの感激でフランス料理を食べていました。「マキシム」は、ドレスコードを守らない下品な客も入店させる。三ツ星の名店の品格が下がる、とマスコミは批判しましたが、「マキシム」は、お客さまが喜んでくれてこそのレストランだと、三ツ星を返上。この心意気に感動したことを、今でも思い出します。
じつは、私にはフランスアルプスの最高峰モンブランの単独登頂という目的がありました。パリに来て3年目にこの夢を達成し、1972年日本へ。そして、30代になって、自らに問いかけました。自分に残された道は何かと。そう、心の中に刻まれたあのパリの日々こそが、板前としての財産だと気づいたんです。だから、私にとって「ワインに和食」は、必然の結果でした。
フォワグラは、とろ火にかけてフォワグラ自身の脂で、ゆっくりと焼きます。湯がいた大根は北海道・羅臼産の昆布と鰹節の一番だしのスープで、1時間含ませ煮で仕上げます。器に大根を敷き、フォワグラをのせたら、中国産の「師塩」をほんのひとつまみ。召し上がったあとも、スープは絶品だ、と自負しています。

フランスから取り寄せている最上級のフォワグラの焼き加減、羅臼産の極上昆布と鰹節の一番だしをまとった大根。そしてソーテルヌの貴腐ワイン。そのハーモニーが五感を優しく刺激する。

小田島 稔 Minoru ODAJIMA
1944年生まれ。東京都出身。都立小石川工業高校時代から登山家を目指す。板前となったが、夢はフランスアルプスの最高峰モンブランの制覇。1969年パリへ。和食屋「たから」でワイン修業。71年モンブラン単独登頂。28歳で帰国。港区芝の実家で「お田しま」開店。その後、割烹「有栖川」を経て、90年、渋谷区神泉で割烹「小田島」を開店。2002年から港区六本木へ移転。ワインとフォワグラと大根という斬新なマッチングと技が、食通をうならせている。
長瀬広子=取材、文 依田佳子=撮影
本記事は雑誌料理王国第257号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は第257号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。