
7月10日、東京・九段会館テラスにて、フランス産チーズと日本やアジアの食材とのペアリングを提案するセミナーが開催された。
フランス全国酪農経済センター(CNIEL)は2024年から3年間、EUの助成を受けてフランス産チーズの魅力を伝えるキャンペーンを展開しており、今回のセミナーもその一環。
講師を務めたのは、“チーズのソムリエ”とも称されるCheesemongerのバスティアン・ファムラト氏。参加者は、5種のフランス産チーズとアジア食材を合わせた、ありそうでなかった組み合わせを体験。店舗でのチーズ提供の可能性も広げる貴重な機会となった。

講師を務めたバスティアン・ファムラト氏は、“Cheesemonger(チーズモンガー)”と呼ばれるチーズの専門家。フランス語では“fromager(フロマジェ)”と呼ばれ、チーズが日常食であるフランスにおいては、単なる販売員ではなく、選定・熟成・提案までを担う、信頼されるプロフェッショナルだ。言わば、チーズのソムリエといえる存在である。
フランス北部・サヴォア地方出身のファムラト氏は、パリのチーズ専門店に勤務したのち、2021年からは上海を拠点にアジアでの活動を展開。2025年2月より東京を拠点にし、精力的にフランス産チーズの魅力を伝えている。

「日本ではチーズに興味はあっても、そのまま食べる以外の楽しみ方をあまり知らない人が多いように感じます。また、店舗での提供方法や、扱う種類も画一的な傾向があります」とファムラト氏。
「フランスチーズはどんな風に味わってもいいし、もっと自由に楽しんでいいんです」。そんなメッセージから始まった今回のセミナーには、新たなメニュー展開につながるヒントが詰まっていた。

「フランスチーズの世界を楽しむ入り口として、まずは“AOP(原産地保護呼称)制度”を知ることが最適でしょう」と語るファムラト氏。AOPチーズは、フランスの土地や気候、伝統を映す“文化財”のような存在だという。
フランス国内には、1,200を超える種類のチーズがあると言われているが、その中でAOPに認定されているのは、わずか46種類に限られる。

AOP認証を受けるには、3つの条件を満たす必要がある。
“どこで、どんな原料を使い、どんな製法で作られてきたチーズなのか”を厳しく定めるこの制度は、各地の伝統を守るための仕組みであり、品質と“本物”の証でもある。

「チーズについての知識を深めることは、牧草地について学ぶことにつながります」。
そう語るファムラト氏の言葉には、素材の背景に目を向けるフランスの美意識を垣間見る。技術力の高さももちろん大切だが、料理のクオリティに本当の違いを生むのは、やはり素材の力だ。それは、日本と共通する価値観とも言える。
よい環境で育った牛は、よいミルクを出し、そしてよいチーズになる。どんな牧草地で育ったかが、チーズの品質を左右する大切な要素になる。

AOP制度においても、生産環境は重視されている。フランスの酪農は規模よりも質を重視する小規模経営が中心で、牛の健康や放牧環境に配慮した「持続可能な酪農」が根づく。
実際、フランスの乳牛の92%以上が牧草地で放牧されており、その内87%は年間170日以上、屋外で飼育されている。この「170日以上」という数字には雪の多い地域も含まれるため、実際には通年放牧を行う農場も少なくない。しかも、一頭あたり平均2,000㎡もの広い土地が確保されているというから驚きだ。
つまり、フランス産チーズは、“おいしさ”と“安心”を両立した食材なのだ。
「フランスでは、人間よりも牛のほうがずっといい環境で暮らしているんです」。そうファムラト氏がつけ加えると、会場には笑いが広がった。

セミナーでは、さらにフランスチーズを知るための基本的な知識として、主に飼育される6種の乳牛や、その飼育環境の違い、さらに技術的観点から分類される欧州のチーズのタイプについても触れられた。
フランスでは、その土地の風土が生み出す味わいの個性を“テロワール”と呼ぶ。「彼らの食べる草はその土地の自然そのものであり、そこから生まれるミルクやチーズもまた、“テロワール”の表現なのです」とファムラト氏は語る。
こうしてチーズの背景にある風土や文化を学んだうえで、セミナーはいよいよ、フランス産チーズとアジア食材をかけ合わせた5つのペアリング体験へと進んでいった。

「ペアリングで最も大切なのは、バランスです」。
そう語るファムラト氏がまず伝えたのは、チーズが“ローカルな食べ物”であるということ。つまり、土地の気候や文化に根ざしたチーズに、まったく異なる土地の食材を合わせるには、慎重なバランス感覚が求められるという。
「日本には本当に多彩な食材があります。だからこそ、ペアリングの可能性も無限大です。みなさんに伝えたいのは、うまくいかないことはあっても、“やってはいけない”組み合わせはないということ。自由に組み合わせて、楽しんでほしい」。
では実際に、どうやって食材を選び、組み合わせていくのか。ヒントとなるのが、ファムラト氏が語る“分母の発想”だ。
「これはあくまで僕のアプローチですが、まず飲み物を決めて、そこにチーズと食材を合わせていくことで、全体のバランスを整えていきます」。
ここからは、セミナーで紹介された5つのペアリングを見ていこう。

最初に紹介されたのが、白カビタイプのチーズ「ブリー・ド・モー」に、塩漬けした桜の葉と温かいウーロン茶を合わせたペアリング。春の和菓子を思わせる組み合わせが、意外なほどチーズと響き合う。
「ブリーは、パリを含むイル=ド=フランス地方周辺が産地で、熟成期間は4〜8週間。マッシュルームのような香りと非常になめらかなテクスチャー、もっちりした食感が特徴です」とファムラト氏。
店舗で提供する際は、こうした産地・熟成・味の特徴といった最低限の基本情報を伝えるだけで十分だという。「チーズは、まずはシンプルな説明で楽しんでもらい、少しずつ興味を深めてもらうのが自然なステップです」

白カビタイプのチーズは温度によって香りが開く特性があり、温かいウーロン茶を合わせることでブリーのクリーミーな旨みがふくよかに立ち上がる。脂肪分が口に残りがちなチーズに、ホットのお茶がやさしく寄り添い、口内をすっきりとリセットしてくれる。
「ブリーはタンニンの効いたワインとも合うチーズ。タンニンを持つ食材として、今回は桜の葉を選びました。僕は桜餅が大好きで、ブリーのもっちりした食感にも合うと考えました」
まずはブリーと桜の葉をゆっくり口に含み、風味のバランスを確かめてからウーロン茶を一口。ほのかに塩気を帯びた桜の葉の香りが和の余韻を添え、香ばしさのある茶葉の風味が全体をやさしく包み込む。
「塩気と甘い香りを持つ桜の葉がチーズの風味を引き立て、ウーロン茶の長い余韻を締めてくれる。すべてがやさしく調和するペアリングです」。
セミナーでは重ねて、ブリーと置き換えてペアリングができるチーズについても言及された。

続いて登場したのは、加熱圧搾のハードチーズ「ボーフォール・エテ」。エテはフランス語で夏の意味。つまり夏のあいだに高地で放牧された牛のミルクだけでつくられる、旨みの凝縮したAOPチーズだ。
山のチーズらしい力強さを持ちつつ、黄色みを帯びた生地と、ナッティで芳醇な香り、噛むほどに広がるミルクの甘みが特徴だ。グラタンやフォンデュなど、加熱しても香りが損なわれないのも魅力のひとつ。
合わせたのは、本わさびと純米吟醸酒という、一見ミスマッチに思える日本的な組み合わせ。だが、ファムラト氏はその意外性こそが、この組み合わせの醍醐味だと語る。
「もともと純米吟醸と本わさびの相性はいいと感じていました。また、僕は子どものころからボーフォールにマスタードをつけて食べるのが好きで、このペアリングにはそんな個人的な懐かしい記憶も重ねています」。

実際に体験してみると、わさびはやや多めにチーズの上にのせるのがポイント。ボーフォールの旨みとコクに、透明感のある辛味がふっと通り抜け、味に奥行きを加える。そこに純米吟醸を一口。やわらかな口当たりとフルーティな吟醸香が、ボーフォールの豊かな風味にすっと溶け込み、鼻に残るわさびの余韻とも美しく調和する。
「日本酒とチーズの相性に驚かれた方も多いのではないでしょうか。ワインであれば、オート=サヴォワ地方のフルーティな白が代わりになります」とファムラト氏。
また、ボーフォールは6か月から3年もの長期熟成をかけるチーズでもある。この日のセミナーでは、チーズの熟成に欠かせない「熟成士(アフィヌール)」の存在と、その高度な技術についても紹介された。

「こちらは伝統的なペアリングです」と、3つ目に登場したのは、アルプス地方サヴォワ産の非加熱圧搾タイプのセミハードチーズ「ルブロション」と、辛口のフランス産シャルドネを合わせた一皿。
フランスでも定番のこの組み合わせに、今回は中華スパイスの花椒(ホアジャオ)をプラス。舌をしびれさせるような麻味と刺激的な香りが特徴だ。
「熟成することでとろけるようなテクスチャーになり、野性的な風味とバターのようなコクが出てくるルブロションに、花椒のピリッとレモンのような爽やかさがとてもよく合うと考えました」とファムラト氏。

「花椒はインパクトが強いですが、チーズの熟成香と重なり、ぐっと奥行きが出てきます。ぜひ花椒の乗った面を直接舌の上に乗せて味わってください」。レクチャーに従って参加者たちが次々と実践すると、驚きや感嘆のどよめきが生まれていた。
しびれるような花椒の刺激と、ルブロションのまろやかなコク。その両方をシャルドネがすっと包み込み、口の中でまるで温度を帯びたような広がりを生む。温かい料理ではないのに、熱をもったような余韻が残る不思議な感覚だ。
「今日はパウダーを使いましたが、本当はオイルの方が、香りも味もさらに引き立ちますよ」。

4つ目に登場したのは、フランス北部・ピカルディ地方のウォッシュタイプチーズ「マロワール」。濃厚な香りとコクを持ち、“通好みのチーズ”としても知られている。
「マロワールは香りが非常に強いのですが、実は味わいはとても穏やかなチーズです。ピカルディ地方はドイツやベルギーに近いため、ワインよりもビールとの相性が良いと考えました」とファムラト氏。
そんなマロワールに合わせたのは、なんとかつお節。マロワールの動物的な香りに負けない強い個性を持ちながら、互いの魅力を引き立て合う絶妙な組み合わせだ。
「マロワールもかつお節も、どちらも発酵による香りを持っています。さらに、かつお節の燻製香が重なることで、香りのバランスが取れると考えました」。
凝縮された旨味をもつかつお節が、マロワールのやさしい味わいに奥行きを加え、ビールが軽やかに進む、絶好のおつまみになる。

「かつお節は“海の食材”なので、チーズが持っていない風味を補ってくれるとも思いました。フランスでも、マロワールとビールは“鉄板”とも言える定番の組み合わせです」。
今回のセミナーでは、日本のラガーを合わせたが、より軽やかなブロンドビールや、ロースト感のあるブラウンエール系とも相性が良いという。
「マロワールは香りが強いので、店舗で提供する際は保管方法に注意が必要です。ラップでぎゅうぎゅうに包むと酸素との接触が断たれて、アンモニア臭が立ち上がってしまうことがあります」。

セミナーの最後を飾ったのは、甘さ、香ばしさ、コクの層が重なり合う、デザートのような一皿。主役は、青カビタイプの中でも穏やかな味わいが特徴の「フルム・ダンベール」。これに、冷たいミルクアイスとドライいちじく、そしてココナッツのクラッカーを組み合わせた。
温かいコーヒーは、飲み物として添えるのではなく、アフォガートのようにミルクアイスの上から注ぎかける。チーズ、甘味、温度、香りが溶け合った、極上の“大人のスイーツ”が生まれた。
「できるだけたっぷりと口に含んで、しっかりミックスして味わってください」。なんだか楽しい食べ方の提案に、参加者たちからは笑みがこぼれ、会場の空気がふっと和んだのを感じた
オーヴェルニュ地方を代表するフルム・ダンベールは、ブルー・ドーヴェルニュのような力強い青カビチーズに比べ、クリーミーで塩気も控えめ。初心者にも受け入れやすい上品な風味を持つ。
「ロックフォールにハチミツを合わせるように、塩味のあるチーズに甘味を加えるのは、定番のアプローチです。今回はそこに、異なる食感の要素も重ねることで、ゆったりと余韻を楽しんでもらえるように工夫しました」。

フルム・ダンベールのやわらかな塩味がミルクアイスのミルキーさと重なり、ドライいちじくの濃密な甘みがコントラストに。さらに、ココナッツクラッカーの軽やかな香ばしさが食感と風味に心地よいリズムを与える。
「お店のメニューには、ストーリー性を持たせることも大切です。“最後のひと皿”として、こんなスイーツの提案はいかがでしょうか?」。
セミナー前にふと思いついたという、ココナッツクラッカーの代わりに“枝豆”を使うアイデアも披露すると、「ありあり」と言わんばかりに参加者たちが一斉にうなずくシーンも印象的だった。
「クラッカーの“カリッ”とした食感に対して、枝豆は“しっとり”かつ“ねっとり”としたテクスチャー。全体のなめらかさを引き立てる補完役として、とても面白い存在になるはずです」。

セミナー終了後、参加者たちはファムラト氏のもとに集まり、それぞれの感想や、自身のペアリングアイデアについて意見を交わしていた。
「皆さん、とても素晴らしいアイデアを持っていました。ただ、新しい発想が浮かんでも、それを試していいのか確信が持てないという印象でした。僕の答えはもちろん、“自由にやってみなよ”。フランスチーズはこう食べるべき、という固定観念がまだ根強いので、少しでもその壁を崩す手助けができたのならうれしいですね」と、ファムラト氏は笑顔を見せた。
ありそうでなかった発想で、異なる文化が自然に溶け合った今回のペアリングは、「店舗で再現しやすい」という点でも好評だった。参加者たちは、その実践的かつ創造的な提案に、大いに刺激を受けたようだった。
text: Yuki Kimishima photo: Hiroyuki Takeda
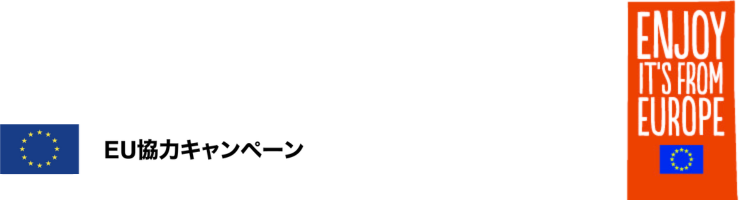
キャンペーンは、欧州連合(EU)の助成を受けて実施しています。ただし、本記事内に記載されている見解は著者自身によるものであり、必ずしも欧州連合やFranceAgriMerの見解を反映するものではありません。欧州連合や助成機関はここに記載されている情報の使用に起因するいかなる責任も負いません。

