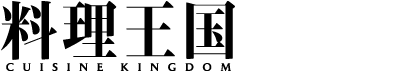国内のトップシェフが注目する「国産キャビア」に新しいプレーヤーが登場した。その名も「霞ヶ浦キャビア」だ。
茨城県がキャビアの生産に取り組む背景には、県の水産事業の高齢化や担い手不足といった人的な課題のほかに、霞ヶ浦や北浦が地球温暖化の影響により水温が上昇し、ワカサギやシラウオ、手長エビなどの漁獲量が減少しているという課題が挙げられる。そのような状況の漁業を安定的で持続可能なものとすべく養殖事業を進めているが、その一環として注目したのが、既に県にあった国内最大級のチョウザメの養殖用稚魚の生産業者だったのだ。県としても水産試験場を設置するなど生産性向上をバックアップ。そして県内の各キャビアメーカーと試行錯誤を重ねながら開発に取り組んできた。

国産においては、宮崎県、静岡県、岩手県、香川県などがメインプレーヤーとなりつつあるマーケットに、最もガストロノミーレストランの多い東京都に特に近い茨城県が加わってきた格好だが、その地の利は売り先に近いというだけではない。その開発にも東京都・京橋にあるシェ・イノの古賀純二シェフによる監修を受けることができた。そうして今回第一弾が完成し、同店にてお披露目されたのである。

シェ・イノといえば、故・井上旭シェフの遺志を古賀シェフが受け継ぎ、そして2022年10月には、この店が100年続くようにとさらに先を見すえて手島純也シェフを招聘したように、伝統的なフランス料理の味を大切にしながら、それを守るだけでなく未来へとつないでいこうと取り組んでいるが、今回はキャビアというフランス料理の王道食材に対して、敢えて日本らしさというエッセンスを加えたとのこと。
そのアイデアの1つが、原材料である霞ヶ浦産のチョウザメの卵本来の旨みを活かすために、塩分濃度を2.5%に設定したことだ。一般的な輸入キャビアはその保存性のために4%前後で作られることが多いが、「霞ヶ浦キャビア」は保存と旨みのバランスが整う適正濃度を古賀シェフとともに研究し、ここに設定した。
塩分濃度を抑えることで保存期間が短くなるというデメリットはあるが、繊細な舌を持ち、食材の元来の力の調和による一皿を作り上げようとする多くの日本人シェフには、広く受入れられる素材になったのではないだろうか。


国内のキャビア消費は年間20トン。現在は、その10%を国産キャビアが占めるまでに伸びているように、その市場には大きな変化が起きている。
この4月の出荷量はかなり限られており、次の出荷予定は23年11月頃まで待たねばならないように、当面の「霞ヶ浦キャビア」の目標は、シェアの獲得というよりもまずは生産体制、環境の構築やこの取組に対する地元の人の認知、理解の促進などに重点が置かれているが、茨城県にはチョウザメの養殖用稚魚を生産する国内最大の企業があるように、キャビアを作る基盤は既にある。卵が採れるまで成長するのに膨大な時間を要するチョウザメではあるが、「霞ヶ浦キャビア」は生産量の増加に伴って存在感を高めていくのも時間の問題になりそうだ。
text:小林乙彦(料理王国編集部)