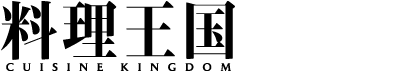アジアの発酵、日本の発酵#2

フォトジャーナリスト・森枝卓士にインタビュー
発酵はアジアと日本の 食文化OSである
日々の食を支える基礎構造としての発酵を、日本、そして日本をふくむアジアというスケールで考えてみるため、アジアの食文化に詳しい森枝卓士さんに話を聞いた。立ち上がってきたのは、魚醤文化、穀醤文化、うま味文化というキーワードだ 。
PROFILE
森枝卓士(もりえだ・たかし)
熊本県水俣市生まれ。水俣病の取材に訪れたユージン・スミスの影響で写真家・ ジャーナリストに。『カレーライスと日本人』『干したから…』ほか食文化に関する著作多数。大正大学客員教授。
発酵とスパイスが交わるところ、東南アジアから眺めてみる
うま味文化圏とスパイス文化圏
「うま味文化圏の西のギリギリは、バングラデシュあたりかなあ」とつぶやきつつ、森枝さんは『アジア菜食紀行』と題された著書の取材でインドへ赴き、ジャイナ教徒の家庭に居候したときのエピソードを語ってくれた。
「カブやゴーヤーなどの野菜とスパイスだけの料理が、本当においしいかった。スパイスは日本語で『香辛料』と訳されますけど、香りと辛味だけでなく、味そのものをつくり出すために使われていて、彼らの食文化は魚醤的なうま味がなくても成立するんだなあと、そのとき実感しました」
インド亜大陸に入ると、うま味の文化は見当たらずスパイス文化圏となる。面白いのは、インドを中心としたスパイス文化がベトナムをのぞく東南アジアにも色濃い影響を与えていること。タイなどにトウガラシを多用した辛い料理が多いのはご存じの通り。
「言語においても東南アジアにはインド文明の影響が古くからあり、タイ語やカンボジア語では抽象概念を表す言葉にインドの古代語であるパーリ語やサンスクリット語起源のものが多かったりしますね」
カレーの話とも相通じる。たとえばタイカレーの「ゲーン」は、ナンプラーやカピなどの魚醤と、トウガラシなどのスパイスがともに使用され、東南アジアが「うま味文化」と「スパイス文化」の交差点であることを象徴する料理の一例だ。金字塔的カレー論『カレーライスと日本人』の著者であり、「カレー大王」の異名もとる森枝さんに、次の機会にはぜひカレーからのアジア食文化論もうかがいたいところである。
「東南アジアから見るとわかりやすい、と最初に言いましたけれど、彼らは魚醤や穀醤のうま味文化を東アジアと共有し、スパイスの文化をインド方面と共有している。そうやって両方を見られるポジションが、東南アジアであるというわけです」
ここまで聞いて思うのは、現代日本人もまた「うま味とスパイス」を愛する人々であり、それを象徴するのがラーメンとカレーという大衆食なのではないか、ということ。伝統食文化だけでなく現代の食生活も、うま味とスパイスで読み解くことができるかもしれない。
開いて受容し、閉じて洗練する
最後に、少し角度の違う質問を。発酵のみならず、食文化の相互作用には人の移動が少なからず関係してきたはずだ。国際的な人の移動がコロナ禍で突然停止した昨今、これにより食文化そのものが変質していくのではないか。
「日本を歴史的に見ると、遣隋使、遣唐使の時代や、安土桃山のように異文化を積極的に受容していた時期があれば、江戸のように鎖国していたときもあって、弁を開いたり閉じたりの繰り返しに思えますね。閉じている時期には、内部での洗練や工夫が生まれる。だからこれからは、少し違ったものが出てくるのかもしれない」
過去にも、天災が食文化を変える大きな要因になってきた。
「コロナで今年前半に国立科学博物館で開催予定が中止になった『和食』展の図録で、明治以降の執筆を担当しました。何が日本の食の節目になってきたかというと、敗戦、オリンピック、万博といろいろあるんですが、とりわけ大きかったのが関東大震災。それを境に江戸的な食文化が払拭されて『東京』になったのだ、という話を書きました」
日本のみならず世界の文化の大きな節目になりそうな 2020 年。これから「閉じて」「洗練される」方向で食文化が変容していくのかどうか、まだわからないが、原点回帰とスペシフィックな深掘りを誘う「発酵」にわれわれの目が向いている状況は、ただの偶然ではないのかもしれない。
text ワダヨシ(ferment books) photo 森枝卓士
本記事は雑誌料理王国2020年12月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は2020年12月号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。