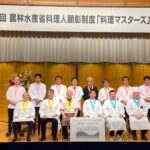農と食の連携を図るために農林水産省が2010年に始めた地域に根差した食文化の担い手として、料理人や生産者など、食にまつわる人々を表彰する「料理マスターズ」の授賞式が、11月17日、東京の帝国ホテルで行われた。
この料理マスターズは、最初の5年間はブロンズ表彰のみ、次の5年間は、ブロンズに加えて、過去のブロンズ受賞者の中からシルバー表彰者を選び、11年目となる今年は、新しくブロンズ・シルバーの受賞者が選ばれたほか、これまでのシルバー表彰者の中から初めて、3名のゴールド受賞者が選ばれた。なお、これまでに選ばれた受賞者の総数は89人となる。
ゴールド受賞者は、音羽和紀シェフ(オトワレストラン・栃木県)、中道博シェフ(モリエール・北海道)、森義文シェフ(カハラ、大阪府)。
授賞式の後には、この3名によるトークセッションが行われた。

音羽和紀シェフ(写真左)
「情報過多の中で、世界が画一化している。その土地に何があるかを考えないといけない。これからのシェフ・料理人は、皿の上だけのことを考えるのではなく、土地との関わりの中で、何ができるかを考えていかなくてはならない。そのためには、料理の世界だけでない、多くの人と交流することが大切だ」
中道博シェフ(写真中央)
「日本の料理のおいしさの核にあるのは、『みずみずしさ』だと考えている。志摩観光ホテルの故高橋忠之シェフの有名な言葉『火を通して新鮮、形を変えて自然』は、すなわちみずみずしいということではないか。今、モリエールグループ全体を対象に、社員食堂を作るプロジェクトを行っている。食材の『みずみずしさ』を味わうにはどうしたらいいか。ご飯は炊きたての30分が命、ということなどを、実感を通して伝えられるのではないかと思う」
森義文シェフ(写真右)
「20年ほど前から、地元で地引き網を行い、料理人が屋台を出して、地域の人や、業界の仲間と交流するという会を行っている。料理人同士がこの会での出会いをきっかけに、お互いに知識を共有し、一緒に食べ歩きを行うなどして、より調理技術が向上するのみならず、客も循環する良い循環が生まれている」
と、それぞれに語った。

また、飲食業界でも、サステナブルなアプローチが注目されるが、今回シルバーを受賞した「オテル・ド・ヨシノ」の手島純也シェフ(写真右から二番目)は、肉を育てる過程でのCO2排出が問題視される中、店のある和歌山は鹿や猪が多く、畑を荒らすため害獣として処分され、捨てられてしまっていたが、地元のジビエ専用の食肉処理施設と信頼関係を築き、丁寧に処理された状態の良い肉を、フランス料理の技法でおいしく仕上げることで、地元の人々のジビエ観を変えた。
また、魚に関しても、「フランス料理の基本は、日本と違って、『はしり』への執着があまりない。一番おいしい旬の盛りで食べる、という考え方」だからこそ、魚も幼魚を取ってしまうのではなく、ちゃんと大きくなった魚を、無駄なく食べることが、資源を守ることにつながると考えている。足繁く漁港に足を運び、漁業者の実情もよくわかるだけに、それが簡単ではないということも理解できる。「サステナブルについて知る料理人が、日々コミュニケーションをとることで、少しずつ変えていければ」と考えている。

手島氏のレストランがある、和歌山は鹿や猪が多く、畑を荒らすため害獣として処分され、捨てられてしまっていた。
手島氏が和歌山で仕事を始めた10年前は、まだジビエという言葉も一般的ではなく、地元の人たちは「ただ臭い肉」で、お金を払ってまで、食べたいという肉ではなかったという。地元の古座川町の町職員が、ジビエの処理施設を立ち上げ、その中でも、状態の良い、よりすぐりの肉が届く。
フランスで修業する中で、学んだジビエ料理で、まずくて臭い肉、というイメージを覆した。今では、レストランは県外のみならず、地元の人でいっぱいの人気店だ。地元の食材との有機的な連動で、少しずつ、地元の食を変え、ジビエの普及にも貢献している。
「サステナブル」を人前で口にすることはあまりないが、「フランス料理の基本は、日本と違って、『はしり』への執着があまりない。一番おいしい旬の盛りで食べる、という考え方」だからこそ、魚も幼魚を獲ってしまうのではなく、ちゃんと大きくなった魚を、無駄なく食べることが、資源を守ることにつながると考えている。
一方で、何度も港に足を運ぶうちに親しくなった、漁業者の実情もよくわかる。「サステナブルな漁法に変換するには、道具を変えたりと、お金もかかる。これまでのやり方を変えるのは、簡単ではない」時間をかけてでも、その大切さを伝え続けることで、次の世代の考え方を変えることができるかもしれない、とも考えている。

授賞式の前の週末、今回ゴールドを受賞した音羽シェフと共に、「トカイナカ」をキーワードにした都市づくりを考える、埼玉県の循環型農業を行う農園の視察の機会を得た。
まず、深谷市にある尾熊農場では、3400頭もの黒毛和牛を育てている。通常は生まれて24〜26ヶ月で出荷される所を、33ヶ月の長期肥育にすることで、赤身の旨味がしっかりある肉に育てている。頭数の多い牛の健康管理は、気圧差を感知する首輪をつけることで、横になっているか、起きているかなどの牛の動きをアプリで把握、問題があると携帯に連絡が入るようなシステムU-motionを全頭に導入するなど、人の目とITを併用した先進的な飼育法を進めている。さらに、処理に困る牛の排泄物を活用した発電所を建設、「どうしても出てしまう臭いなどで迷惑をかけてしまっているから」と、近所の住宅に格安で電気を供給している。

また、小川町の霜里農場はトイレの排泄物を、微生物の働きで浄化して無臭化するシステムを採用、浄化された水を畑に散布するなど、循環型の農業を行っている。野菜などを育てているほか、今は鶏のほか、黒毛和種に短角牛の血が混じった雌牛を育てている。夜は牛舎に入るものの、基本的には放し飼いで、餌は全て無農薬の自家製で、牛のためにわざわざ飼料用のカブを目の前の畑で育てている。音羽シェフは「地域の食と農の関わりには、様々な形がある。大切なのは、地域への還元とコミュニケーション。尾熊さんの発電所建設や、霜里農場の金子さんは、研修生を受け入れて、多くの次世代の農家を育てている。文化は簡単に生まれるものではないからこそ、継承していくという意識が大切だ」と語った。
料理人と生産者が連携して作る未来の食。より良い未来のための対話の時間が、これまで以上に進むことが求められている。

ワールド・レストラン・アワーズ審査員。
元テレビ山梨、テレビ神奈川ニュースキャスター。シンガポール在住時、国営ラジオ局でDJとして勤務。世界約50ヶ国を訪ね、取材した飲食店や食文化について日本・シンガポール・イタリアなどの新聞・雑誌に執筆中。