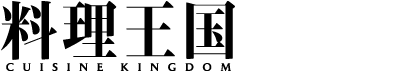中国料理はいつから日本にあった? 江戸〜昭和のグルメ本から読み解く中国料理

明治の文明開化とともに、海外の料理にも触れることになった日本人。しかし中国料理は、西洋料理に比べると、そんなに騒がれていなかったようだ。その理由は、どうしてなのか?
実は明治の人は、中国料理について、かなりの情報を持っていたのである。
中国料理の情報はきっちりあったお江戸の時代
江戸は鎖国の時代といっても、長崎を通じて清(当時の国名1636〜1912年)との交易はあり、国産の干しナマコなどは、幕府の重要な外貨獲得品でもあった。長崎には清国人の居留地、唐人屋敷もあり、町中で弁髪の清国人を見かけることもめずらしくなく、食文化の交流も当然あった。
江戸時代半ば、宝暦11(1761)年、バスエンチョンエンシキ長崎の人、山西金衛門は『八僊卓燕式キ記』というタイトルで、長崎に入港した清国船でご馳走になった記録を残している。金衛門は中国語が達者で、名字も、中国山西省からとったという中国通。食卓の形から素材、什器、コース料理の流れ、各料理の説明と、記録は実にこまやかで、漢字で表記したそれには、さすがの中国通、中国語のルビまでふってある。すでにこの時代、中国料理をベースにした卓袱料理が長崎に登場しており、それなら本場をとことん見せてやろう、という気持ちもあったのかもしれない。
卓袱と呼ぶ中国風の食卓を囲んで食べる卓袱料理は、かの地の影響を強く受けながら、長崎に誕生した長崎風中国料理。江戸時代の後半には江戸でブームとなり、高級料亭で名を馳せた「八百善」の当主栗山善四郎までも、自店ピーアールのために著した『料理通』第四巻のために、長崎へ卓袱料理を学びに出かけている。その四巻の挿絵には、長崎丸山で卓袱料理を味わう光景などが描かれ、レシピ集では、八百善流の卓袱ならびに普茶料理の数々が披露されている。
異国情緒たっぷりな卓袱料理や普茶料理などの書物の出版は、ほかにもあの手この手で相次ぐが、そんな光景を横目で見ながら、幕末に登場するのは『新編異国料理』。異国とは清国であり、本場もんの堂々たるレシピ本として、酒や茶の紹介、餃子なトンポーどの点心類、フカヒレやナマコの煮込み、東坡ロー肉など伝統のメニューもくまなく紹介されている。
こうして出版物から江戸の中国料理を見ていくと、明治に西洋料理が怒濤のごとく押し寄せ、やがて洋食というアレンジが生まれ、さらに本物の味への探究が始まる、という現象似てなくもない。江戸時代、中国料理は、知識階級の間でのピンポイントとはいえ、明治〜昭和にかけての西洋料理で起きた現象をも体験していたといえる。
そして、明治へと入っていく。
肉食解禁。本格的中国料理はセレブの私的な食卓から
明治となり、開港した横浜には、清国から大挙して人々がやって来た。欧米との交流が始まったといっても、日本人は言葉がわからない。ところが清国人は話せた。そして、日本人とは漢字で筆談が可能であり、活躍の場はいくらでもあったのだ。貿易に従事するほか、手先が器用なので建築や洋裁、印刷と、あらゆる面で才能を発揮した。食の面でも、西洋人の厨房で腕を振るうのは清国人であった。彼らが集い、住まいとしたのが今日の中華街の発端であり、彼らのための料理店もほどなくできてくる。
東京に本格的な中国料理の店ができたのは、明治12(1879)年、築地居留地にできた王
斉が経営する「永和斉」である。本格的な、とするのは、肉食が解禁されたことに関係する。江戸時代、中国料理の情報やハウツーはあっても、表向きに肉食はタブーであり、栗山善四郎が考案したレシピにも肉類はいっさい登場しない。獅子煮(肉だんご)はタコを使い、豚和えという料理には、アワビを豚の角煮のように切って油や味噌で仕上げた、いわばもどき料理である。食材を縦横に駆使できるようになった明治は、その意味で、本格的な中国料理の始まりといえよう。
永和斉は、「西洋料理よりもやや淡白にして」と、勘どころを押さえた宣伝文で賑わったというが、4年後の明治16年には、八丁堀亀島町(今の茅場町あたり)に、「偕樂園」がオープンする。実業界の大御所、渋沢栄一らの音頭とりで始まったこの店は、名士のクラブ的な存在でもあった。
明治28年出版の『實用料理法』には、この店への探訪記が記されている。「同園は、府下に名だたる支那料理の茶亭ゆえ、よりて他の茶亭にて調進しつるものも、さばかりは違わらざん」とあるように、すでにこのころ、偕樂園ほどではないにしろ、いくつかの中国料理の店はあり、偕樂園の探訪をもって、その概要を紹介しようとしたのである。
私たちも、筆者の後ろについて、その情景をちょっと覗いてみよう。経営者は日本人だったが、料理人は腕っこきの清国人をそろえていた。
シュロやソテツが青々と葉を繁らせた中庭を見ながら、筆者は、庭をぐるりと囲む廊下を経て、座敷に案内される。中国製の紫檀の食卓には、白紙に包みべにどうし紅唐紙で帯した箸、レンゲをのせた小皿が美しくセットされている。丸髷を美しく結った仲居さんに、「お酒は日本酒を温めますか」と問われるが、せっかくのことなので支那酒を注文する。すると早くも前菜2品「アナゴを甘辛く煎りつけたもの、鶏の肉を蒸して細く切りたるもの」が運ばれてくる。支那酒は「実に味わい苦く、ほぼビールに似たりけり。紹興酒と名づくとかや」と。琥珀色をした飲み物という連想から、ビールをイメージしたのだろうか。
同園のメニューは、上等、中等、並とあり、上等は四客以上一客につき1円50銭、中等は同じく1円、並は75銭。1円は、今でいうと1万円くらいか。といっても、明治後半の給料生活者の月給が10〜15円ということを思えば、庶民には手の届かないお値段。ちなみに筆者が選んだのは、中等だった。
さて、前菜に続く料理は「干しナマコとフカのヒレを細びきて、羹に調えたる魚翅雑拌。エビを小口切りにして、シイタケとサヤインゲンを細びきて、羹にした炸蝦仁。鶏肉の炒め。カニの肉をむしり、シイタケの細かく切ったものに煎り卵を合わせ、まろやかに湯葉にて包み揚げたる炸蟹包。そして東坡肉」と、今でも宴会料理にありそうなメニューである。
紹興酒には、いささか驚いたものの、食後に支那茶などすすり、イチゴをつまみながら、筆者がつらつら思い出すのは、食べ込んできた卓袱料理である。「食卓のしつらえといい、小菜用の支那焼きの器といい、まっことよく似とるわい」
そして、こうして座敷に座るスタイルではなく、あちら風に椅子式のほうが、もっと「興味も深まらし」などとちょっぴりの不満ももらしている。
ここで私が驚くのは、筆者のその余裕である。
同時代、ナイフとフォークに悪戦苦闘しながら西洋料理を食べていたことを思えば、同じ、海外の料理でありながら臆するところがない。
渋沢さんも、接待では肩をいからせ西洋料理を食べていただろうが、ここではリラックスして舌つづみを打っていたんでしょうね、きっと。
女学校の調理実習にも中国料理が登場
初手はセレブのプライベート・ディナー。お気に召せば、口に合うとわかれば、裾野へと広がるのは世の習いである。
明治44(1911)年、日本一の繁華街浅草に、「来々軒」誕生。数種類の麺類を中心に、ちょっとした料理も食べさせる、いわゆる町の中華屋さんの走りである。経営は日本人であったが、厨房スタッフは中華街からスカウト。名物は支那ソバとシュウマイで、支那ソバのお値段6銭なり。味は本場もん、ニッコリ大衆価格のこの店の大繁盛ぶりは、多くの人が書き残している。全国津々浦々で見ることができる「来々軒」という名の中華屋さん、これは大正と年号が変わる前年、浅草に生まれた同店から広まったのである。
明治から大正にかけ、「晩翠軒」「維新號」「陶々亭」「山水樓」と、数々の特色ある名店が東京に誕生。昭和に入ると、家族連れや宴会で、こうした店での味を多くの人が知るようになる。「最近のように、支那料理が皆様に歓迎されてきますと、支那の全卓料理も、作ってみたくなります」とあるのは、昭和8年「婦女界」という雑誌の付録についた中国料理紹介記事の前書き。当時の気分を物語る一例だろう。
大正の終わりから昭和にかけ、主婦という言葉が生まれて婦人誌ブームが起きるが、料理ページは目玉のひとつ。中国料理もさまざまな切り口で紹介され、先に挙げた名店のシェフたちも、家庭に向けた自慢の味を誌面で披露しており、今、私たちが思い描く中国料理のすべてが出尽くしているといっていい。
女学校の料理実習でも、中国の味が登場。昭和6年発行の「女学校用お料理実習」には、手打ちの麺、スープ、ギンナンで作るデザートのほか、名月の献立として、栗ごはん、松茸と焼き麸の清汁に、主菜は東坡肉となっている。ちょっと首をかしげる献立だが、実はちゃんとソトウバ意図がある。東坡肉といえば蘇東坡であり、詩人でもあった彼が、月明かりに乗じて舟遊びをしたと歌った「前赤壁賦」にちなんでのこと。先生たちは、料理実習の前に、この漢詩を披露し、蘇東坡について語ったのだろうか。かなり上級の情報量のもとで学んでいたことになる。
しかし、世の中が平穏なのも昭和1桁の時代までで、10年代に入ると、戦争の暗い影が覆いはじめる。ここでまた中国料理は、新たな展開をみせる。油を使うので栄養的なこと、あるいは手近な材料で作れることなどに、価値が見いだされていく。
昭和12年、「料理の友」という雑誌では「栄養本位支那精進料理」「廃物を出さぬ支那惣菜料理」を、立て続けに付録として出している。
支那精進料理で紹介されるレシピは、ナス、ホウレン草、キノコ類、ダイコンやニンジンなどの野菜を使っているが、実は今そっくり「ヘルシーベジタブル料理」のタイトルで紹介しても、キッチリうけそうな内容である。「廃物を出さぬ〜」のほうは、食糧生産が窮乏してきたことを受けてのことだが、当時、魚介類は豊富であった。そこでイワシ、サバ、アジ、数々の白身魚、イカ、貝類を使ったメニューとなるが、これも「チャイナのシーフード料理」として使えそうだ。
ここで注目したいのは、それまで中国料理の紹介記事で必ず顔を見せていたフカヒレ、干しナマコ、燕の巣といった高級食材が姿を消していることだ。戦局を控えての苦しい実情を反映したものであったが、はからずも中国料理は、よりいっそう身近な味になったのである。
福地享子 文
雑誌や単行本の編集、執筆業をこなしつつ築地の魚河岸で働く。趣味で古書、古い雑誌の収集をしており、とくに料理書や婦人誌に希少なものが多い。
本記事は雑誌料理王国第159号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は第159号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。