
2021年4月5日〜10日、昨年アジアのベストパティシエにも選ばれた庄司夏子氏による、東京・渋谷の「été(エテ)」にて、同じく昨年「アジアのベストレストラン50」で4位に輝いた香港「ベロン」のダニエル・カルバート氏が東京に拠点を移し、満を侍してこの6月1日にフォーシーズンズホテル丸の内 東京に開業する「Sézanne(セザン)」とのコラボレーションが行われた。
元々は「ベロンの料理に惚れ込んだ」庄司氏が、2年前にカルバート氏の東京訪問の際にエテに招待したことがきっかけで交流が始まり、今回のイベントにつながった。庄司氏は、ファッションブランドやアーティストとのコラボレーションも多く行うが、それらの世界は、料理と同じく、華やかさの裏側に緻密な手仕事、職人魂ともいえるものが背景にある、と感じているという。そんな手仕事を体現しているシェフが、カルバート氏だ、と感じているという。実際、カルバート氏はトリュフのミルクレープなど、細かい手仕事を愛好する職人肌。そのカルバート氏は、庄司氏の技術のみならず、アーティストとのコラボレーションを含めたエッジの効いたラグジュアリーな空間づくりなどの世界観にも学ぶことが多い、と語る。「手仕事をアートに昇華する」そんなテーマを感じるコラボレーションだ。
もう一つの二人の共通点は、無類のシャンパン好きであること。カルバート氏の新しい店の名は、祖父母が別荘を持っていたシャンパン地方の村にちなんでおり、子ども時代からの幸せな記憶と結びつく飲み物だという。また、庄司氏は、店で使うことが多い魚介類との合わせやすさも、シャンパンの魅力だと語る。
今回は、シャンパンの帝王とも呼ばれるクリュッグのグランキュヴェがセットになっており、そのマリアージュも考えたコース構成。実際に見ていこう。


エテを会場に、今回はフォーシーズンズホテル丸の内 東京の、シンガポールや香港で豊富な経験を持つマネージャークラスのベテランがサービスする機会となった
(料理名の後のアルファベットは担当したシェフCはカルバート氏、Sは庄司氏)

フランスのビストロの定番、ラディッシュとバター。フレッシュな生のラディッシュの辛みをバターで和らげるという組み合わせ。これを、フランス・ボルディエのバターでコーティングし、Sézanne(セザン)が国内唯一の取り扱いという、ペトロシアンのキャビアを一粒一粒飾るというラグジュアリー版として登場させた。
こういった細かい手仕事は、本質的にカルバートシェフが好むもの。
濃厚な旨味のペトロシアンのキャビア、口内の温度でバターが溶けるにしたがってキャビアの香りも解き放たれ、クリュッグの持つ樽香と共に立ち上る。生のラディッシュのみずみずしさとほのかな苦味が、濃厚な味わいのバランスを取る構成になっている。

さっくりとしたサブレ生地の上に生うにを乗せるのがエテでの定番だが、間にフォワグラのクリームを挟み込み、上に塩漬け卵黄を削ったものと、季節の花山椒、金箔を飾った。油脂のコクという構成はカルバートシェフのラディブールと対になるような印象。もともとはフォワグラを使っていなかったものの、「ベロン」でのカルバートシェフの冷製フォワグラの前菜へのオマージュから今回は特別バージョンに。花山椒の清涼感のみならず、中心にはほんの少しだけ自家製のガラムマサラのエキゾティックさを忍ばせて、華やかでボリューム感のある味わいに。

24ヶ月熟成、軽い酸味のある薄切りのコンテチーズに、48ヶ月熟成の濃厚で温かなクリームを詰めたグジェール。一転して味の要素はシンプルに、温度感やテクスチャの違いで、同系の味のレイヤーをシックにまとめた。
どれも、乳脂、フォワグラ、ウニなどのコクの有る素材で、口の中でとろけ、一緒に提供されたプレステージシャンパンのクリュッグ・グランキュベの酸と乳化して完成されるように構築されているように感じられる組み合わせ。

とろけるギリギリの温度感のさっぱりとしたヨーグルトのアイスクリーム、ほのかにエキゾティックなアクセントとなるカルダモンをかけて。冷たいガスパチョとフルーティなオリーブオイルを添え、乳と酸のコントラストを落ち着かせた、軽やかなトーンで一休みといった印象。

ベロン の名物といえば、クラストは香ばしく、内側が水分量たっぷりでもちもちとした焼き立てのサワードゥブレッド。カルバートシェフが香港から持ってきた5年もののスターターを使い、今回は沖縄のスイートコーンを加えたコーンブレッドに。スイートコーンを軸ごと香ばしく焼き上げ、粒を外してから細かく砕き、ポレンタにしてから練り込んだ。香港時代よりも、旨味がより濃厚になったのは、日本に移ったせいもあるのかも知れないと感じた。庄司氏の手によるスモークバターはスライスしたローストアーモンドを散りばめて。

ふんわりとしたかき氷の山を背景に、小さなスダチの中には、アボカドのクリームと、シャンパンに欠かせないものとして、カルバートシェフがこだわりで特別に入荷した、ペトロシアンのキャビア。中でもロシア皇帝の呼称を冠した、ツァー・インペリアル・オシェトラ、塩気はあまり強くなく、濃厚な凝縮感とナッティな後味を楽しめるキャビアは「Sézanne(セザン)」でも使用予定だとか。伝統的にはサワークリームと合わせるキャビアだが、植物性のアボカドと合わせ、スダチの酸味とほのかなえぐみを効かせた軽やかな仕上がりに。

さらにこちらも旨味素材の競演。白えびの下にはロワール産のホワイトアスパラガスの角切り、そしてさらにタラでとったまろやかなフュメと合わせたホワイトアスパラガスのクーリ。

カルバートシェフが、香港の「Sushi Shikon(すし志魂)」で学んだと言う、甘酢で〆たサバ、その間にタイバジルを挟み込んで軽く冷燻にしたもの。「ゼラチンで少し固めてあるのですが、その工程はテリーヌ作りの考えを応用していて、クラッシックなフランス料理を学んできたシェフならではと感じました」と庄司氏。
ハマグリのエスカベッシュは、やや甘めでコクのある味付け、甘い香りのタラゴンとイタリアンパセリが混ぜ込まれている。

「若竹煮にインスピレーションを受け、わかめの代わりに海藻の香りと旨味を持った鮑と組み合わせました」と庄司氏。えぐみを抜いてから牛のコンソメで煮含めたタケノコの表面をバターで香ばしく焼き上げ、蒸したアワビのスライスを飾って。間にはアワビの肝、しっかりと炒めたマッシュルームのペーストなどの濃厚なソースを挟み込んで。

濃厚なバター感の残る口内を洗い流すような一皿。
あっさりとしたハマグリの出汁がまず提供され、焼き立てのアマダイの松笠焼を庄司氏が一人一人の皿に入れてゆくと、ジュワッという音、広がる湯気と共に、食欲をそそる甲殻類のようなアマダイの皮の香りが広がる。小口に切ったセリ、細切りにしたウルイと、春の野菜が野趣と清涼感を加えている。
北海道産鶏のポシェ ヴァン・ジョーヌ ペルテュイ 産アスパラガス 編笠茸 C


ここで登場するのは、北海道産の鶏。香港の「酔っ払い鶏」をイメージし、鍋で煮た後に1週間、旬のモリーユ茸とジュラワインに漬けたもの。中華圏では、比較的高価なジュラワインに代わりに中国酒を使ってソースを作ることもありますが、こちらはその真逆。そして、そのマリネ液を詰めたものに、鶏ガラから取ったトリプルコンソメを合わせたソースと共に。鶏の皮の下には、ポルチーニ入りの鶏のムースを入れて、ふくよかな印象に。添えてあるのはプロヴァンスの有名産地、ペルテュイのグリーンアスパラガス。手法や食材自体はフランス料理のものだが、ベースになっている味の構成は中国料理。カルバート氏は「4年間香港で暮らす中で、自分の味覚も香港に合ってきたからこそ生まれた料理。11月に日本に来てからは、産地訪問に加えて日本中の名店で食べ歩き、これからは、日本の味のバランスを自分のものにして、新しい料理につなげて行きたい」という。


フラワーアーティストの東信氏の作品、アクリルにイチゴを一本丸ごと閉じ込めた器は、庄司氏のコレクションで「私たちの作る料理も、同じアートである、ということを伝えたい」という思いから。フッレッシュなイチゴのジュースにシャンパン、イチゴのムースをゼラチンで包んだ球体を浮かべて。

そして、庄司氏のシグネチャーのマンゴーケーキ。さっくりとしたサブレの上に、濃厚なクリーム・ディプロマ、そして美しく薔薇の形を象ったマンゴー。芯の部分の作り込み、自然に広がる花弁の重なり方など、ファッションメゾンに通じる繊細な仕事ぶりが感じられる一品。
華やかさが先立って捉えられがちな庄司氏だが、「6席のレストランだけに、みんなにおいしいと言って帰ってもらいたい」と、多くの人に好まれるストライクゾーンにぴったりと投げ込む堅実な料理が印象的だった。
カルバート氏が日本に拠点を移した大きな理由の一つは、最上級の日本食材を知りたいということ。その知識欲は止まることを知らず「今朝も4時起きで豊洲に行ってきたところ」だという。開店後も週に数回は豊洲に通い、リピーターにはその日仕入れた食材での新しい料理を随時提供していく予定ということで、意欲的に日本の味のバランスを吸収し、進化してゆく料理が楽しみだ。
どちらのシェフも、モダンなプレゼンテーションを行いつつも、根本の味の構成は手堅く、下ごしらえの手間を惜しまないのも共通点。全体的に、小さめのポーションでありつつもコクと旨味を凝縮させて満足感につなげていて、プレステージシャンパンやグランヴァンを受け止める度量の有る料理の数々。どちらも、美食のみならず、美酒を愛する人にもぜひ訪れていただきたい店だ。
4月20日に発表された、次世代を担う世界の若手飲食関係者を選ぶ新しいアワード50Nextでも「起業家的クリエイティブ」として選ばれた庄司氏は、女性シェフのロールモデルとして世界からも注目されている。エテの厨房では、まだ20代前半の女性スタッフ2名が働いており、カルバート氏もこの度女性スタッフを参加させ、まだまだ日本で少ない女性シェフの育成にも意欲的だ。そんな新しい時代の息吹も感じたコラボレーションだった。

仲山今日子=取材、文
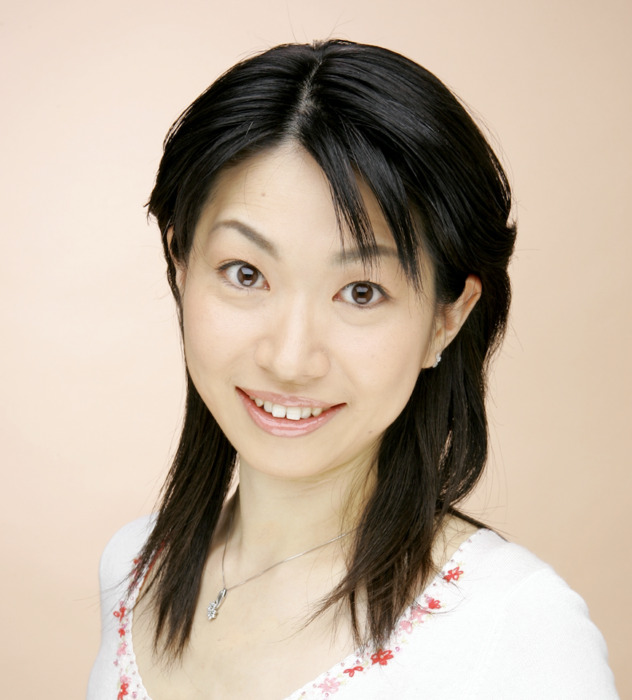
仲山今日子
ワールド・レストラン・アワーズ審査員。元テレビ山梨、テレビ神奈川ニュースキャスター。シンガポール在住時、国営ラジオ局でDJとして勤務。世界約50ヶ国を訪ね、取材した飲食店や食文化について日本・シンガポール・イタリアなどの新聞・雑誌に執筆中。

