
寿司とフレンチ。どちらも人気の食のジャンルではあるが、両方を一つのコースの中で味わった人は多くないだろう。そんな既成概念を覆すコラボレーションが、5月1日にフォーシーズンズホテル東京大手町のフレンチレストラン「エスト」で行われた。
会場ともなったエストは、季節感と日本のテロワールを表現し、食べる人の感情に訴えかける料理を、と元ミッシェル・トロワグロのギョーム・ブラカヴァル氏が自らのスタイルを表現するモダンフレンチの店。「寿司とのコラボレーションは長年の夢だった」というブラカヴァル氏にとっては念願のイベント開催となった。
銀座の寿司「はっこく」佐藤博之氏は、以前にパリで一度行ったことがあるものの、国内でのフレンチとのコラボレーションは初めて。「オープンマインドで、色々なことにチャレンジしたい」と、今回のオファーを受け入れた。

寿司とのコラボレーション、と聞いて一番気になったのがサービス方法。エストは客席を望むガラス張りの壁の向こうにキッチンがあり、調理をするシェフの姿、ライブ感も楽しめるが、通常寿司はカウンターで、握りたての瞬間の鮮度と、その間のコミュニケーションも寿司の楽しみの一つ。「サービスも含めて楽しんでもらう、寿司のグランメゾンを目指したい」という考えを持つ佐藤氏は、移動式のテーブルを持ち込み、テーブルごとの「出張寿司」スタイルに。1テーブル4人まで、席数を減らして計30席に限定し、時間差で予約をとる事で、はっこくで右腕を務める齋藤淳氏と共に、客席を移動しながら常に握りたての寿司を提供できるようにした。そこで生きたのが、ラグジュアリーホテルならではのサービス力。初回ではあったものの、バタつく事なく「こんなにスムーズなコラボレーションはなかなかない」と、佐藤氏も驚くスムーズさ。サービスは、パリのフォーシーズンズ・ジョルジュ・サンクなどで経験を積んだ、エストのマネージャー、ジョナサン・モンソー氏が取り仕切った。

また、板前という言葉があるように、切りつけは昔から日本料理の華。レストランを入ってすぐのところに固定のカウンターを設置し、前菜の盛り付けステーションにしている。こちらも、寿司店のようなライブ感が目でも楽しめる演出だ。
それでは、その全料理を見ていこう。

まずはエストの定番、カリッとして香ばしいじゃがいもの生地を使ったタルト。一つ目はパースニップとフェンネルルート、フェンネルのさっぱりしたもの、二つ目は若干フレッシュさを残した玉ねぎの味わいが残る、クリーミーな男爵じゃがいものピュレに、黒トリュフのクリームという濃厚な味わいを組み合わせて。エストは、軽やかでモダンなアプローチを取りながらも、クラッシックな味わいや味の組み合わせを大切にしている。そんな2つの視点がタルトのフィリングからも感じられる。

はっこくのシグネチャーとも言える、「突先」と呼ばれるマグロの頭の部分の手巻き。手渡しで受け取り、パリパリの海苔が楽しめるのも、この「可動式カウンター」のおかげ。マグロの有名卸「やま幸」の天然マグロのみを提供するが、「マグロの中でも好みなのは100キロ程度で大きすぎず、脂の乗っているもの」なのだとか。今回は静岡・下田産の巻網のもので、大きすぎないためか、きめ細かく繊細な身質と、巻網ならではの酸味も楽しめる。今回は1週間程度寝かせてあるものの、熟成ありきで逆算して作る寿司ではなく「元々寿司は冷蔵庫のなかった時代にどうやって魚をおいしく食べるか、という考えの元編み出された」という考えのもと、冷蔵庫のある今の時代のやり方で、魚ごとに違うおいしさのピークで提供したい、という。しっかりとした赤酢の酢飯はコクのある濃厚な赤酢を酸のある赤酢で割ったものに塩を加えただけで、糖分を足さない酢飯。米は、熊本で無農薬で育てられている、原種に近い米、朝日一号を使用している。一つの穂につく米粒の数は少ないが、その分しっかりと味が凝縮している。「オーガニックや無農薬の食材をなるべく使い、食材の魅力を引出したいという」ブラカヴァル氏の素材へのアプローチとも重なる部分があるように感じた。

このコラボレーションのために、特別に作った皿。元々ブラカヴァル氏はクリームを控え、豆乳に置き換えるなど、植物原料を使うことで食後感を軽やかにする料理を提供しているが、こちらも、ソースは白アスパラガスの根元の部分を絞ったコールドプレスジュースに、クリームの代わりに豆乳でコクを加えた温かいソースを使っている。
佐賀産の白アスパラガスはバターでソテーし、生の状態のスライスをリボンのように飾り、たっぷりとキャビアリのクリスタルキャビアを乗せ、みりん、醤油などで煮た昆布をパウダーを散らした。
アスパラガスに添えられる卵黄を使ったサバイヨンソースの代わりに魚卵のキャビアのコクと旨味、そして昆布と豆乳の大豆、みずみずしく甘い白アスパラガスと、様々な種類の植物性の旨みのレイヤーを重ねる構成だ。寿司につながる流れを作るためにブラカヴァル氏が考案した、フランスの春の味の日本的表現。

通常はっこくでは、23カンの握りのみの提供で、箸休め的に野菜の小鉢を挟む構成となっているが、今回はフレンチとのコラボという事もあり、刺身を野菜と盛り合わせた。
比較的さっぱりとした赤身、中トロ、シンプルに酒と塩で程よい柔らかさに蒸しあげた島根産の黒アワビ、しっかりと昆布の旨味が乗ったアイナメ。みりんと水で割った煮切り醤油を添えて。醤油をあえて甘味のあるラディッシュやニンジンは、仙台味噌ベースのソースに絡めて。

おぼろをかけた、コハダ、ネギとカツオは、この日届いたばかりの鹿児島出水の春子鯛(チダイの幼魚)はもっちりとした食感。薄塩をして皮目を湯霜して柔らかくしてから、全卵に酢を入れて作る「酢おぼろ」をまぶして。伝統的な仕事も大切にする佐藤氏、赤酢のしっかりとした酢飯だが、いわゆる長期熟成系の寿司ではない。「江戸前の仕事は冷蔵庫がなかった時代の保存のための手段。基本的に寿司の起源は獲れた魚と酢飯をさっと合わせて食べるファストフード。休ませるのは大切ですが、魚の香りが感じられる新鮮なものを、一番おいしく食べる方法を考えていきたい」と考えている。

シュッとした細身の姿が粋な天草産のコハダは、しっかりめに〆てあり、キリッとした味わい。

千葉県勝浦の初カツオをネギと生姜、二つの薬味を重ねて、タタキを食べるような味のコンビネーションに。

和歌山産の柔らかいフィレ肉をプランチャで焼いて、辛みよりも柚子の香りが際立つブラカヴァル氏の自家製の柚子胡椒を乗せ、大根やラディッシュのピクルスを添えてあります。ピクルスの甘酸味がちょうど寿司酢に近いもの、あえて苦味を残したものと、バランスを変えてあったのも印象的。「寿司で魚が出るので、野菜と肉で何ができるかを考えました。酸味、辛みと苦味で肉の脂を軽やかに、また寿司に合わせて、少しソースを軽めに仕上げています」

和牛の鉄分とサシのバランスと後半の寿司の継投役のように感じられたのが、静岡県下田産の10日ほど寝かせた130キロの本マグロ、上質でナッツのような甘い脂が楽しめる背なかの中トロ。

甘味と柔らかい食感が楽しめる鹿児島県産の車海老は、鮮度を生かし、甘みが出るギリギリの浅い火入れが印象的。「今の時代は鮮度の良い食材が手に入るので、それに合わせてベストの調理法も変わるはず」と佐藤氏。

道東のバフンウニを使った軍艦は、ウニが多め、酢飯が少なめの贅沢なバランスで、まさにクリームのようにとろけるウニをたっぷりと味わえる。海苔は有明産一番摘みの香りがよく旨味もあるもの。

対馬産のアナゴはウニを握り終わった後にスタッフの方が厨房であぶったばかりのものを持ってきて、温度感もきちんと楽しめる連携プレー。甘すぎないツメを少しかけて、アナゴ本来の味が楽しめる仕立て。素材の味をきちんと味わって欲しい、という思いが伝わってくる。仕上げに清涼感を感じる青柚子の皮をかけて。

たっぷりの芝エビと芝エビの出汁を使っているということで、しっかりとした香りがありつつ、ブリュレのような表面のカリッと感と、プルプルの柔らかい食感が魅力の玉。

「玉は寿司におけるデザートのような位置づけ」としつつも、とは言え「寿司の最後にフレンチのデザートが食べられたら最高なのに、と常に考えてきた」と話すのが、ブラカヴァル氏とミッシェル・トロワグロ時代からコンビを組む、ペストリーシェフのミケーレ・アッバテマルコ氏。上質なオーガニックな食材をなるべく使い、砂糖を控えた自然な味わいを追求するアッバテマルコ氏がプレデザートとして考えたのは、フローラルな香りと酸味をテーマにしたルバーブのデザート。アーティストのマーク・ロスコ氏の絵画「ルージュ(赤)」にインスピレーションを受けた四角いタルト。一番下には濃厚な旨味と自然な甘味の極薄い栗のサブレ、フランボワーズとティーベリー(ブラックベリーとラズベリーの交配種)、カシスのムース、その上からルバーブの薄いゼリーをかけて仕上げた。サイドにはエルダーフラワーとヨーグルトのアイスクリームを添えた。

そして、アッバテマルコ氏のシグネチャーとも言えるミルフィーユ。こちらは、軽やかでありつつも、「グルマンディーズ」を踏襲した、しっかりとした味わい。フィユタージュにクリームを挟んだだけのように見えるシンプルなルックスだが、ミネラル感のあるイタリア粉を使った極薄のフィユタージュの間には、実はバタークリームとヘーゼルナッツのペースト、ヘーゼルナッツムース、コーヒームース、バニラの効いたクリームシャンティイなどをホワイトチョコレートで薄くコーティングした、様々な味の層が隠れている。一番上には薄い飴、オパリーヌの層で、カリッとしたフィユタージュの表面の印象を強めている。
周りはアングレーズソースに見立てたヨーグルトとカリンのソース。トロワグロ出身らしい酸味を生かした一皿だ。

シャキシャキのリンゴの果肉の食感が楽しめる青リンゴの形のチョコレート、グルマンディーズを体現する、とてもクリーミーでコクのあるヘーゼルナッツのプラリネチョコの2つを。「自然の味わいを生かし、甘さを控えた軽やかでヘルシーさと、フランスの伝統的な甘味」という、二つの視点のどちらも大切にしているエストらしい締めくくり。

今回、寿司ははっこくで出しているそのままを提供したという佐藤氏、普段提供している野菜の小鉢の代わりに今回はフランス料理が「合いの手」として入る形となったが「フランス料理と寿司の良いところ取りのようなコースで、自分も食べたくなった」と充実したコラボレーションを振り返った。
確かに、時間のかかるソース作り、味の構造も含めて、細かいレイヤーを「積み重ねる料理」であるフランス料理。一方で、ものによっては素材を寝かせる時間はあるものの、基本的には獲れた魚を切って握り、すぐ食べる「瞬間の料理」である寿司。食材へのアプローチがある意味対照的な、どちらも楽しめる、メリハリの効いた構成となった。
とはいえ、シンプル=簡単、という意味ではもちろんない。ブラカヴァル氏が「お客様の前で握る寿司はやり直しがきかない。酢飯のバランス、切り方、温度。シンプルであるからこそ難しい」と言えば、アッバテマルコ氏も「和菓子も、シンプルな食材しか使っていないのに、様々に異なった形、食感が表現できる。シンプルに見えるものの裏に技術がある、日本の文化を心から尊敬したい」と話す。
トロワグロといえば、柑橘や酸味の使い方が特徴だが、7年半のトロワグロでのキャリアの中で、それを自然に吸収したブラカヴァル氏の酸味使い、赤酢を使い、マグロがシグネチャーで、しっかり味の輪郭をつけながらも、素材感を生かしたはっこくの寿司の相性は想定以上。今後もコラボレーションを考えているということで、注目したい。
仲山今日子=取材、文
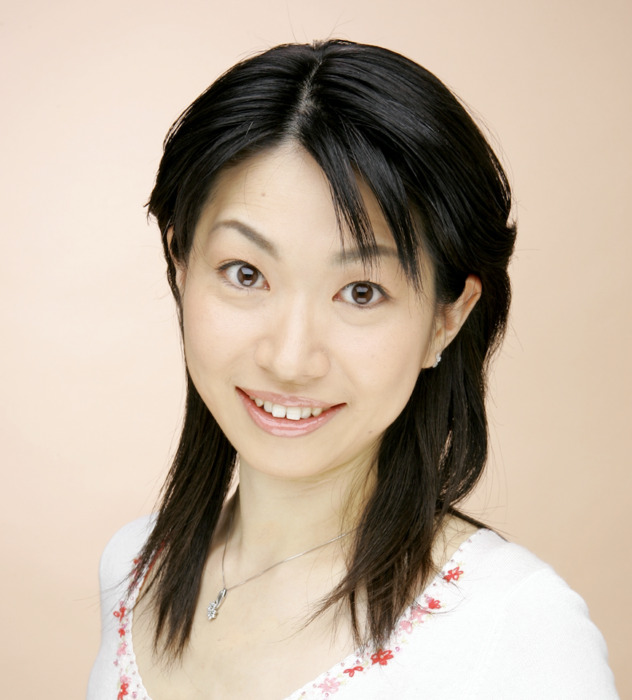
仲山今日子
ワールド・レストラン・アワーズ審査員。元テレビ山梨、テレビ神奈川ニュースキャスター。シンガポール在住時、国営ラジオ局でDJとして勤務。世界約50ヶ国を訪ね、取材した飲食店や食文化について日本・シンガポール・イタリアなどの新聞・雑誌に執筆中。

