
10月、東京・日本橋「ラ・ボンヌターブル」をはじめとする都内3店舗で、「浪江フェア」が幕を開けた。請戸漁港の魚介“請戸もの”や地元農産物を用いた特別メニューが登場する予定だ。その開催に先立ち、中村和成シェフが海外インフルエンサーとともに浪江町を訪問。生産者の情熱とともに、復興の歩みを重ねながら磨かれてきた食材のポテンシャルを再発見する旅となった。

福島県浜通りに位置する浪江町。太平洋の豊かな漁場と肥沃な農地が広がり、海と大地の恵みが交わる土地として、古くから漁業と農業が人々の暮らしを支えてきた。
しかし2011年3月11日、東日本大震災で震度6強を観測。15mを超える津波に襲われた浪江町は、加えて福島第一原子力発電所から約8kmという距離にあったため原発事故の影響を受け、震災翌日には全町民が避難を余儀なくされた。
震災前に約2万人いた人口は一時ゼロに。日常が突然途絶え、漁港も田畑も長く人の手から離れたままとなった。その後も帰還は容易ではなく、現在の人口は震災前の一割、約2千人にとどまっている。

それでも少しずつ、浪江の海と畑には再び人々の姿が戻り、かつての風景を蘇らせつつある。失われた時間を取り戻すように、なかでも「食」をめぐる取り組みは、力強く再生の歩みを進めている。
「震災直後、会社の取り組みで被災地へ料理を届けに行きました。自分はまだ若手でできることも限られていましたが、食を通じて地域とどう向き合えるかを考えるきっかけになりました」と当時を振り返る中村シェフ。

請戸漁港で水揚げされる魚介は、かつて“常磐もの”と呼ばれていた。浪江・請戸の鮮魚を指す言葉は、その評判が広がり、やがて浜通り全体の海産物を示す総称へと変化していった。
震災後、請戸漁港は原発事故による風評被害が根強く残り、漁業者は安全性を訴え続けながら市場の信頼回復に努めてきた。そうした中で、古くからの地元の呼び名“請戸もの”をあえてブランドとして前面に掲げ、差別化を図る。その名は全国で品質の高さを認められ、いまや復興の象徴としても広く知られている。

福島沖は親潮と黒潮が交わる潮目の海で、魚種の豊富さと身質の良さから「宝の海」と呼ばれる。古くから築地市場でも高い評価を受けてきた“請戸もの”は、震災による9年の休止を経て、2020年に競りを再開。
しかし、漁船は94隻から29隻に減り、月12日ほどしか漁に出られない制限もあるが、漁師たちは魚価維持と資源保護を両立させながら水揚げを続けている。

震災後に整備された競り場では床にパレットを並べ、その上をカゴをすべらせたり、生魚を配置する仕組みを導入。作業効率が高く、スムーズに競りが進む。競りの見学に訪れた中村シェフは「豊洲と比べても魚がきれい。清潔でシステマチックな流れに驚いた」と、流れるように進む競りから目が離せない様子。
震災前と比べて温暖化も影響し、漁獲種や時期は変動しているものの、ヒラメやカレイに加え、トラフグが新たな主力として存在感を増している。
昨年には「請戸もの」のロゴマークも制定され、ブランド発信力はさらに強化された。漁業体験や食イベントなど新しい試みにも積極的で、若手や女性漁師の姿も増えている。港には、復興を担う新しい世代の力が息づいていることを、中村シェフも感じ取っていた。
相馬双葉漁協(請戸漁港)
浪江町大字請戸字中島地先
TEL 0240-34-4121
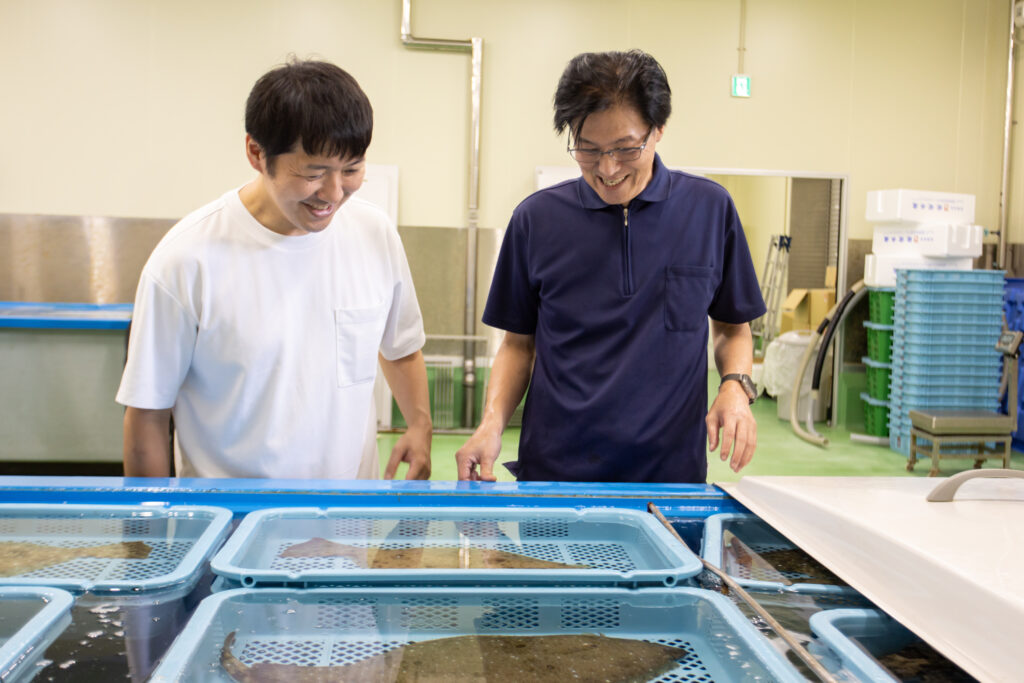
「とてもレベルが高い」。視察前に東京で請戸の魚を受け取った中村シェフは、漁師や仲買の食材への愛をそこに感じたという。
明治30年創業の柴栄水産は、請戸漁港の競りで魚を扱う仲買業者として“請戸もの”の品質を支え続けてきた。震災で約9年にわたり休業を余儀なくされたが、2020年に事業を再開。以来、安定した仕入れと丁寧な手入れで、料理人からも厚い信頼を集め、“請戸もの”の価値をさらに高めている。
実際に手にしたホッキ貝やヒラメは、これまで東京で愛用してきた魚と比べても遜色のないレベルで驚いたという。「透明感があって、包丁を入れてみたいと思わせる品質。梱包や配送にも真心が表れていて、ブレのない安定した良いものを届けてくれる、そんな信頼感がありました」と中村シェフは笑顔で話す。

同社は、加工業者としても確かな技術を持つ。視察ではしらす加工の工程を見学した。水揚げ後に選別・洗浄し、加熱や乾燥、冷却を経て箱詰めされる。その工程はシンプルに見えるが、実際には天候や原料の状態に応じて職人が判断を下していく繊細な作業だ。
白さや形の美しさ、混入物のなさといった基準を満たすために、複数回の目視検査が欠かせない。2025年の今季もしらすは水揚げが不安定ながら、職人の目利きと技術で高い品質を保っている。

一方で、中村シェフが注目したのが柴栄水産のキャラクター。「柴犬がモチーフの“しばえもん”をキャラクターにしたブランディングもいい。一見ユーモラスに映りますが、パッと見て伝わるアイコンのような存在は、今の時代にとても大切。技術だけでなく、戦略も素晴らしい」と高く評価した。
仲買と加工、そして発信力。三つの力を兼ね備える柴栄水産は、“請戸もの”を市場へ、そして未来へと橋渡しする存在である。
有限会社柴栄水産
浪江町請戸古川15−7
TEL 0240-23-5411


江戸時代に廻船問屋から始まり、地元漁師に愛されてきた鈴木酒造店の酒は、浪江の風土と人々の誇りを映す存在だ。浪江町の海沿いにあった“日本一海に近い酒蔵”は、2011年の津波で全壊した。
一度は「もう酒造りはできない」と絶望するも、残されていた蔵付き酵母を頼りに南会津での醸造を経て、山形・長井市に移転。そこで酒造りを継続しながらも「浪江に戻る」という願いを捨てず、町に新たな蔵を再建した。
浪江の蔵では、地元のコシヒカリと地下水を用いた仕込みを行う。酒米ではなく食用米をあえて選ぶのは、より厳しい基準を満たすことで“浪江の米の安全性”を証明するためだ。ラベルには「浪江町産」を明示し、地元資源の価値を訴求している。
少量生産を前提にした酒造りでは、AI解析を取り入れ、“請戸もの”の魚に合わせたニッチな酒の開発にも挑んでいる。


視察では、浪江町の花・コスモスから酵母を抽出して仕込んだ磐城壽純米吟醸「壽こすもす」の、火入れ前の生酒を特別に試飲させてもらった。3年にわたる研究の末に実現した一本で、微発泡のフレッシュな口当たりが特徴だ。
もともと生酒が大好きで、毎年冬を楽しみにしているという中村シェフは「格別」と頬をゆるめる。「軽やかな酸味と透明感があり、とてもきれいな酒。上品な旨みに、花酵母ならではの個性が加わっている。コシヒカリでここまで洗練された酒が造れるとは思わなかった」と感嘆。「料理に寄り添い、和も洋も包み込む懐の深さがある」と続け、視察でしか味わえなかった特別な一杯として強く印象を残した。
少量生産ゆえ、市場に広く出回ることは少なく、蔵直販や限定流通が中心となるが、鈴木酒造店は浪江の食文化全体を広く発信する取り組みにも積極的に関わっている。復興の象徴的な酒蔵は、地域の未来を支える存在となっている。
鈴木酒造店 浪江蔵
浪江町幾世橋知命寺40 なみえの技・なりわい館内
0240-35-2337


300年以上、“焼き物の里”としての歴史を紡いできた浪江町。伝統工芸「大堀相馬焼」は、淡い青磁色にひび割れ模様が浮かぶ「青ひび」や、二重焼きによる「走り駒」の文様など独自の技法で知られる。
震災と原発事故で多くの窯元が被災。存続自体が危ぶまれたが、今も職人たちが炎を絶やさずにいる。
訪れたのは、宝暦10年(1760年)創業の窯元「陶吉郎窯」。相馬焼の功労者・近藤陶吉郎の名を受け継ぐ歴史ある窯だ。
震災後は一時、いわき市で制作を続けてきたが、2024年に浪江・大堀工房を再オープン。当主の近藤学さんは、「別の土地で窯を開いても、それは大堀相馬焼ではない。大堀の地でなければ意味がない」とし、土地とともに歩む姿勢を貫く。

中村シェフらは工房で陶芸体験にも挑戦。手捻りで土を成形するひとときからも、伝統を受け継ぐ重みと手仕事の奥深さを実感した。
器について中村シェフは「新しい発想を与えてくれる存在」とし、自身の店ではこれまで縁のある作家の器を使うことが多かったが、「大堀相馬焼は手仕事を感じさせる豊かな質感とモダンな表情もある。また、こちらの意図に応えてくれそうな柔軟な空気感があり、今後もお付き合いしたいと思える出会いでした」と、今回の訪問を喜んだ。

「料理に食感があるように、器やカトラリーにも“口に触れる触感”がある。コーヒーやワインも器で味が変わる。相馬焼のカップなら、飲み物の表情も新しく引き出せそう」と、早速コーヒーカップの導入を検討する意欲を見せた。
震災を越えて浪江に再び炎を灯した陶吉郎窯の相馬焼は、復興の証であると同時に、新たな料理のインスピレーションを誘う器としても大きな役割を担っている。
大堀相馬焼 陶吉郎窯 大堀工房
浪江町大堀字後畑98-1
TEL 090-2604-9890
※通常、陶芸体験は「いわき工房」(TEL: 0246-38-7855)のみとなります。

甲冑姿の騎馬武者が約400騎駆け抜ける、国指定重要無形民俗文化財「相馬野馬追」。浪江を含む相馬地方の象徴的な祭は、今もなお地域の誇りだ。
浪江町生まれの吉田さやかさんの生家も代々、野馬追に参加してきたが、馬とともにある暮らしは震災で突然途絶える。その時の無念が次世代へつなぎたいという決意となり、浪江に帰還後、吉田さんは農家に転身する。選んだ作物は、馬の堆肥を生かしたニンニクづくりだった。
「ニンニクを育てるなら馬の堆肥が一番よ」と教えてくれたのは祖母だった。おがくずを含む馬の堆肥は、水はけがよく、それでいて保水力もあり、土をふかふかにする。吉田さんはこれを活かして栽培を開始し、今では年間3万8千株を育てるまでになった。

“野馬追の馬の堆肥で育ったニンニク”という唯一無二の背景から、「サムライガーリック」と命名。浪江を代表するブランドへと育っている。
中村シェフも「大粒ながら香りと旨みが凝縮している。まさに新しいニンニクの時代を感じさせる存在」と高く評価。「これまでの常識を変える可能性がある食材であり、サムライガーリックに合わせた新しい調理法を追求したい」と意気込みを見せる。
評判は口コミで広がり、町内だけでなく仙台や首都圏のレストランにも出荷。吉田さんは「ニンニクが評価されるのはもちろんですが、その先に野馬追や浪江の文化に興味を持ってもらえるのが嬉しい」と微笑む。

馬の飼育は震災で大きく減少し、現在、町内で常時飼育されているのは1〜2か所、わずか8頭ほど。全体でも50弱の世帯にまで減少している。それでも「馬とともに暮らす文化を絶やさない」という強い思いで、吉田さんは活動を続ける。
今回は、吉田さんが主宰する「ランドビルドファーム」は、サムライガーリックをはじめとした取り組みの拠点を訪問。馬と人、そして土地をつなぐ活動の現場を垣間見ることができた。
現在は150年続く母屋を拠点に、一般の方が農業体験や文化体験をできるイベントなども実施。「なくしたものを悔やむより、今あるものを大切にしたい」。サムライガーリックは、野馬追の精神を食のかたちで未来へとつなぐ。
サムライガーリック(株式会社ランドビルドファーム)
浪江町室原
https://www.instagram.com/landbuild_farm/

今回の視察では、現地で中村シェフによる特別な食事会が開かれた。会場には生産者や行政関係者、海外インフルエンサーが集まり、まさに「浪江の食と文化の縮図」となる場となった。
会の冒頭、中村シェフは「浪江の食材は世界に引けを取らない」と力強く語り、生産者たちを大いに励ました。この日提供された料理には、道の駅やスーパーで買い足した旬の野菜や果物も登場。全11皿からなる料理は、より“リアルな浪江”を表現するコースとなった。






最初の一皿は、ズッキーニ、きゅうり、梨をシンプルに仕立てたサラダ。「新鮮さをそのまま味わってほしかった」とシェフ。続く「平目のカルパッチョ」はあえて寝かせず、とれたての食感を青柚子トマトソースで生かした。
会場で大きな歓声が上がったのが「ホッキ貝と桃、バジルの冷たいパスタ」。意外な組み合わせながら甘みの相乗効果で大好評となり、皿はあっという間に空になった。
魚料理のメインは「スズキのポワレ、ブールブランソース」。刺身でも十分においしい素材をあえて火入れし、フレンチの原点を示すひと皿に仕上げた。さらに、肉料理のメイン「鹿肉のソテー、黒ニンニクとチレアルボワのソース」では、サムライガーリックの黒ニンニクの可能性を示す挑戦的な一品となり、意外にも日本酒に合うと会場を沸かせた。





最後に即興で仕立てた「つるむらさきとナス、ホッキ貝 サルサベルダソース」では、メキシコの調味法を取り入れ、「地産地消を超えた新しい出会い」を表現。参加者は浪江食材の奥深さと可能性を改めて実感した。
「常識にとらわれず、この土地ならではの新しい調理法を追求したい」と締めくくったシェフの言葉通り、この夜の体験は浪江の食材が“世界水準”であることを強く印象づけるものとなった。




視察では「東日本大震災・原子力災害伝承館」と「請戸小学校」も訪れた。いずれも、浪江町を語るうえで欠かせない震災の記憶を伝える場所だ。
伝承館では、津波と原発事故がもたらした被害の全貌、復興に向けた歩み、そして町が直面した課題を学んだ。写真や映像、証言資料の数々が、当時の空気を生々しく伝える。
加えて、日替わりで行われる「語り部講話」に耳を傾けた。被災当事者の体験談は、日常の延長にある暮らしが一瞬で失われた現実を伝え、エネルギーのあり方や普段の生活を見つめ直すきっかけを与えてくれた。

請戸小学校は、津波で全壊した校舎を保存・公開している。打ち砕かれた教室の跡や津波の爪痕は、子どもたちを守ろうと必死に避難誘導した先生方の行動とともに、今も強烈なメッセージを放つ。
中村シェフは「食材をただおいしいと紹介するだけではなく、その背景にある歴史や苦難も知ることが重要だと感じた」と語る。食の魅力とともに、震災を生き抜いた町の物語を世界に伝えることの大切さを改めて実感する時間となった。
震災と原発事故を経て、長く風評被害に苦しんできた浪江町。だからこそ「安全でおいしい」という確かな価値を、国内外に発信する取り組みが重ねられている。インバウンド需要も視野に入れた活動は、いま本格化の段階に入った。
今回の取材では、その歩みを現地で確かめ、生産者や料理人、海外の発信者たちと交流する中で「浪江の食」の可能性を再発見することができた。生産現場に息づく努力と誇り、そして食卓での喜びを直に感じることができ、大きな収穫となった。
10月1日から31日まで東京のレストラン3店舗で「浪江フェア」が開催される。“請戸もの”や地元農産物を、一流シェフが独自の感性で昇華させた特別メニューとして届ける。浪江町の“今”を食を通して体感し、未来へと受け継ぐための一歩となるだろう。
Text & photo: Yuki Kimishima

