
持てる才能を縦横に発揮し、最も斬新で完成度の高いインパクトのある料理を提供している料理人へ贈られる「今年のシェフ賞」。2023年度は「日本料理 かんだ」の神田裕行さんに贈られた(店の評価は最高点の5トック、20点満点中19点)。
日本料理界の重鎮として知られ、世界的にも十分な評価を得てきた神田さんが、『ゴ・エ・ミヨ』日本版第7号で初の受賞となったのは、少し意外な気もする。本インタビューでは、受賞の率直な感想から、東京で勝負し続ける意味、今後の展望についても聞いた。
神田さんは、2022年2月、自身の店を元麻布から虎ノ門へ移転。現代美術作家の杉本博司さんが手掛けた和の空間で「感性と味覚のぎりぎりのところで成立する繊細な日本料理」を追究し、日本料理を海外にも発信。NPO法人「FUUDO」では料理人として食の未来を考えるなど、日本の料理界を牽引する存在であることが評価された。
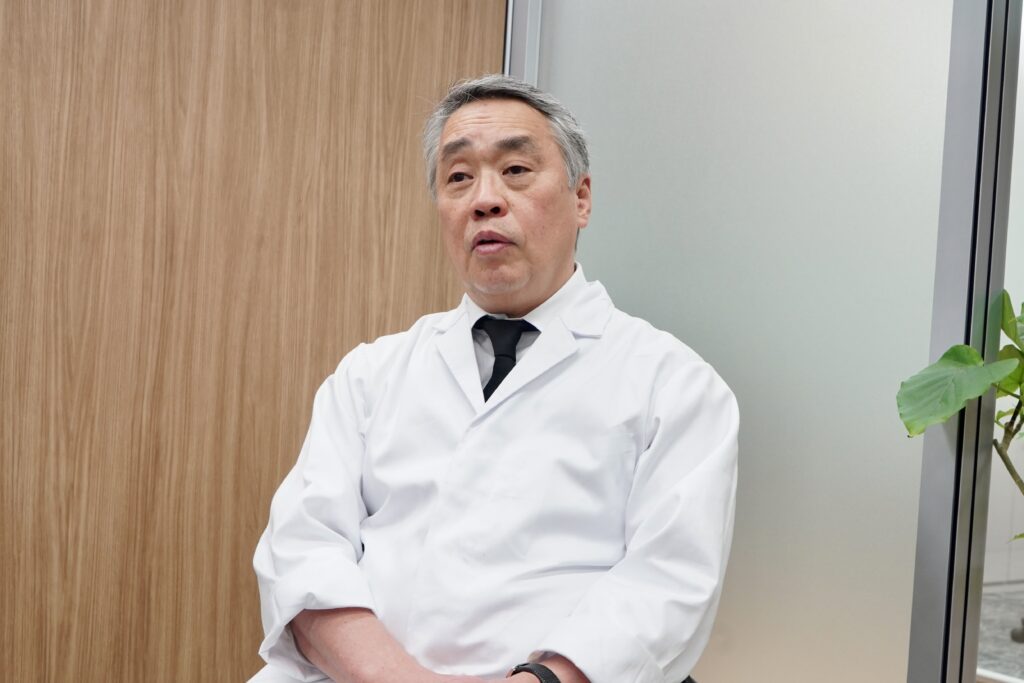
――国内外で数々のアワードを受賞している神田さんですが、『ゴ・エ・ミヨ』の「今年のシェフ賞」は、今回が初です。なぜ今だったのかという考察も含め、率直な感想をお聞かせください。
いま思えば、コロナ禍以前は自分の軸が少しブレていたように思います。ミシュランではずっと三つ星をいただき(注:『ミシュランガイド東京』が初めて刊行された2008年度版から、昨年末の2023年度版まで16年連続三つ星の評価を得ている)、海外からのゲストを喜ばせたいという思いもあって、日本料理のグローバル化を目指してきました。それが少し行き過ぎていた部分もあったのではないかと。
ところがこの2年半のコロナ禍で、お客様は日本の方ばかりになり、自分の料理を顧みる機会をいただいた。お陰さまでいまは、王道の日本料理が8割、時代に沿った遊び心が2割くらいの、ちょうどいいバランスになっていると思います。それをお客様が再評価してくださり、『ゴ・エ・ミヨ』の評価にもつながったのかなと。
――神田さんは、パリの板前割烹「TOMO」の料理長時代、1988年に初めて『ゴ・エ・ミヨ』で評価を得ています。その当時から現在にかけて『ゴ・エ・ミヨ』には、どんな印象をお持ちですか。
『ゴ・エ・ミヨ』での初めての評価は1トック、14点(当時)。それがアジア料理の最高峰と言われ、自分のいる世界の小ささを実感しました。日本料理の素晴らしさを世界に知らしめるために、まず日本で頂点を目指さなければと奮起するきっかけにもなりました。
『ゴ・エ・ミヨ』のイメージは、いわば“ミシュランガイドのカウンターカルチャー”ですね。『ミシュランガイド』の星は、シェフ個人の腕や料理というより、ワインリストや空間、インテリア、ホスピタリティなども含めた総合的な評価。三つ星はいわゆるグランメゾン、日本料理で言えば料亭に贈られるものでした。
一方『ゴ・エ・ミヨ』は、星ではなくトック=コック帽が示しているように(0~5トックで評価)シェフとその料理にフォーカスしている印象。「今年のシェフ賞」をいただいて、非常に光栄に思っています。
――東京で日本料理を追求する意味、価値をどのように考えていますか。
近代の日本料理は、新鮮な素材とともに発展してきた料理です。そして東京には毎日、日本中からさまざまな食材が降り注ぐように届く。こんな場所、ほかにないです。流通の質と量、スピード感、正確さは天下随一。京都ですら東京には及ばないんですよ。
世界最高峰の食材が集まる東京こそ、日本料理のいちばんの戦場です。東京でしかできない料理があり、だからこそ、世界中の人が憧れをもって食べに来る。いまどき世界の主な都市ならどこでも日本料理は食べられますが、本当の日本料理は日本でしか食べられないし、日本の人にしか作れないものだと思っています。素材や技術以上に、日本人としての感性が重要になってくるからです。

『吉兆』の創業者である湯木貞一さんが、「世界之名物 日本料理」という素晴らしい言葉を残しています。名物というのは、決して向こうからはやってこない。日本の情緒のなかでいただく日本料理こそ“世界之名物”たり得るのです。まさに正鵠を得た言葉だと思います。
――日本の情緒という意味では空間も重要ですね。
もちろんです。京都のグランメゾンは、やはり料亭だろうと思います。京都の歴史、風土に沿った建築、内装、室礼も含めて、料亭文化がいまも息づいている。でも東京でやるなら、靴を脱ぐ必要はないと思うし、お客様と料理人が間近で、ライブ感やコミュニケーションを楽しめる空間がしっくり来る。
みんなが鮨や天ぷらが好きなのも、料理人が目の前で作ってくれるからですよね。お座敷で食べてもピンとこない。その感覚が、日本料理にも求められています。ならば東京のグランメゾンは、やはりカウンターであるべきでしょう。

――虎ノ門の「かんだ」も、カウンター主体のお店になりましたね。移転を決意したきっかけは?
50代に入ったころ、「いつまで現役で料理ができるだろか」と考えるようになりました。僕の言う現役というのは、毎日調理場に立ち、時代の風を感じながら、お客様の前で料理し葛藤し続けるということ。それができるのは70歳までだろうと。もう一度アクセルを踏んで料理に没頭するために、新たなステージに移るのもいいなと思ったのが50代の半ばごろです。
元麻布の店は、徳島の建築家の友人と一緒に考え尽くしたもので非常に気に入っていましたが、ウェイティングスペースや個室専用の化粧室など、一流のお客様を迎えるためのファシリティを整えたいと考えていました。庭も欲しいし、日本の文化の粋のような建築、空間、インテリアも大事にしたい……そう考えていたときに、現代美術作家の杉本博司さんに出会い、意気投合して、新しい店作りをお願いしました。
極端なことを言えば、日本料理のお吸いものって、 日常のお茶の間や、逆に広すぎるホールで飲んでも、美味しさはわからないと思うんですよ。過度な調味料を使わず、研ぎ澄まされた素材本来の味、繊細な美味しさを感じていただくには、清潔で、謙虚で、心地いい緊張感のある空間が必要です。それを千利休は茶室に求めたわけですが、日本料理店のコンセプトも基本的には同じ。限られた空間のなかでお客様の感性を引き出し、その感性にフォーカスするような料理を出していきたいですね。

――最後に、今後の展望を教えていただけますか。
僕は今年60歳を迎えます。70歳まではあと10年、3650日。いま、営業日数を年240日くらいに絞っているので、2400日しかありません。そう考えると、一日たりとも無駄にはできない。心地よい緊張感のなかで、日々、真摯に精進を重ねていきたいですね。後進の育成? いや、まだまだ(笑)。自分自身が成長過程にあると思っていますし、そう思っていたいです。

神田裕行 Hiroyuki Kanda
1963年徳島県生まれ。大阪で日本料理の世界に入り、86年渡仏。パリの日本料理店で5年間料理長を務め、帰国後は、徳島の料亭「青柳」へ。東京・赤坂「basara」の料理長などを経て独立。2004年、東京・元麻布に「かんだ」をオープン。『ミシュランガイド東京』が初めて刊行された2008年度版から、昨年末の2023年度版まで16年連続三つ星。21年「メンターシェフアワード」受賞。22年2月、自らの店を虎ノ門に移転。
text:伊藤由起, coordinate:江藤詩文 Shifumy

