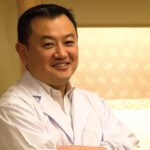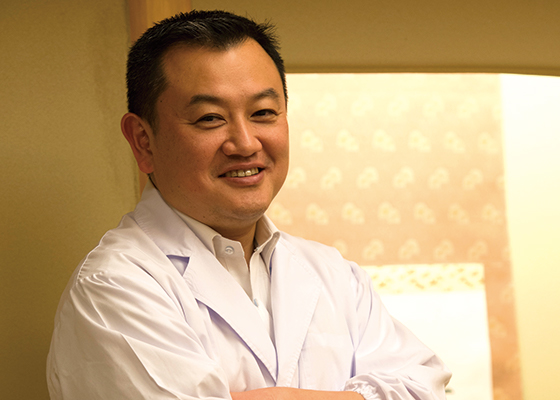
日本料理店「銀座小十」の奥田透さんは、世界にいち早く本物の日本料理を見せた、気鋭の料理人だ。フランス・パリに日本料理店「OKUDA」を出店したのは、折しも「和食」の無形文化遺産登録が決まった2013年。きっかけは、自身が愛する日本料理の未来を危惧したからだという。
「7〜8年前のことになりますが、従業員を調理師学校から採用する時に、和食を専攻している子が全体の一割くらいだったんです。それで、和食は人気がないんだなと。日本料理の料理人はなり手がいない、私の中でそれが明確になったんです。でも、毎日、和食をやってきた人間からすると、なんで嫌われなくちゃならないのかと疑問で。それではこの国は、あまりに悲しいじゃないですか」
何か自分にできることはないか、そう考えた末に辿り着いたのが、海外出店だったという。
日本料理は若い人に人気がなく、料理人のなり手がいない。それは、日本料理の素晴らしさ、魅力が正しく伝わっていないからではないか。そう考えた奥田さんは、日本料理の未来のために、3つのことを行っている。1つ目は海外での本格日本料理店の出店、2つ目は調理師学校の改革、3つ目は日常の和食を根づかせること。この3つを行うことで、日本人の中で日本料理の価値が高まり、未来へつながるのだという。
「私がまず、日本料理の未来のためにやるべきだと考えたのは、海外での本格的な日本料理店の出店です。日本は島国なので、海外に憧れがある。そして、世界で一番は日本のものではないと思っています。だから、海外のもので一番になれば、世界でも凄い人になったように思ってしまう。フランスまで出かけて、有名なワインの葡萄畑に行って、作り方もブドウの品種も覚えて。でも、酒米の田んぼを見に行ったことがあるかといえば、誰も見たことがない。日本酒の作り方だって、答えられない。なんで、日本のものを覚えて、世界に見せようとする人がいないんだ、と強く思ったんです」
海外へ行けば、日本人が認めることができないような不思議な寿司がある。結局、ビジネス面で考えれば、現地の人々に合わせるのが近道だからだ。今までは、海外に行った日本人が、金儲けのために仕方なくやる寿司、という側面が強かったのだと奥田さんは語る。
「カリフォルニアロールとか、サーモンにマヨネーズとか、そういうのをやらないといけない状況にあったんです。まず、本格的にやろうと思っても魚がない。お客さまも、だしの薄い味がわからない。ならば、現地の魚で使えるものを使い、醤油をたくさん入れればいい。でも、そんなことをしていたら、日本料理の形は変わってしまいますよね。それを打破したかったんです」
しかし、日本近隣のアジア諸国であれば、築地から毎日、食材を仕入れることができ、日本にいるのとほぼ同じ料理ができるだろう。箸の文化もあり、醤油だって問題なく手に入る。器なども、持って行くのは比較的容易だ。なのになぜヨーロッパ、しかもフランスのパリに最初の出店をしたのだろうか。
「結局、日本人は欧米への憧れが強い。英語やフランス語が話せることに格好よさは感じるのに、日本語のありがとうがよい言葉だというのはあまり感じない。そんな日本人ですから、欧米で成功しないと価値をわかってもらえないんじゃないかなと。私は、日本人が一番憧れているのは、やはりパリなんじゃないかと思っています。だからパリにしました。商売するだけなら、同じヨーロッパでも金融の街でありお金も多く動くロンドンの方がやりやすかった。でも、世界のフランス料理と同じ土俵で戦って認められないと、たとえその地で認められても、日本人には凄さが伝わらないと思ったんです」
しかし、ヨーロッパは遠く、日本料理の食材も手に入りにくい。さらに、各国に根づいた文化も強い。日本人に凄さを伝えたかったとは言うが、奥田さんはなぜ、わざわざ困難な道を選んだのだろうか。
「ミシュランで星をとってから、ビジネスではいい話が山ほどきました。でも、10代20代と、寝る間も惜しんで頑張ってきたことを、結局は金儲けのために使ってしまったら、この先の人生が嫌になるんじゃないかと思いました。だから、あえて一番大変なことをしようとしたんです。パリへの出店当時、日本は東日本大震災からまだ数年しか経っておらず、みんな下を向いて歩いていた。この国には他の国にない素晴らしい文化や培ってきたよいものがあるはずなのに、下を向いて歩かなきゃいけないのは疑問でした。だから自分が最も大変なことに挑戦すれば、ほかの業種の人にも、もしかしたら何か、頑張る力が伝わって、明るい方向へ行くんじゃないかと思ったんです」

奥田さんが取り組んでいることの2つ目は、日本の調理師学校の改革だ。2016年、「東京すし和食調理専門学校」を開き、奥田さんは顧問を務めている。
「日本の調理師学校は、もっと和食、寿司、天ぷら、蕎麦、和菓子といった日本料理を教えるべきなんです。それをしなければ、フランス料理やイタリア料理に、若い子たちをみんな取られてしまう。将来、誰も日本料理を勉強しなくなってしまうのではと危惧しています。10人の中から凄い人を見つけるのと、90人の中から凄い人を見つけるのとでは、大きく違いますよね。多くの調理師学校は和食のクラスも先生も少なく、ここはどこの国なんだ、と思います。フランスなどから、私の店にも日本料理を習いたいとたくさんの人が来日しているけれど、それは、自分の国の料理をよくするために日本料理の要素を取り入れたいだけであって、日本料理の店をやりたいわけではないんです」
日本人がフランス料理を志して本場フランスへ行き、給料もそこそこに働いて料理を覚え、フランス語を覚え、星付きレストランの二番手を務めたといって帰国する。それは素晴らしいことではあるが、手先が器用で勤勉な日本人がいいように使われているのではないか。そんな状況を、奥田さんは憂いているのだ。「日本料理専門の調理師学校を始めて、3年目になります。開校した頃から、話題になりました。日本で日本料理の学校をやって、話題になるのはおかしくないでしょうか。でも、これを見たほかの調理師学校の人たちが、うちも日本料理に力を入れなきゃならないと、みんな思い始めていると感じています。私はその意識を持ってもらえただけでも、やった意義はあったかなと思います」
奥田さんの取り組みの3つ目は、日常の和食を根づかせること。これは、調理師学校での、日本料理の必要性にもつながる話だ。
「子供たちが和食に触れる機会が少なくなっています。麻婆豆腐や餃子が食卓に上るのも悪くはないけれども、家庭では日常的に和食を作っていないし、食べてもいない。夫婦共働きが当たり前になって食事を作る時間がないこともあるのでしょう。和食を作ったことも教わったこともない、なのに、パスタや鶏のソテーはすごく上手に作れるんです。そんな状況ですから、教育の一環である小中学校の給食にだけでも和食が残れば、未来に日本料理は残せるのではと思っています」

奥田さんがフランスの次に海外出店の地としたのは、アメリカの中心、ニューヨークだ。
「やはりアメリカへの憧れというのは、多くの日本人にあるものだと思うんです。そこで本格的な日本料理を見せ、日本人は凄いと思ってもらえれば、何かのきっかけになるかなと。欧米への憧れは、劣等感の裏返しです。でも、料理の世界では何も負けていない。世界一の大都市ニューヨークで日本料理の凄さをきちんと示すべきではないかと思います」
奥田さんは、まったく文化の異なる土地へ、日本料理をそのまま持って行くことにこだわった。EUには、日本のものが入ってきにくい現状がある。そんななかでも奥田さんは、建築から器、人材にいたるまで、そのままを持って行った。その苦労は、想像に難くない。しかし、それまで誰もが不可能だと思っていたことを、情熱と粘り強さで乗り越えてきたのだ。それは、日本のものを無理にでも持ち込むことで生まれるメリットがあるからなのだという。
「ひとつは、日本の物がたくさん輸出できるようになること。今、一番やるべきなのはこれです。日本のいいものを海外に紹介できて、単純に国益が上がる。だから現地の人に日本料理を認めさせて、日本のあれが必要だ、これが必要だと思ってもらえるようにするのが大切なんです。もうひとつは全く逆で、その国のものを使っておいしい日本料理を作って、インターナショナルな料理になること。フランス料理や中国料理は世界的な料理ですけれど、どれも現地の食材を使っておいしく作れます。でも、日本料理はいまだに、日本産の食材じゃないと作れません、と言っている。そんな概念は払拭しないと、いつまでも日本料理は世界に広がらないんです」
難局を乗り越え、今でこそ海外に多店舗を構えている奥田さんだが、海外で現地の協力者にはしごを外されたことは数知れずだという。
「だから、そんなことやらなければいいのにと言われます。でも、活け締めすら知らない国が多いなかで、日本人が伝えるべきことはまだまだある。誰かがやらなければ、何も始まらないんです。前例がなければ難しいことはあると思います。成功するのは、2番目か3番目かもしれない。でも大切なのは1番最初にやることだと思います。どれだけ大変でも、どれだけ失敗しても、挑戦したことは事実なので、私のしたことを見て、『自分もニューヨークで本格的な日本料理をやりたい』とか、『奥田よりもいい店を作りたい』とか、そう思ってくれる人が増えることを望んでいます」
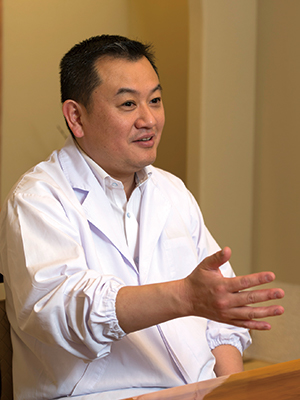
Toru Okuda
1969年静岡県生まれ。高校卒業後、静岡の割烹旅館で修業を始める。その後も各地で研鑽を積み、29歳で静岡に「春夏秋冬花見小路」を開店。2003年から東京へ移り、「銀座 小十」をオープン。2013年フランスに「OKUDA」、2017年アメリカに「OKUDA New York」をオープンさせた。
澤由香=取材、文 小寺恵=撮影
本記事は雑誌料理王国2018年6月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は2018年6月号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。