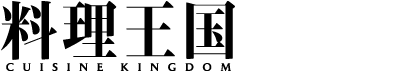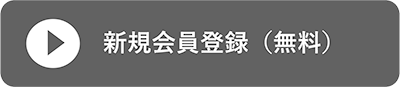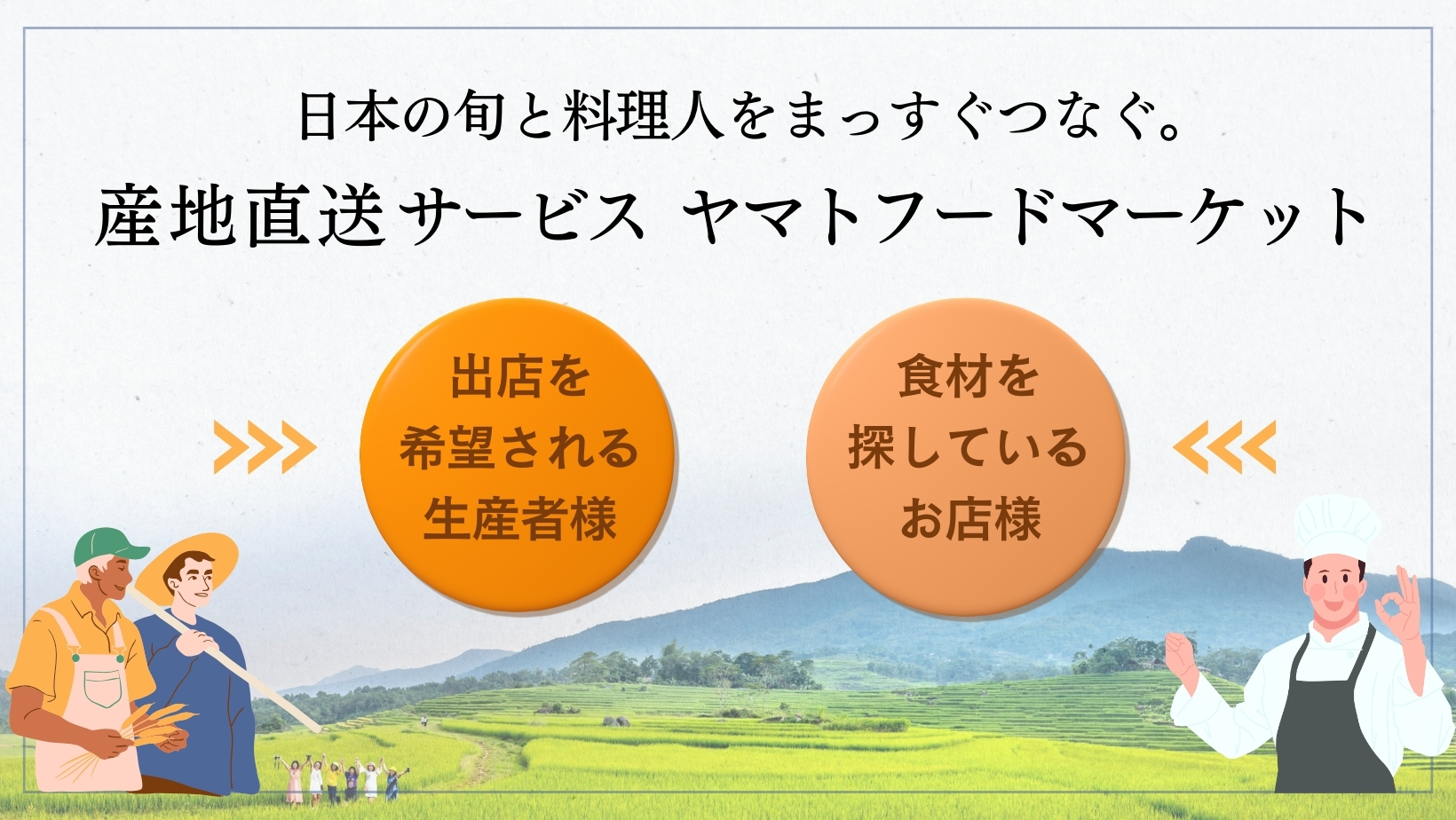全部わかりますか?日本のだいこん47種類

ダイコンの日本への伝来は弥生時代とされ、ヤマイモやサトイモ、ウリなどとともに、日本最古の伝来野菜のひとつとされる。エジプトや地中海東岸一帯が原産地とされ、そこからヨーロッパとアジアに伝わった。アジア側のルートは、中東を経て北と南。北の道は中国北部や韓国を経て日本へ。寒地を経たので〝かたいダイコン〟に。南の道はインドや東南アジアを経て九州や沖縄へ。こちらは暑さに強い〝やわらかいダイコン〟となり日本に来た。
続きをご覧になるには、無料会員登録が必要です。
会員登録がお済みの方は、こちらよりログインしてください。
SNSでフォローする