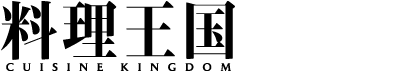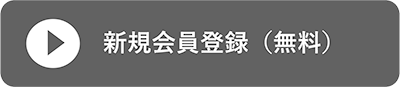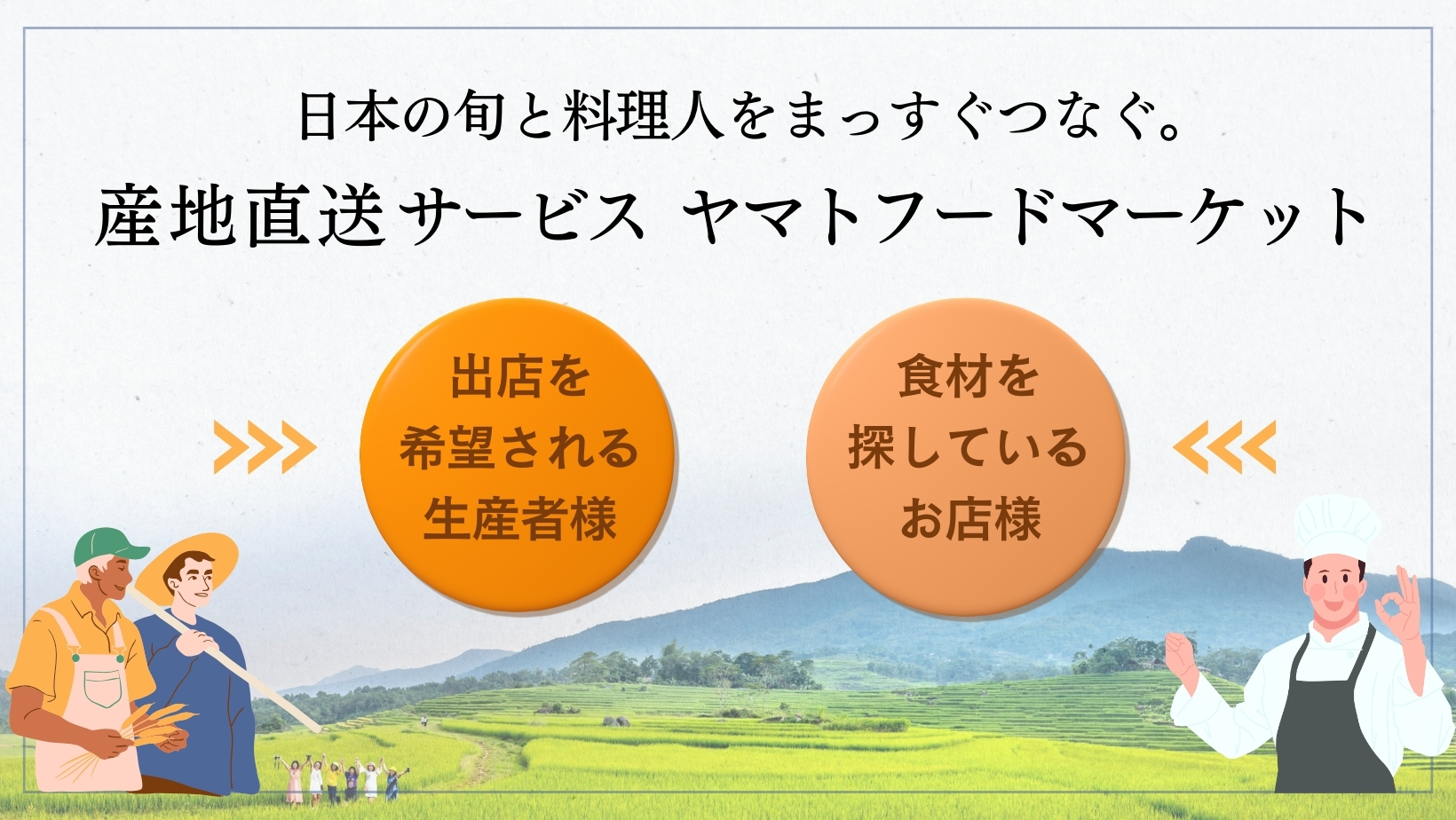2024年6月19日
進化するパリの日本人料理人たち

フランス、とりわけパリでフランス料理を手がける日本人料理人たちは今や一大勢力となった。 彼らは〝日本人シェフ〟という枠を超え、さまざまな形でフランス料理の発展を担っている。
日本人料理人たちのフランス料理界での活躍が止まらない。《日本人料理人によるフランス料理》は、特にパリでは一種の流行となり、多くのメディアで特集が組まれるようになった。
そんなシーンでよく登場していた、彼らの料理を形容する言葉は、〝日本人らしいシンプルな、引き算の美学〞〝洗練と精度と美しさ〞〝禅の精神を感じさせる〞〝高級和食店同様、お任せメニューのみ〞。もちろん肯定的な意見だ。とはいえ、同時に、十把一絡げ的で、〝日本人=こういうイメージ〞とは、短絡過ぎないだろうか? 実際、一人ひとりの活動をしっかり見てみると、今や、このステレオタイプな評価から抜け出して、より個性を打ち立てて活動をしている日本人シェフの姿が続々と増えているのに気づくだろう。
続きをご覧になるには、無料会員登録が必要です。
会員登録がお済みの方は、こちらよりログインしてください。
加納雪乃=取材、文
Yukino Kano
会社の駐在で過ごしたパリでレストラン文化の魅力に触れ、レストランの楽しさを伝えたい、と、ライターに転身。2000年から、パリはもとよりフランス全国を旅し、フランス美食文化の担い手たちを日本の雑誌に紹介している。
本記事は雑誌料理王国第277号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は第277号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。
SNSでフォローする