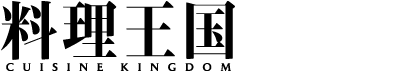なぜイタリアンは日本に受け入れられたのか?

日本のイタリアンクロニクル
日本におけるイタリアンの歴史は、長いとはいえない。しかし、その浸透度はイタリアの人々にも、驚かれるほどだ。一般家庭でもイタリア料理が作られ、ほとんどの町にはイタリア料理が食べられる店がある。そうなった理由は何だったのか紐解きつつ、未来像を探っていく。
今日、日本におけるイタリア料理店の数が1万軒を超えているということを来日したイタリア人に話すと、皆、同様に「本当か?」と聞き返してくる。しかも、これらの店のほとんどが、日本人によって営まれていると知ると、これまた何とも言えない、異様な顔をする。
アメリカ、カナダ、オーストラリアなど、イタリア人移民の多い国では、多くのイタリア人がイタリアンレストランを経営しているが、これは、ごく普通の流れだろう。しかし、日本はまったく違う。イタリア人の移民はほとんどいないし、当然、その二世、三世もいない。では何故、日本においてこれほどイタリア料理
が人気を得たのだろうか。今回は、日本におけるイタリア料理の歴史を紐解くとともに、本国イタリアのイタリアンレストランとの違いを探りながら、今後の日本におけるイタリアンレストランの展望を語ってみることにしようと思う
日本におけるイタリア料理の歴史
日本にイタリアンレストランが本格的に開店し広まっていくには、1970年代の終わりまで待たなければならない。第二次世界大戦以前にも和製マカロニやケチャップなどが販売されていたが、とくにケチャップは、もともとイタリアには存在しなかったもので、イタリアからアメリカに移民した人たちの末裔が使い始めたのではないかといわれている。
戦後は、日本においてもイタリア料理に使える素材が開発されるようになるが、本国イタリア製とは似て非なるものであった。1960年、麻布に「キャンティ」がオープンし、六本木族や芸能人などオピニオンリーダーの人気を得る。
すでに、「アントニオ」、「ニコラス」などの店も開店していたが、一部の人々の通う店であった。1970年代、イタリアの洋書を中心に輸入販売をしていた「文流」の西村暢夫氏が「リストランテ文流」を開店し、1978年にはイタリア・ローマでの修業を終えた吉川敏明シェフが西麻布に「カピトリーノ」を開店。
この頃から1980年代にかけては、日本におけるイタリア料理ブームの時期となり、フレンチレストランからイタリアンレストランに鞍替えする店も増えた。なかには、フランス料理をベースにパスタ料理を加え、国旗をイタリアのものに差し替えて営業する店すらも現れたほどだ。しかし、サービスにほとんど力を入れず、人件費を下げるためにアルバイトを多用したため、サービスの内容はひどいものだった。また、コストを下げるためほとんどの店が、比較的家賃の安いビルの地下もしくは2階にあったと記憶している。
そんな状況では、やがて淘汰される店も現れ始めた。実はこれらの店には、ある種の共通点があった。店内の装飾はシンプルで、北イタリア風のデザイン。ブーム初期には、「リストランテ・マニン」、「エル・トゥーラ」などに代表されるアパレル関係の会社が経営する店舗が多かったこともあって、デザイン性が高かった。
一般的に料理はというと、パスタはスパゲッティを中心に、トマトとオリーブオイルを使った料理が多く見られた。日本人はうどんやそばのように長い麺状のものが好きで、それを出していれば安心だったのだ。さらに少しトマトの酸味を加え、コクを出したソースがあれば、充分に満足してもらえた。こうして、多くの
場合、内装は北で料理は南という、本国ではミスマッチなものが日本的イタリア料理店として認知されていき、顧客サイドもそれほど違和感を持たなくなっていたと思う。しかし、本格的なイタリアンが台頭していくにつれ、そういった店は姿を消した。
1970年代、イタリアレストランは本格的に広がっていく

1987 年、自身の店オープンのため来日した。
1983年、片岡護シェフが麻布に「アルポルト」を開店し、その後、「サバティーニ」、「リストランテ山﨑」、「リストランテ ヒロ」、「クチーナ ヒラ」などが周辺に開店した。また、大阪にも山根大助シェフが「ポンテベッキオ」を開店。さらに、「エル・カンピドイオ」、ホテル西洋の「アトーレ」などが開店し、イタリアンファッションとあいまってブティック・レストランにこぞって人が集まるようになる。この頃、レストラン同様にイタリアのブティック・ワイナリーのワインも日本に上陸を果たし、これらの高級ワインはほとんどの店のワインリストに載ることになった。
1990年代に入り、イタリア各地の星付きレストランを経験して帰国した日髙良実シェフが広尾に「アクアパッツァ」を開店し、同じく若くしてイタリアに渡り、北イタリアで修業をした植竹隆政シェフが代官山に「カノビアーノ」、原田慎次シェフが広尾に「アロマフレスカ」を開店した。この頃になると、1980
年代に開店したシェフ達よりも一世代あとのシェフたちが店を持つことになっていた。また、銀座に三ツ星レストランの「エノテーカ・ピンキオーリ」、青山に「リヴァ・デリ・エトゥルスキ」、麹町には「エリオ・ロカンダ」など、本国から来たイタリア人がかかわる店も続々とでき、その特色を出したメニューも提案されるようになる。
そんななか、1997年「グラナータ」を去って2年間イタリア料理を現地で見て回った落合務シェフが、銀座一丁目に「ラ ベットラ ダ オチアイ」を開店し、20年に渡るそれまでの日本におけるイタリア料理を総括した、きわめてオーソドックスな店づくりを提案し、話題を呼んだ。今でも、予約が取りにくい人気店として存在感を発揮している。
2000年代に入り、イタリアンレストランは地方にも根付いていく。
山形に住む奥田政行シェフが「アル・ケッチァーノ」を開店し、地元の野菜や食材を使ったイタリア料理を提案した。2002 年には、京都の笹島保弘シェフが、観光名所・祇園に「イル・ギオットーネ」をオープン、地元京都の素材を生かしたイタリア料理を提案した。その後、2010年には、目黒にナポリピザのブームを巻き起こす、「ピッツェリア・エ・トラットリア・ダ・イーサ」がオー
プンした。
一方、イタリアからの有名店の日本進出は、残念なことだがことごとく失敗していた。高島屋の「ペック」、大丸の「パラクッキ」をはじめ、「グアルティエロ・マルケージ」、「エル・トゥーラ」、「エノテーカ・ピンキオーリ」、「ビーチェ」、「サドレル」、「アンティカ・オステリア・デル・ポンテ」、「レ・カランドレ」など、イタリアで星付きの店が多く開店したが、その多くが数年で撤退を余儀なくされている。
イタリア独自の食材が輸入されるようになり、イタリア料理店の幅が広がっていく
イタリア輸入食材の増加と日本のイタリア料理
1970年代末の初期イタリア料理ブーム前後、イタリア食材、イタリアワインの輸入販売に特化した商社が相次いで設立された。1970年代末から1980年代にかけて、イタリアから帰国した吉川敏明シェフ、片岡護シェフらが自分の店を開店すると、日本でも本物のイタリア食材を求める声が高まったためだ。
そこで、1977年、イタリアの化学品会社「モンテ・エジソン」から独立した「モンテ物産」が、イタリア人のディ・ナポリ氏、松原賢氏らによって設立され、1981年には日本オリベッティ社OBのルチアーノ・コーヘン氏が「日欧商事」を設立した。
1980年代には、イタリアンファッションブームが最盛期を迎えていた。私は仕事で1982年からミラノに駐在していて、ミラノの中心地にあるショッピング街モンテ・ナポレオーネ通りの賑わいを見た。
とくに、セールの始まる1月や7月には、グッチ、プラダ、フェラガモ、ジョルジオ アルマーニ、ブルガリなどのブランド店に日本人の長蛇の列ができていた。バブルが崩壊する前のことだ。
その頃には、日本にイタリア料理ブームが到来して高級イタリア料理店の数が増え、そこで扱われる高級イタリアワインの量も増えた。輸入酒業各社はイタリアの超一流ワイナリーへ出向き、その輸入代理権を獲得すべく動いていたのであ
る。1960年代に1パーセント程度だった日本での輸入イタリアワインのシェアは、このイタリア料理ブームによって大幅にシェアを伸ばし、20 パーセント近くまで到達。しかし、イタリア料理店以外への開拓が遅れてしまい、世界一の生産量を誇るイタリアワインでありながら、残念ながら今日においても20パーセントには届いていないのが実状だ。
しかし、ほかの食材の輸入は確実に伸び、パスタはもちろん、トマト缶詰までもが日本の各家庭に常備されるようになった。また、1980年代からは、体によいという健康志向からオリーブオイルの輸入が増加し、さらには「ドミノピザ」を始めとする宅配ピザが人気を得て、ピザが家庭でも広く食べられるようにな
る。1980年代にはほかにも、ティラミスやパンナコッタなどのデザートが日本に導入されたのみならず、バルサミコ酢をはじめとするイタリア独自の食材がさまざま輸入されるようになった。そして、1996年、生ハムの輸入が解禁され、2000年にイタリア食肉加工品が全面的に解禁されると、原産地呼称付きの優れた食材が多く日本に輸入されるようになり、日本におけるイタリア料理店の幅はさらに広がっていった。
近年では、チコリやズッキーニなどのイタリア野菜も日本で栽培されるようになったほか、モッツァレッラチーズなどフレッシュチーズの輸入量が大幅に増え、これに冷凍品も加わり、輸入イタリア食材の市場規模は大きく拡大している。
イタリアにおけるレストラン・ビジネスの動き
1980年代、世界的なイタリアンファッションブームが巻き起こった時、イタリアのレストラン業界は大きな岐路に立たされていた。
戦後の高度成長期から、大都市には多くのレストランができ、人々はこぞって外食を楽しんでいた。そこで期待されたのが、古くからの伝統料理ではなく、新しいスタイルのファッショナブルなレストランだった。その旗振り役となったのが、ミラノにおいてイタリア初のミシュラン三ツ星を獲得したシェフ、グアルティエロ・マルケージ氏だ。彼は、“ヌオヴァ・クチーナ・イタリアーナ(新イタリア料理)”を生み出し、その旗手として、独自の手法で人々を驚かせた。その後、イタリアにも三ツ星レストランが増え、ミラノ郊外の「アンティカ・オステリア・デル・ポンテ」をはじめ、「イル・ソーレ・ディ・ランコ」、「ダル・ペスカトーレ」、「ドン・アルフォンソ」というふうに、ミシュランガイドを作るフランス人の思惑もあって、ほとんどの店が大都市から離れた片田舎にあった。この頃から、日本人の若い料理人がこれらの店を目指すようになり、実際に店に行ってみると、時にはキッチンに日本人が4〜5人いることもあった。

どちらも、リストランテと比べて肩肘張らない雰囲気が特徴だ。
1990年代の不況を受け、イタリアでは財政面での問題から増税が行われ、コストがかかるレストランの経営は、アングラマネーなしには成り立たないほどになっていた。多くのトラットリアが中国料理店に変わり、主要都市を中心に、ピッツェリア・リストランテという新業態が増え始めた。イタリア人は外食好きで、週に一度は家族で外食するファミリーが多い。各ファミリーは自分たちの予算内で外食をしなければならない。そうしなければ、毎週外食を続けることはできないからだ。そこで彼らはなじみの店を作り通うことになるが、ユーロ導入以降、リストランテは高嶺の花となり、よりリーズナブルな価格の店を求める動きと、できる限り幅広い層の顧客を取り込みたいというレストラン側のニーズとが重なり、外食の店の選択理由が大きく変わった。その結果ピッツェリア・リストランテの需要が拡大し、人気を得ることになったのだ。
ピッツェリア・リストランテとは、名前のとおり、ピッツェリアとリストランテの両面を兼ね備えた店である。これにはふたつのタイプがあって、ひとつはもともとリストランテであった店にピッツァの窯を入れ、若い顧客や子供連れのファミリー客にも来てもらおうとしたもの。もうひとつは、ピッツァ中心の店にトスカーナ料理やプーリア料理、魚料理といった特徴を持たせ、ゆっくりと食事をしたい客にもサービスできる形にしたものだ。こういった、TPOによって楽しめる店は、1990年代に大都市から地方へと伝わり、数多くのスタイルの店が生まれた。なかには、平日のランチから夜の軽いディナー、あるいは週末のウェディングなど幅広く使われる店もある。これも、不況による客数大幅減からレストラン経営者たちが新しく見出した業態といえる。また、ある意味リストランテ業態の大衆化ともいえるだろう。しかし、一部のファミリーは価格のさらに安い中国料理店に流れるようになった。
2000年代に入ると、自分なりの時間帯で食事をしたいという消費者のニーズの多様化によって、ワインバーの需要が高まった。長い間、バールというのは、ワインといえば泡、白、赤とだけ書いてあり、そのワインの名称そのものは問われなかったのだが、この頃から、ワインの種類にこだわる店が増えていった。
私が住んでいたミラノは、金融をはじめとするビジネスの街という側面と、ファッションの街という特色があり、多くのファッション関係者が仕事をしていた。当然のことだが、有名デザイナーやファッション関係者が通う店には、自然と若者が集まる。多種類のワインを試すこともできるワインバーは、いつでも食事ができ、夜遅くまで営業していたため、そういった人々の社交場になっていた。そんなワインバーの中でも、きちっとしたおいしい料理を出す店には人気が集まるようになり、さらに、生ハムやチーズ、サラミ類のバラエティを増やすことにより、その魅力も広がった。しかしてこの業態トラットリアやリストランテだけではなく、ピッツェリア・リストランテにも脅威をもたらす存在となっていった。
日本におけるイタリアンレストランの方向性

三ツ星だけあって、つねに盛況だ。
1980年代に始まった日本におけるイタリア料理ブームは、首都圏を中心に広まり、大阪、名古屋、福岡などの都市でもイタリア料理店の開店が相次いだ。なかでも東京では、イタリア料理の個人店の開店が麻布、六本木を中心に始まり、広尾、青山周辺、銀座へと広がりを見せていった。また、その頃のイタリアンレストランのフレンチレストランにはないラフなスタイルも受け、「イタメシ」を食べるというライフスタイルが若者を中心にブームとなった。人気店も数多く誕生し、それから30年以上を経て、今日、全国に存在するイタリア料理店は1万軒に達するという。
ブーム当初はローマを中心に修業したシェフが多く、トマト、オリーブオイルを使った料理が目立ったが、次第にイタリア各地で修業したシェフや、ミシュランの星付きレストランを回り、日本でも高級レストランを目指すシェフも現れ始めた。こうなると、これらの店で仕事をし、基礎を学んでからイタリアに修業に行く料理人が増え、イタリアの大都市よりも、むしろ田舎にあって特徴のある店で修業するようになった。
そんななか、1990年代初頭にピエモンテ地方のカスティリオーネ・ダスティに開設された、イタリア料理学校ICIFの存在は大きい。毎年数十人が、前半にこの学校で学び、後半は学校と提携しているイタリア各地のレストランに入って実際に働きながら研修する。私も2度目にイタリアに駐在した最初の2年、イタリア料理の基本素材の講義をするため、この学校を訪れたことがある。ハードの部分がしっかりしていて、とてもよい学校だった。
そんなふうに、本場イタリアで学んだ彼らが日本に帰国すると、その特徴ある地方料理を披露するようになり、それまでとは違った地方色豊かな店が誕生していった。さらに、イタリアでの経験を活かしながら、日本の素材を使い、日本料理同様にその時々の旬の食材をふんだんに使って特色を出したメニューを提供する店も多くなった。
それにしても、どうしてこれほど、日本人にイタリア料理が受け入れられるようになったのだろうか。
まず、日本にはもともと素材を活かしたシンプルな調理法による日本料理があって、イタリア料理の特長が分かりやすかった点が挙げられる。日本とイタリア両国は、南北に長い島国、半島国で四季があり、地形や気候条件もよく似ている。また、新鮮な素材がたくさんあり、これをシンプルに調理して食べる調理スタイルもよく似ている。そう考えると、中国料理、韓国料理、インド料理など多くの外来食文化を受け入れてきた日本人がイタリア料理をすんなり受け入れたことは、不思議ではない。実際、1980年代にはすでに一般家庭でもパスタは常備されており、スパゲッティとトマトという組み合わせがすでに浸透していたことは、前述のとおりである。
一方、今後の日本におけるイタリア料理の業態について考えてみると、先にイタリアのレストラン業態のところで紹介したピッツェリア・リストランテ業態が、日本においても定着していく気がする。ランチは短い時間でかなりの人数をこなせるし、夜も工夫して料理を考えれば、いろいろな使い方をしてもらえる。また、日本においてもスペシャリストが不足し、人件費の問題を考えなければならないのがレストラン側の現状であるから、解決策として、この業態へのシフトは充分に考えられる。ある程度素材のわかるシェフがいれば、価格的にリーズナブルで、TPOで気軽に使ってもらえる店になるだろう。つまり、ひとつの店をTPOで使い分ける。自分の懐具合によってピッツァですませるか、ゆっくり食事をするかも選択できる。この業態では、ピッツァのみの客に偏って客単価が下がってしまう、という声も上がるかもしれないが、安定して一定数の顧客を得られるとすれば充分にやっていけるであろう。ただし、この業態で忘れてはならないのは、接客のスキルである。TPOで使い分ける大切な常連客のニーズをしっか
りと覚え、把握していることがこの業態の重要なポイントだからだ。
“ザ・ジャパニーズ・イタリアン”のシェフ誕生も遠い先の話ではない
日本人シェフによるイタリアンレストランの可能性

ピエモンテ州アルバの街の中心地に位置する「リストランテ・ピアッツァ・ドゥオモ」は2005年にオープンした。開店からこの店のシェフを務めるエンリコ・クリッパ氏は、料理学校を卒業し、その後フランスの有名店で働き、1996年から3年間、日本でも仕事をしている。神戸の「リストランテ・グアルティエロ・マルケージ」で2年、大阪の「リーガ・ロイヤル・ホテル」で1年間働いた。
その後、イタリアに帰国し、バローロで有名な「チェレット社」で働くこととなるが、最初の2年間は店を持たなかった。その間、彼は毎朝2時間をかけてアルバの朝市へ行って野菜を見て回ったという。2005年に現在の店をアルバの街の中心地に開店するが、そこからなんと、6年という驚異のスピードで三ツ星を
獲得した。彼の料理の基本はフォッサーナ牛を使った肉料理や、アニョロッティなどピエモンテ地方の地元の料理。これにアイデアを加え、独自のスタイルに仕上げている。店では専用の野菜畑を持ち、つねに3人の農夫が管理する。野菜にこだわりを持つ彼ならではである。
今年3月、パリのインターナショナル・アカデミー・オブ・ガストロノミーで、エンリコ・クリッパ氏は今年の世界一のシェフに輝いた。この賞は、イタリアンでは2010年にモデナの「リストランテ・フランチェスカーナ」のシェフ、マッシモ・ボットゥーラ氏が獲得している。一度、エンリコ氏に“自分の料理についての思い”を聞いたことがある。彼曰く、「メインディッシュと聞かれたら、肉ですか、魚ですか、そして野菜ですかと言える料理を作りたい」ということだった。40代中ごろのまだ若いイタリア人シェフが、本気になって、地元の料理をベースに新鮮な野菜を使ったナチュラル&ヘルシーな料理に向かっている。まさに、将来のイタリアンレストランのひとつの方向性ではないかという気がする。たとえば、冬には11種類のサラダを用意し、春には21 種類、夏には31種類を用意する。これをピンセットで食べさせる。同じ野菜でも、葉があり、芽が出て、花が咲く。この植物に対する彼の繊細さがこうしたメニューを創出させるのだろう。
そんな、エンリコ氏の料理を見ると、これは日本人シェフにもできる可能性がある、と思えてくる。日本人の繊細さと、基本に忠実な調理スタイルを活かせば、必ず世界に通用するトップシェフの店ができるのではないかと密かに期待している。そして、“ザ・ジャパニーズ・イタリアン”のシェフ誕生も遠い先の話ではないような気がするのである。

Shigeru Hayashi
イタリア在住13年・イタリアビジネス34年の経験を持つ。1995年、日本人初のイタリアン・プロフェッショナルソムリエ(AIS認定)の資格を取得。
現在はフードジャーナリストとして、イタリアの食文化の普及に貢献している。『最新基本イタリアワイン』(CCCメディアハウス)『イタリアワインの教科書 (よくわかる基礎からDOCG&DOC最新情報まで) 』(イカロ
ス出版)、『国家が破綻しても人生は楽しい? イタリア流ライフスタイルのすすめ 』(万来舎)ほか、多数の著書がある。
林 茂=文・写真提供
本記事は雑誌料理王国274号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は274号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。