

竹炭を使った生地の中にブーダン・ノワールを閉じ込めた「ブーダン・ドック」、菜の花の辛子和えを思わせるような味わいに、削りかけたカラスミが日本の出汁の印象を増幅する「菜の花のタルト」、メインディッシュで提供される尾長鴨のもも肉をコンフィにし、九条ネギや菊芋と合わせてから、スパイスの効いた滑らかなピュレに。カリッと薄いチュイルに包み、滑らかさとクリスピーさのコントラストが楽しめる「尾長鴨と九条ネギ」。
そして、佐藤氏のシグネチャー「イカとカリフラワー」。白で統一された小さなひと皿だが、スライスした生のカリフラワーの下には、表面だけ軽く焼き目をつけた肉厚のアオリイカとカリフラワーのピュレ。むっちりとした食感のイメージが重なる、濃度の高いカリフラワーのピュレとイカ、山の旨味と海の旨味、そしてピュレに使われている果実味豊かでフレッシュなオリーブオイルと、カリフラワーのスライスに絡ませたローストアーモンドオイルの焦げ感までの幅広いレイヤーの味が詰まっている。

北の食材で「春告魚」とも呼ばれる、脂ののったニシンを白バルサミコ酢でマリネし、南の柑橘類、晩白柚と合わせた。細切りにしたウドの香り、ホースラディッシュの穏やかな辛みをフロマージュブランのクリーム感が包み、どこか北欧的な組み合わせ。一粒一粒がキラキラと輝く晩白柚の果肉は、液体窒素をかけて粒をばらしたもの。細切りにした晩白柚の皮のコンフィと共に表面にまとわせ、ニシンとクリームの脂をすっきりとまとめている。

次は食感をテーマに、サクっとしたタケノコとこりっとした白ミル貝を合わせた皿。上に飾られているメカンゾウの芽が食感のアクセントになっている。前の皿のボリューム感ある味わいから一息つくような、ひんやりとした温度帯、食感を生かすために、塩を入れた氷水にくぐらせて身を締め、表面だけ軽く火を通した白ミル貝、タケノコ、メカンゾウの根と、優しい甘みが重なる。少しシークワーサー果汁の酸味でエッジをたてて。

静かで優しいレイヤーの味わいのあと、ここで一気に味と香りのボリュームが上がる。トリュフ、バニラ、バター。官能的な味わいを一口に凝縮させた熱々の百合根。糖度が高く香りのよい帯広産の月光百合根をフランス産バターとタヒチ産バニラでコンフィに、下は月光百合根と黒トリュフのエスプーマ。香ばしく焼き上げた際のヘーゼルナッツのような香り。まるで焼き菓子を食べているような甘やかな一皿は、フランス料理の「グルマンディーズ」の要素を集約させたような印象だ。

前の皿のインパクトを一旦リセットするような、石垣島産の南ぬ豚(ぱいぬぶた)を塩漬けにし、味を凝縮させてから作ったピュアな味わいのスープ。もっちりしたラビオリの皮にはちょっと猪を思わせるような温かみのある香りの肉がぎっしりと詰まっている。噛むと、フキノトウの野趣、味噌と混ざって濃厚さが増した豚肉の香りがフワッと広がる。上には、小さいフキノトウの花が3つ散りばめられ、苦味のアクセントになっている。

「フランスの魚に比べ、日本の魚はどうしても味が繊細すぎたり、日本料理の方が合うような気がする、それならその繊細さを生かした料理を」と、アヒージョのようにニンニクとオリーブオイルで火入れをし、セリをたっぷり使ったリゾットと合わせて。「作っているうちにどんどんセリが増えてしまって」実は米の4〜5倍のセリが入っているのを、優しいシラウオ の味とリゾット に入っているパルミジャーノ・レッジャーノチーズが受け止める。

チーズつながり続く次の皿は、フランスの春の風物詩、ロワール産のホワイトアスパラガス。その火入れがとても印象的だった。茹でるのではなく、鮮度のよい素材そのものが持つ水分を生かし、フランス産発酵バターの中でじっくりと火を入れたそうだが、しっかりと火を入れることでホワイトアスパラガスの甘みが最大限引き出されている。最高の状態の火入れで、出来立てを供するため「アスパラガス専門」のスタッフを2名つけるほどのこだわりだ。添えられているサバイヨンは上質なヴァンジョーヌのアルコール感をしっかり残してあり、フランスの著名なチーズ熟成士、ベルナール ・アントニー氏が熟成したコンテチーズ、生クリーム、卵黄と合わせてある。秀逸だったのは花うどの葉、香りはヴァンジョーヌに、ほのかな苦味はアスパラガスに合わせて、今、この時期の日本でしか食べられない皿に仕上げてある。

様々な赤い甘みをまとめたさっぱりとしたグラニテ的な位置付けの皿、イチゴに、イチゴエキスでマリネして甘みを加えたトマト、辛みよりも甘味が際立つ唐辛子、ポブラノをサラダのように仕立て、上にイチゴのチュイルを飾って。ポブラノの穏やかな辛みは、食欲が増進させるだけでなく、唾液が出ることで前の皿の印象をリセットし、口の中がさっぱりとするという役割も。

フランスの春の食材、乳飲み仔羊の中でも極上のロゼール産をこのために特別に取り寄せ、きめの細かい肉質を、桜の葉の甘い香り、仔羊の骨などからとったフォンを軽やかにオリーブオイルで乳化させたソースでいただく。

ワラやヒノキの香りをつけながらローストした新潟の網獲りの尾長鴨は、しっとりとしたベルベットのような食感と皮のクリスピーさの対比が楽しめる。春が旬の葉ごぼうは、根は揚げて、茎はソテーにと別の調理法で仕上げ、フキのピクルスを飾って。鴨とオレンジは定番のコンビネーションだが、ソースは鴨の骨のフォンに熟成バルサミコ酢、宇和島産のみかんジュースを煮詰めて仕上げ、甘いスパイスの香りをまとわせた。

鴨の赤身の香りをすっきりとさせてデザートへの橋渡しをするのは、日本人なら誰しも癒される、ヒノキの香りのプレデザート。世界で活躍する著名なミクソロジスト、南雲主于三氏の協力のもと、ヒノキの香りを移したジンで作ったジントニックを更にシャーベット状にし、キウイフルーツと合わせたもの。最後にヒノキのエキスを垂らして、香りを立てる。

コースの最後に合わせて軽やかに、意外性がありつつも王道のデザートを、ということから生まれたのが奄美黒糖のミルフィーユ。軽やかなパイ生地に合わせてエスプーマで仕上げることで、しっかり、たっぷり絡ませられるカスタードは奄美黒糖が味わいのコクも加える。
そして、印象的だったのが添えられたラムレーズンのアイスクリーム。パナマ産の21年物のラム酒にバニラビーンズを漬け込み、そのバニラを使った極上のアイスクリームを作成。更に、同じラム酒に大粒の干しぶどうを漬け込み、直前に混ぜてサーブすることで、極上のラムとバニラの華やかな香りとしっかりとラム酒を吸い込んだ干しぶどうのジューシーさを満喫できるアイスクリームに仕上げてある。

発酵によって引き出された、フルーツのような酸味が魅力のカカオハンターズ社の2種類のコロンビア産チョコレートを使ったデザート。赤いフルーツの印象があるシエラネバダ産チョコレートのガナッシュと、よりすっきりとした味わいのアルアコ産のチョコレートのソルベに、高田氏自らが発酵させた、ハスカップのジュースを合わせ、更にカカオパルプを煮詰めて作ったグラニテを合わせるなどして、「糖分や乳脂肪を加えてしまうと、おいしいチョコレートになってしまう」(佐藤氏)ということで、その手前のカカオという素材の香りと酸味を生かしたデザートとなっている。

小菓子はヘーゼルナッツのメレンゲに、栗の蜂蜜が香るプラリネクリームを挟んだもの。
冬から春を迎えようとする今。フランスと日本の、極上かつ希少な食材を、異なる2つの視点から磨き上げ、昇華させた料理の数々。料理は本質的に不可逆的なものだが、「いま、ここでしか食べられない」という、瞬間を捉えた贅沢な料理を頂いたと感じた。
このコラボレーションが捉えたのは、食べる側の心だけではない。席数50に対して、調理に携わったのは30人、サービススタッフ30人という異例の多さ。
今年10月に隈研吾氏デザインのファインダイニングをフランス・パリに開業予定の佐藤氏、数々の賞のみならず、3月16日開業の日本初のWホテル、「Wホテル大阪」の飲食部門をコンサルティングする高田氏と、これからの動向も注目される両シェフ。そんな2人のもとで働きたいと、日本各地から研修を希望する若手料理人が参加していたからだ。このフェアの立役者である、ホテルニューオータニ(東京)の岩崎州彦氏によると、ニューオータニ では通常、関係者以外は研修を受け付けていないが、このフェアの際には、きっちりと健康診断をした上で、特別に参加してもらっているという。それには、未来につなぐ、こんな思いがある。
「こうして集まって来た若手料理人は、『将来は自分も海外で開業したい』などの明確な夢を持っていて、少しでも多くを学びたいと、目の色が違う。彼らにホテルのスタッフも良い刺激を受けています。『いつかパリに店を出したら、このフェアをさせてください』なんて声も聞きます。このフェアが、彼らが夢を具体的に描く手助けとなり、未来の『世界で活躍する日本人シェフ』を生み出すきっかけになれば」。
また、20年という長い年月をパリで過ごして来た佐藤氏にとって、食の視座はフランスにあり、日本は故郷でもあると同時に「旅先」でもあるという。「旅はインスピレーションの源。コロナ禍もあり、日本で多くの時間を過ごし、高田シェフとたくさん話し合い、同じ厨房で料理を作りあげることで、良い刺激を得られる、深いコラボレーションになりました。また、フランスをはじめとする海外に行けず、外食も控えていたお客様から、ガストロノミーの喜びを伝えていただけたことが嬉しかったです」と、シェフとしての思考を深める時間ともなったようだ。
社会が変わりつつある今、未来の料理、ガストロノミーはどうなっていくのか。2人の心に映る景色が見たくて、抱いていた疑問を投げかけてみた。
2人が口を揃えて言ったのは、「コロナ禍でも料理そのものは変わらない」ということ。「そんなことで変わるような料理を作っているつもりはないです」と佐藤氏が言えば、「(コンサルティングの仕事を増やすなど)ビジネスのスタイルが変わることはあっても、料理自体は変わらないですね」と高田氏もうなずく。「だって、うちはうまいもの屋だから」。そう、「おいしい」は、どんな時代の荒波にも負けない、正義なのだ。
こんな記事もよく読まれています!
仲山今日子=取材、文 依田佳子=撮影
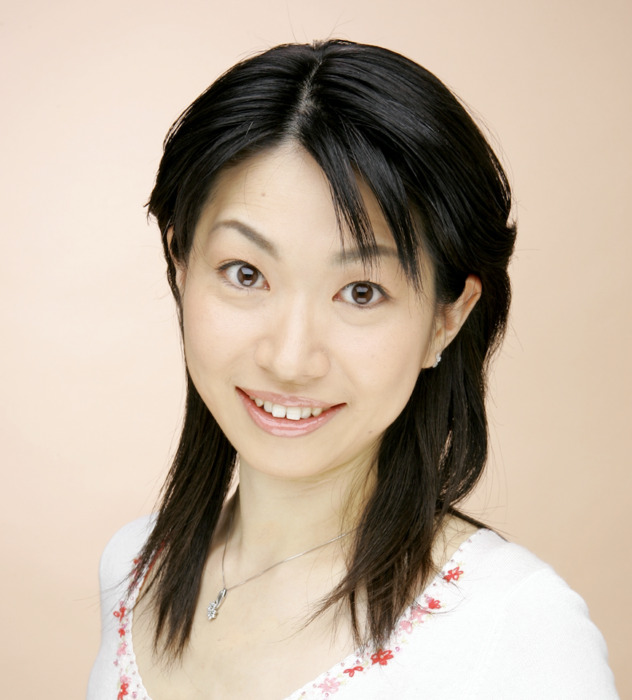
仲山今日子
ワールド・レストラン・アワーズ審査員。元テレビ山梨、テレビ神奈川ニュースキャスター。シンガポール在住時、国営ラジオ局でDJとして勤務。世界約50ヶ国を訪ね、取材した飲食店や食文化について日本・シンガポール・イタリアなどの新聞・雑誌に執筆中。

