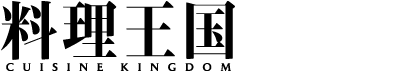「みえガストロノミーツーリズム フェスタ」から見る三重の美食の未来

24年3月、三重県・多気町の商業リゾート施設「VISON(ヴィソン)」内にあるAT CHEF MUSEUMにて、「みえガストロノミーツーリズム フェスタ」が開催された。伊勢神宮や熊野古道など、観光資源には事欠かない三重県。食についても松阪牛や伊勢海老のように、古くから観光客たちを魅了してきた食材も多い。しかし今、ガストロノミーツーリズムに求められているのは単に「食べること」以上の、そこでしかできない食を通じた体験だ。その実現に向けて、高らかなキックオフの場となった。

24年3月、三重県多気町、VISON内のAT CHEF MUSEUMにて、「みえガストロノミーツーリズム フェスタ」が開催された。AT CHEF MUSEUMは全国の18名のシェフによる、三重県産食材をふんだんに使った監修メニューが一度に楽しめる施設で、三重県の食の発信基地として「フェスタ」の開催には特にふさわしい場所と言える。今回は23年度の取組の発表と、未来に向けた提言としてパネルディスカッションが行われた。

伊勢海老や松阪牛に代表される豊富な食材、それらを提供するレストランや宿泊施設が揃った三重県を訪れる旅行者にとって、「グルメ」は大きな目的の一つだ。三重県は、そこをさらに磨き上げて「ガストロノミー」として昇華し、三重県のそこでしか食べられない料理、そこでしか体験できない食文化を発信していくことで、感度の高いフーディーの誘客につなげることを目指し、「みえガストロノミーツーリズム」を掲げる。
その一環として行われているのが、今回のフェスタの第2部で表彰式が行われた「みえの食レシピコンテスト 2023」であり、県内5エリアの事業者への伴走支援事業だ。23年度は公募で集まった10エリアの中から有識者による選定会議で、一般社団法人グリーンクリエイティブいなべ、一般社団法人四日市観光協会、VISON、志摩市、そしておわせむかい農園の5つが選ばれた。
この「フェスタ」の会場にもなったVISONのある多気町はサンセバスチャン市と「美食を通じた友好の証」を締結している。現地のバル3店舗がVISON内に出店、定期的にシェフも来日し直接指導を受けながら運営されているほか、施設内のレストラン「IZURUN」はICEX(スペイン貿易投資庁)による、高品質なスペイン料理を提供するレストランの認定プログラムである「RESTAURANTS FROM SPAIN」にも認定されている。

そんなVISONが目指しているのは、スペインのバスク地方のように「食の巡礼のメッカになること」と「地域を巻き込み、みえガストロノミーツーリズムを盛り上げること」。今回の事業の中ではVISONを核とした「三重県サンセバスチャン構想」を打ち出し、AT CHEF MUSEUMを県内の料理人向けカンファレンスに活用することや、VISON内のレストランで伝統野菜の伊勢芋や特産品である次郎柿を使った特別メニューの提供など、地域との連携を図ってきた。今後は、三重県内の他の地域の特産品も巻き込んだフェアの実施のほか、第2回世界料理学会 in VISONや全国高校生ガストロノミー甲子園の開催も予定されており、三重県内の食の産地を繋ぐ「ハブ」となることが目標となっている。

伊勢志摩国立公園に指定されている志摩市は古くから朝廷や神宮に食料を献上していた「御食国(みけつくに)」として知られ、伊勢海老や鮑をはじめ、的矢かきやあおさなど豊富な海産物に恵まれている。また、奈良時代から続く波切の鰹節の伝統を今に伝える天ぱくや、海女さんと一緒に囲炉裏を囲んで食事ができる海女小屋体験施設、さとうみ庵など、地域で育まれた食、食文化を体験できる観光資源はすでに備わっている地域だ。

今回の事業ではこうした観光資源という点をストーリーという線で結んでルート化することが行われた。そしてその先には、地域全体が一体となって面として観光に取り組み、持続可能な食の旅として続いて行くことが目指されている。

尾鷲湾の南側、尾鷲港を一望する山の斜面に位置する尾鷲市向井地区。1960年代以降およそ60年間にわたって、中部電力尾鷲三田火力発電所がこの地域の重要な産業を担ってきた。しかし、それが2018年12月に廃止となってしまった中で、「鉄から土へ」を合言葉に発電所が栄える中で耕作放棄されて行った段々畑を借り受けて始まったのが、おわせむかい農園だ。ブルーベリーや希少なフィンガーライムなど、そして発電所以前に植えられてずっと農薬もまかれずに放置されてきた段々畑の甘夏に加え、彼らが取り組んでいるのが虎の尾という、この地域のみで栽培されている伝統野菜の青唐辛子だ。漁師が船上で魚を刺身で食べる際にわさびの代わりに薬味として使う習慣があり、「漁師の刺身唐辛子」とも呼ばれている。


虎の尾は、アルヴァの平木正和シェフが毎年使っており、INUAのスーシェフだった石坂秀威シェフが商品開発を担当するシーベジタブルの「Re-seaweed」ブランドでもヒジキと合わせた商品が作られるなど、その美味しさはトップシェフたちにも評価されている。その一方で、高齢化により生産者が4名まで減ってしまっていることと、連作障害の出る植物であるために栽培地を毎年変えなければならず、新規参入のハードルが高いことで、近い将来の絶滅という危機に直面しているのが現状だ。
そうした中でおわせむかい農園では、23年8月にオープンした「海が見えるだんだん畑のキャンプ場 minore」を活かし、調味料としての虎の尾とキャンプ場から眺める景色、そこで過ごす時間の全てがスパイスとなるガストロノミーツーリズムに取り組んで来た。これからも継続的に虎の尾の消費拡大と安定供給を目指すとともに、次の世代の育成に向けて若年層への訴求、発信を続けていく予定だ。


こうした事業者たちの取組を含む三重県全体の「みえガストロノミーツーリズム」の向かうべきところ、未来への提言が、パネルディスカッションでは語られた。登壇したのは日本ガストロノミー協会会長でVISONの伴走支援も務めた柏原光太郎氏、ヴィソン多気株式会社代表取締役の立花哲也氏、そして三重県を代表する料理人としてTHE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 賢島の今村将人シェフの3名だ。

最初のテーマは三重のガストロノミーツーリズムの可能性について。まず柏原氏からはそもそものガストロノミーの歴史と定義が語られ、コロナ禍が収まったらどこに観光に行きたいかというアンケートで日本が世界中で1位だったことが紹介された。そして、世界中の観光が好きな人たちにとって、美味しいものを食べたいから日本に行く、というのは共通の概念になっているという。このような状況を背景に、特に地方の、そこにしかないものを食べに来てもらうというのが非常に注目の取組になっていると話す。
それを受けて実際に現場でゲストを迎える立場の今村シェフは、東京にいた頃は日本中、世界中からあらゆる食材が集まって来るが、その鮮度に重きが置かれることはあまりなかったという。一方でここ三重では、今の時期だったら生のワカメをゲストの目の前で湯がくその瞬間に変わる色に驚かれ、それが一番の体験だったと言われることもあるそうだ。これは塩蔵や乾燥させずとも新鮮なワカメが手に入る地元ならではのガストロノミーだ。

また、三重県のガストロノミーツーリズムの未来に向けてというテーマでは、県の推進事業を受ける経営者の立場から立花氏は、4月の世界料理学会 in VISON、夏にはシェフのフェスや料理の甲子園のような企画も実施予定であることを紹介してくれたが、そういった活動は一部の取組になりがちで、だからVISONは地域や県と連携し、みんながここで学び合うプラットホームのようの場所を目指すと語る。さらに柏原氏が、レストランを起点にその周りの生産者などまでを巻き込んだコミュニティが日本の各所で形成されていることを紹介し、三重県は人も温かく情報を共有する動きがあり、自然の美味しい食材も揃っているなど、三重県独自のガストロノミーが成立する土壌は既に揃っており、後は中心で起爆剤となる料理人が出てくれば、と話してくれた。
そして最後に、「今村シェフがいうように、食べ手から見ても都市部には何でもあるけれどどこか『丸い』ものが多いです。逆に地方にはとんがったもの、キラキラしたものがあると思います。キャビアもフォアグラもないかもしれないけれど、ここにしかない、鮮度が落ちるのが早くて東京まで持って行けないようなエビや魚。こういうのが三重の良さだと思っています。そしてそんなとんがった食材を調理するのが好きな料理人はやっぱりとんがっているんですね。今まではそのとんがりがなかなか理解されにくかったけれど、デスティネーションレストランのような言葉が出て来たように、その価値がようやく認められるようになってきました。だからそんな食材の多い三重にはものすごい可能性があって、そこをもっと発見、発掘していければ、複合的な良さが出て来ると思っております」と語りディスカッションを締めた。
そして一見知事が「三重県には食材は揃っているけれども、これをガストロノミーに高めていくために重要なのが人ですね。三重県の人は温かい人が多いけれどそれだけではなく、東京や海外を経験してきた人たちに助けてもらうのが大事で、三重県は助けてもらう素地も事業性もあるので、そういった形で取組をまとめていきたいと思います」と、次年度に向けての展望を語ってくれた。

みえガストロノミーツーリズム
https://mie-gastronomy.com/
text: Otohiko Kobayashi photo: Tetsuo Ogino
関連記事