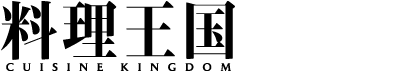高温か、低温か、によって生まれる食感の個性。「志摩観光ホテル」総料理長 樋口宏江シェフの火入れ

松阪牛をポワレに
低温調理のあと燻製の香りを一瞬まとわせる
三重は松阪牛の産地。フィレ肉を真空包装して63℃で15分間湯煎する。燻した伊勢茶の香りをまとわせてからフライパンで焼く。低温調理にすることで、うま味が出てやわらかくなり、上質な脂も肉にじんわりと浸透する。
伊勢茶の香りをまとわせた松阪牛のフィレ肉
焼きリゾットにかつおのコンソメをかけて

ステーキの下にはもち麦の入ったリゾット。チキンブイヨンとトマトウォーターを1:1で合わせたものにかつお節を加え香りを移し、そのスープをお茶漬け風に注いで食べる。地元宮川産わさびと青ねぎを添えて。
火入れを語る
樋口宏江 シェフ
「志摩観光ホテル」には「鮑のステーキ」「伊勢海老のクリームスープ」「松阪牛のステーキ」といった伝統的なスペシャリテがあります。それらは完成されたおいしさであり、ずっと大事にしたいと思っています。そのいっぽうで、今という時代のなかで私が表現できるものは何か? と考えたとき、まず香りが浮かびました。たとえば、鮑を高い温度で長い時間加熱すると、とてもやわらかくなってうま味も出てきますが、どうしても香りは飛んでしまいます。素材が持つ香りをもっと引き出せる方法があるはず。鮑ならば、最初に下ゆでしているときに感じる、あの磯の香りを引き出したい。そう思いました。
ある日、日本料理の方が鮑の磯の香りを残す最適な温度を調べられているのを知りました。厨房機器が発達している現代は、コンベクションオーブンが使えます。さまざまな温度を試す中で私がよいと感じたのが57℃。やわらかさを保ちつつ、とても香りが立つ鮑に仕上がりました。「香りを生かす」という点でも、低温調理はすぐれています。牛肉は63℃で調理を行います。やはり香りで印象を残したいので、伊勢茶の茶葉を低温で燻し、緑茶の香りを残しつつ香ばしい香りを肉にまとわせます。
メインの香りを生かすことを意識すると、合わせるソースや付け合わせも自然とその香りに寄り添うように、軽やかなものになっていきます。これまでの伝統的なフランス料理がうま味をまとうものとすれば、今私がやろうとしていることは、従来のフランス料理のおいしさに加え、もっと香りも楽しんでほしい料理といえるかもしれません。伊勢海老もそうです。身質を活かして短く火入れし、殻を熱源に当てて香ばしい香りを引き出す。この2つの要素をアロゼで生み出しています。
ここは目の前が海ですから、揚がったばかりの素材に香りの立つ火入れをして提供することが無理なくできる。それが、私が思う「火を通して新鮮」ということかも知れません。

樋口宏江
1991年「志摩観光ホテル」に入社。 2014年に総料理長に就任。16年5月の伊勢志摩サミットでワーキングディナーを担当し、高い評価を受ける。19年「ミシュランガイド」にて「ラ・メール」がミシュラン一つ星。
高橋忠之シェフが遺したもの
昨年12月に亡くなった「志摩観光ホテル」の元総料理長、高橋忠之氏は生まれ育った志摩を離れることはなかった。「火を通して新鮮、形を変えて自然」とする料理哲学と味の追究を、志摩の海を通して貫いた。素材に対する先入観を一度壊し、フランス料理の考え方にのっとった調理法によって、鮑は鮑以上に、伊勢海老なら伊勢海老以上の表情を見せる料理に仕立てた。日本でなければ、伊勢でなければならない普遍的な料理が、彼のスペシャリテとして今も親しまれている。

text 小林みどり photo 天方晴子
本記事は雑誌料理王国309号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は 309号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。