
時は80年代初頭の日本のフランス料理〝黎明期〞、ある画期的な料理ムックが出版されました。専門家の味をあなたの食卓に――。そのサブタイトルが示すとおり、一般家庭に向けて、プロの料理人さんたちにご自身の手の内を、ぜ〜んぶ、披露してもらっちゃいましょう〜!という前代未聞、大胆不敵なシリーズがそれ。創刊編集者の大本幸子さんが当時を振り返り、シェフと編集部をめぐる喜劇と取材秘話を生き生きと語ります。
「シェフ・シリーズ」は、1981年5月、当時「ビストロ・ド・ラ・シテ」、「オー・シザーブル」勝又登シェフ(現「オーベルジュオー・ミラドー」)を皮切りに、中央公論社(現中央公論新社)より出版された料理ムックのシリーズです。1999年、77号を終了とするまで長く続いたので、まだご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。このページをお読みの方の中には、お仕事をお願いした方もいらっしゃるかもしれませんね。大変お世話になりました。
たまたま、私は創刊号から15号及び別冊まで16冊の担当編集者に命ぜられ、現代フランス料理黎明期ともいうべき時代の風を存分に体験する幸運に恵まれました。フランス本土ではヌーヴェル・キュイジーヌが評価を得た時代、フランスへ渡った料理人さんたちが新しい知識を身につけ続々と帰国を始めた時代、フランス本土でも日本でもヌーヴェル・キュイジーヌをよしとする派しない派が入り混じった大きな転換期でした。他方、日本を基地に切磋琢磨し、フランス料理の哲学を皿の中に表す力を得た面々がめきめきと料理を発表しはじめた時代でもありました。

創刊号
フランス料理の魅力
ビストロ・ド・ラ・シテ、レストラン・オー・シザーブル 勝又登
1981年5月

2号
小さなコース料理
ビストロ・ボン ボワザン、ビストロ・プティ ボワザン毛利進
1981年6月

3号
海の幸スペシャリテ
志摩観光ホテル 高橋忠之
1981年7月
どんなジャンルであれ、黎明期は興奮期です。「健康によい料理が注目されているんです」「いやいやオーソドックスこそ本流」。誰もが興奮し、技術を持ち帰った者は知らせたい気持ち、行かぬ者は知りたい気持ちで満ちていました。加えて、これまで技術一辺倒であった世界に、料理に哲学があることをも持ち帰ってくださったことは、画期的な収穫であったと思います。この時期を境に、伝統と格式でかためられていたフランス料理界に風穴があき、作り手の個性に満ちたしなやかな料理が次々に発表されることとなりました。その様は、満々と水をたたえた川が機を得て流れ出るよう、怠らず手入れを施した花園でここぞとばかりに薔薇の花が開き始めるよう、その勢いは足音がドスンドスンと聞こえてくるような止めることができない巨大な動きでした。そんな時期に私はシェフ・シリーズの編集を命ぜられたのでした。
しかし、在籍の出版社は料理専門ではなく、私はまったくの料理の門外漢。たとえ家庭向けとはいえ、知識はなく真っ白な吸い取り紙のようなものでした。私は読者と同レベルの素人、私が面白ければ読者も面白いはず。こんな乱暴な出立でした。本稿では、かくものレベルで始めた私の仕事体験を通して感じた時代、驚きを、少しばかりご披露したいと思います。

4号
魅惑の南仏料理
レストラン・シェ・ジャニー春田光治
1981年7月

5号
季節の貴婦人 オードヴル
ラ・ロシェル 坂井宏行
1981年10月
シリーズの企画に当たっては、皆さんの本が同じ内容にならないことを留意しなければなりませんでした。しかし幸いにもそれは杞憂で、皆さんはそれぞれにお考えが違っていてバラエティ豊かでした。トップ号の勝又登シェフは、素人が読者とご存知の上、しかし、ともかくフランス料理の現況を伝えたい思いでいっぱいでした。古典もヌーヴェルも元は同じであること、でもここが違うということを、実例を挙げながら諄々とやさしく説いてくださいました。「ボンボワザン」の毛利進シェフ(2号)からは、「せっかくなら3品くらいのコース仕立てにしたら?」と提案されました。ならばオードブルもデザートも連携的に習えます。素人では考えつかないプランでした。北岡尚信シェフ(10号)は10品でコースの提案でした。ちょうど、ムニュ・デギュスタシオン真っ盛りの時期でしたから、そんなご提案が出たのだと思います。
1年に6冊ペースの出版では編集作業は私一人ではとても足りません。アシスタントを募集しました。なまじっかの知識は邪魔、条件は素人であること。本物の素人が寄ってたかって取材に行きました。シェフたちもさぞや面食らったことでしょうね。
キーは「なぜ」です。「いかに」だけではだめ、「なぜ」を聞かなくっちゃあ。シェフさんたちはそういうことを学んでいらっしゃったのですから。「なぜ、そうするのですか?」「なぜ、この料理をつくってくださったのですか?」果ては、「なぜ、この料理はおいしいのですか?」とまで聞いたものです。そうしたら、皆さん、「それはね、こういう理由でおいしいのですよ」と、きちんと答えてくださる。いえ、「おいしいのですよ」とはおっしゃいません。「おいしいと思うのですよ」とおっしゃるのです。皆さんは自信に満ちてはいるのだけれど独りよがりなところがなく、本家のフランスに敬意を忘れず、しかし、ここは日本だから学んできたものが通用するかどうかを心配しているような物言いでした。
それはそうでしょう。フランスとは食材が違う、水が違う、空気が違う、日の光さえも違うのです。しかも、食べ手はフランス人ではなくて日本人なのです。でも、本物を教えたい。フランスで絵を学んだ画家が帰国して戸惑うのに似ていたのではないでしょうか。取材時にはいつもそんなことが話題でした。ハーブとは、ブーケ・ガルニとは、トリュフとは、新しい西洋野菜のいろいろ。親切極まりない説明つきです。えっ、トマトを調味料にするなんて!トマトの皮のむき方も絶対に載せましょう。今では言うまでもないことも、その頃はニュースでした。フレッシュハーブは滅多に手に入らず、写真を見るとレタスの芯の小さな葉やパセリをあしらっているものもあります。大ホテルならいざ知らず、フレッシュトリュフも手に入りにくく缶詰でした。缶詰には白いマーブル模様はなくて、香りもあるようなないような…。こんなコリコリする味もないものがなぜ媚薬?「フレッシュはとっても香りがいいんだけれど、これは缶詰だから。手に入ったら見せてあげましょう」。数年後には、ハーブはもちろんのこと、フレッシュのトリュフもフォワグラも当たり前のように厨房にありました。不足をかこった料理人さんの働きかけが、市場を豊かにしたのでした。今はどうでしょう。ないものがありません。

6号
野生が香る フランスの地方料理
オー・シュヴァルブラン 鎌田昭男
1981年12月

7号
肉の調理ノート
カフェ・ド・ニース 野口新生
1982年7月

8号
日本の素材イタリア料理
りすとらんて・はなだ ルイジ・フィダンザー
1982年5月
日本で育ったフランス料理も注目でした。〈火を通しても新鮮、形を変えても自然〉。これこそが真髄と看破なさった「志摩観光ホテル」高橋忠之シェフの一冊(3号)。磯の香りがするような、潮騒が聞こえてくるような、力強さにおいて追随を許さない皿々でした。仕事の美しさでは右に出るものはいないと言われる坂井宏行シェフ(5号)は、日本料理とフレンチの技術と考え方を交じり合わせた繊細なオードブルの数々で食いしん坊を驚嘆させました。
「シェ・ジャニー」春田光治シェフは、「料理に昔も今もない。おいしさの原理は同じ。私は大好きな南フランス料理を紹介したい」と、実に、のびやかに南フランスを再現してくださいました(4号)。そうした料理は初見でありました。なのに、今までどこかで食べたことがあるような印象があります。つまり、春田シェフは、無理のなさが哲学であったのでした。
各号の紹介をしても退屈でしょうか?でも、こうした考えや手際の違いこそがシェフの個性でした。仕事ぶりもそれぞれでした。スタッフとにぎやかにやっているシェフもいれば、緊張びんびんの厨房もあり、千差万別。が、厨房のドアから出てくる皿はいずれも驚きでした。

9号
リヨン料理
ア・ラ・メゾンマリー・クロード 長尾和子
1982年6月

10号
皿数で楽しむ家庭フランス料理
プティ ポワン 北岡尚信
1982年8月

11号
ウィーン菓子
新宿中村屋グロリエッテ 横溝春雄
1982年10月
当方、なにせ経験がないのですから、なにを見ても驚くのですが、それにしても、日本料理でいうところの単色の繊細さとはまったく違う、力強い色合い、力強い香りがありながらの繊細さ。それに、実に美しい。これはヨーロッパ絵画の美しさだと思いました。じゃがいものグラタンのどっしりとした金色の輝きに言葉を失いました。昨今は美しいというとまるでいけないことのようですが、美しいことはいけないのでしょうか。この時期にフランスを習い覚えたものとしては、残念でなりません。魚料理も肉料理も、そのひとつひとつがフランスと日本は違うと語っていました。口にすると、香りが違う、塩味が違う、ナイフのあたりが違う。フランスは外国なのでした。盛りつけもこれまで知ったものとはまったく違うものでした。読者も私同様に驚いてくださったに違いありません。フランス経験のある画家や音楽家の方々からは、毎号送って頂戴とリクエストをされました。若い料理人さんがこのシリーズを握り締めてフランスに渡っていくんだよと聞かされて、どきどきしたこともありました。
現在「東京ドームホテル」総料理長を務めていらっしゃる鎌田昭男シェフは、フランスから帰国なさったばかりで、オープンに向けて工事中の六本木「オー・シュヴァルブラン」に案内してくださいました。道々、これからこんな料理を出したいんだと思いのたけを語ってくださるのです。語っても語っても言葉がほとばしり出てしまう。皆さんそうでした。眼が輝いて、とどまるところを知りませんでした。鎌田シェフは「フランス料理は地方料理を知らなければ理解できないからね」(6号)と、地方の料理をご紹介くださいました。「ガチョウの首の詰め物」だとか、「蛙のスープ」だとか気を失いそうな料理が続々。少しばかり知識を得た現在、あの折に教えていただいた料理がどれほどの宝であったかが理解できるようになりました。後年、オーベルニュの旅の中、教わった「アリゴ」を市場で発見して嬉しかったことといったら!「カフェ・ド・ニース」野口新生シェフの肉料理(7号)では、ヨーロッパの伝統の肉文化の深さを再現していただき、「マリー・クロード」長尾和子シェフからは、リヨンのレストラン修業の間にホームステイしていた家庭料理の数々(9号)をいただきました。リシャール家のおばあちゃん伝授の料理は、温かみに満ちた出色のリヨン地方の家庭料理で、たいそう好評でした。「クイーン・アリス」石鍋裕シェフ(12号)には、材料は町のスーパーマーケットで手に入るもの、手法は家庭レベル。本当に家庭で作れる、でも、とってもおいしい料理をとお願いしましたら、「はいはい、こんなのどう?」と、いとも軽々と、簡単ながらセンスの光る数々を教えてくださいました。
シリーズを始めて2年後、時代は野菜が話題となっておりました。「銀座レカン」城悦男シェフの手になる野菜料理集(14号)は、目を奪う華やかさと重厚さに満ちていて、地球の向う側では野菜料理もこんななんだね〜と、読者は目論見通りに驚いてくれたようでした。間にイタリア料理、スペイン料理、ウィーン菓子をはさみ、東京プリンスホテル「ボー・セジュール」ジョゼ・アリミシェフ(15号)、別冊「野菜図鑑」を最終に私は退社し担当を終えました。ジョゼシェフの料理は、まさにフランス人の作るフランス料理。どっしりと貫禄がありました。
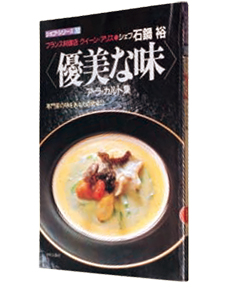
12号
優美な味
クイーン・アリス 石鍋裕
1982年12月

13号
日本の素材 スペイン料理
ロスプラトス 高橋俊明
1983年4月
この原稿を書くために、今、あらためて15冊を並べています。もう四半世紀も前の料理というのに、どの料理にも古めかしさを感じません。色合いの鮮明な野菜、ふっくらと焼けた魚や肉、ソースの濃厚さ。この素材はこうするとおいしくなるんですよと語りかけているようではありませんか。
初期シェフ・シリーズの時代はおいしさを率直に表わした時代ではなかったでしょうか。家庭向けにと企画されたものでしたが、うさぎも鹿もいのししも並びました。あらら、叱られちゃう。「どうしましょう〜」。編集長に訴えたところ、「時代の記録だから」と答えが戻りました。そう、まさに私は時代の記録係でありました。しかし…、と思います。であればなおのこと、当時の私にもっと知識があればシェフの皆様をもっと的確に表現する本作りができたでありましょうに。それを思うと、まことに申し訳なく、シェフの皆様にも食いしん坊の読者の皆様にも、ご容赦をお願いするばかりです。ほんと、不足だらけの記録係で申し訳ないことでございました。
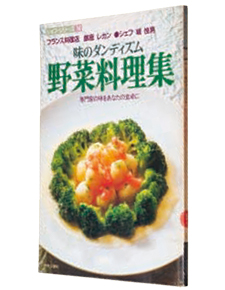
14号
味のダンディズム 野菜料理集
銀座レカン 城悦男
1983年6月

15号
パリ←→東京の合わせ味ボーセジュール
ジョゼ・アリミ
1983年8月
text 食のジャーナリスト 大本幸子
長瀬ゆかり ― 写真、写真協力/中央公論新社
本記事は雑誌料理王国155号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は155号発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。掲載されている商品やサービスは現在は販売されていない、あるいは利用できないことがあります。あらかじめご了承ください。

