
2020年2月、新型コロナウイルス感染症が流行する直前、今思えばぎりぎりのタイミングで、日本ホテル(株)統括名誉総料理長の中村勝宏氏が会長を務め、「和」「洋」「中」の一流のプロフェッショナルが集う会である「ゴブラン会」の基調講演で食品ロスへの取り組みについてお話しさせていただいた。

講演後、中村シェフ考案の料理がホテルの会場に並べられた。中でも、「もったいないメニュー」と名付けて、普段は使われないような素材を活かした料理は必見だった。京にんじんの皮を使った人参寄せや、出汁を取ってから乾燥させた鰹節を添えた、海老芋と椎茸の包み揚げ、残りご飯を利用したお米のガトー(杏のクレームと共に)など、工夫が凝らされていた。中でも驚いたのが、バナナを皮ごとコンフィにしたデザートである。生まれて初めてバナナの皮を食べたが、さすがに長時間かけて調理されただけあって、まったく違和感なく美味しくいただいた。

ここで思い出されるのが、世界ベストレストラン50で世界一の座を獲得した、イタリアの「オステリア・フランチェスカーナ」のオーナーシェフ、マッシモ・ボットゥーラ氏だ。2015年、イタリア・ミラノで開催されたミラノ国際博覧会(ミラノ万博)でもその名を知られた。筆者も5月の開催スタートとともに渡航し、万博会場を見てまわった。テーマは「地球に食料を、生命にエネルギーを」だった。詳しくは書籍『世界一のレストラン オステリア・フランチェスカーナ』(池田匡克著、河出書房新社)に記述があるが、ボットゥーラ氏は、ミラノ万博で生じる食品ロスを使って料理し、食事を求める人たちのための食堂(Refettorioレフェットリオ)を開設したのだ。
鮮度が落ちてきた野菜や果物、肉やチーズ、固くなってきたパンなどを使い、トップシェフが料理し、恵まれない人に無償で提供する。ボットゥーラ氏は、このレフェットリオに到着すると、まずは冷蔵庫を開けて「今日はなにがあるんだ?」と言って料理をはじめると言う(前述の書籍より)。わざわざ食材を買い揃えるのではなく、あるもので作るという姿勢なのだ。
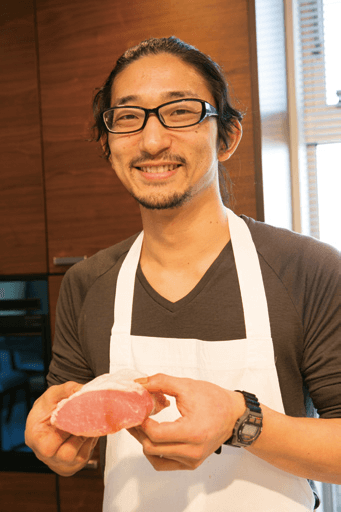
イタリアだけではなく、日本にも、「あるものを活かして料理する」姿勢のシェフがいる。それが、東京都世田谷区でフランス料理のレストラン「OGINO」を営む、荻野伸也さんだ。一般的には、たとえばにんじん料理が作りたいから「にんじんを1万円分ください」と農家の方に頼む。だが荻野さんは、農家の方に「今、畑にある野菜を1万円分ください」といった頼み方をしている。自分の都合に合わさせるのではなく、畑の都合に自分が合わせるのだ。
人間の都合でなく畑の都合。採れた野菜を見て料理を考える」規格外を捨てずに活かすターブルオギノの挑戦
https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20181015-00100505/
美食家の北大路魯山人(ろさんじん)は、皮や葉や茎なども喜んで調理したという。書籍『知られざる魯山人』(山田和著、文春文庫)には、魯山人が料理人たちに「捨てるような部分はない。そこだけで前菜を作れ」「ゴミを出すな。すべて食べられる」と口酸っぱくして言う様子が描かれている。
世間でいうまともな部分だけを使う料理人は、何十年やっていても定型にとらわれてそこから脱却することができない。
(『知られざる魯山人』山田和著、文春文庫)

コロナ禍でロックダウン(都市封鎖)になったイギリスやイタリア、オーストラリアなどの調査を見てみると、買い物に行けなくなったため、家にあるものをまずチェックして買い物リストを作るようになったり、家にある食べ物や残り物を捨てなくなったりした傾向が見てとれる。
家庭で、冷蔵庫にある食材で家族のために料理する、というのは想像できる。が、レストランで顧客のために「ある食材」を使って料理し、お金をいただくには、料理人の力量が問われる。だが、魯山人の言う通り、ある食材を活かすことができてこそ、真の料理人と言えるのかもしれない。
文=井出留美
奈良女子大学食物学科卒、博士(栄養学/女子栄養大学大学院)修士(農学/東京大学大学院農学生命科学研究科)。
ライオン(株)、青年海外協力隊を経て日本ケロッグ広報室長等歴任。311食料支援で廃棄に衝撃を受け誕生日を冠した(株)office3.11設立。
「食品ロス削減推進法」成立に協力した。食品ロス削減を目指す、政府・企業・国際機関・研究機関のリーダーによる世界的連合Champions12.3メンバー。著書に『賞味期限のウソ』『捨てられる食べものたち』。

