
キャビア、フォアグラと並び、世界三大珍味のひとつとして知られるトリュフ。なかでもオーストラリア産黒トリュフは、南半球の冬に収穫され、真夏の日本に届く。今回は「シェ・イノ」の手島純也さんが、その魅力や調理法を教えてくれた。
古くから黒トリュフを特産物としてきたフランス西南部の地、ペリゴール。その気候や土壌と似た西オーストラリアのマンジアップで、カシやナラの植樹が始まったのは、ヨーロッパでトリュフの収穫量が減り始めた1980年後半のことだ。恵まれた環境だったことも幸いし、トリュフの収穫量は年々増加。今ではフランス、イタリア、スペインに次ぐ世界第4位の産地に育った。
そんなオーストラリア産黒トリュフを10年以上前から使っているのが、2022年10月に「シェ・イノ」の料理長に就任した手島純也さん。
「僕はフランスにいた頃、何度かトリュフを扱うポジションに就いていたことがあって、黒トリュフに対しては思い入れが強いんです。当時は人が入れるほど大きな冷蔵庫で黒トリュフを保管していて、庫内に入るとその香りでクラクラするほど。陶酔感があるというか、ちょっと猥雑で、フランスではよくエロティックと形容しますが、まさに唯一無二。代わるものがない。フランス料理には欠かせない食材のひとつです」。
南半球の冬は、北半球の夏。オーストラリアと日本は季節が真逆。かつては冬の味覚だった黒トリュフだが、「今や、真夏の日本でもフレッシュなものを料理に使えるということが最大の魅力」と手島さんは言う。
「夏場にフレッシュな黒トリュフが使える上に、日本に入ってくるのは最上級品です」。

シェフによっては、黒トリュフは冬の食材だから夏に使うのは違和感があるという人もいる。
「でも、僕はそんなことは考えたこともなかった。むしろ、夏にフレッシュな黒トリュフが使えることで、料理の幅が広がると思いました」。
というわけで、今回は夏の食材であるアワビを使った「アワビとフォアグラとトリュフのショソン」を作っていただいた。





手島シェフも絶賛するオーストラリア産黒トリュフ。なかでもアルカンが輸入しているのは、西オーストラリアのマンジマップ地域に位置するサプライヤーのもの。この辺りは土壌が柔らかく豊かで水はけも良く、トリュフ栽培には最適の条件がそろっている。実際、南半球のプレミアムトリュフの70%以上がこの地域で生産されている。
「弊社でも約5年前からオーストラリアの黒トリュフを輸入していますが、私個人の感覚ではフランス産やイタリア産と並べても同等のクオリティです。現地できちんと管理・選別されたトリュフを常に送ってくれる。汚れや痛みも少ない。信頼できるサプライヤーです」とアルカン東日本物流センターの青柳智之さんは話す。

もちろん、アルカン側の管理体制も万全だ。
「トリュフは水分を多く含み、香りの成分は揮発性が高く、密閉したままだと中が濡れてきて、トリュフは水を吸ったところから腐っていきます。かといって密閉しなければ、水分や香りの成分が減っていき重量が軽くなってしまいます。トリュフを扱う上で、水分と温度の管理は重要です」と、東日本物流センター長の長久保幸司さんは言う。また施設自体の管理体制についても言及する。「当センターでは冷凍から常温まで5つの温度帯で管理された倉庫を配置しています。さらに、各食材が持っている菌が影響し合わないように、品目に特化した5つの冷蔵室も用意し、徹底した品質管理を行っています」。

トリュフ栽培に適した大地、トリュフ栽培に真摯に取り組むサプライヤー、アルカンのノウハウ。それらが三位一体となって、最高級のオーストラリア産黒トリュフは顧客の元へ届けられている。


黒トリュフは、北半球では基本的に冬の食材とされている。しかし20世紀後半、南半球のオーストラリアで黒トリュフが栽培されるようになり、北半球の国々では、“冬場に収穫された”フレッシュな黒トリュフを夏でも使えるようになった。もちろん、品質はフランス産やイタリア産と比べても同等の品質であり、近年ますます需要が高まっている。
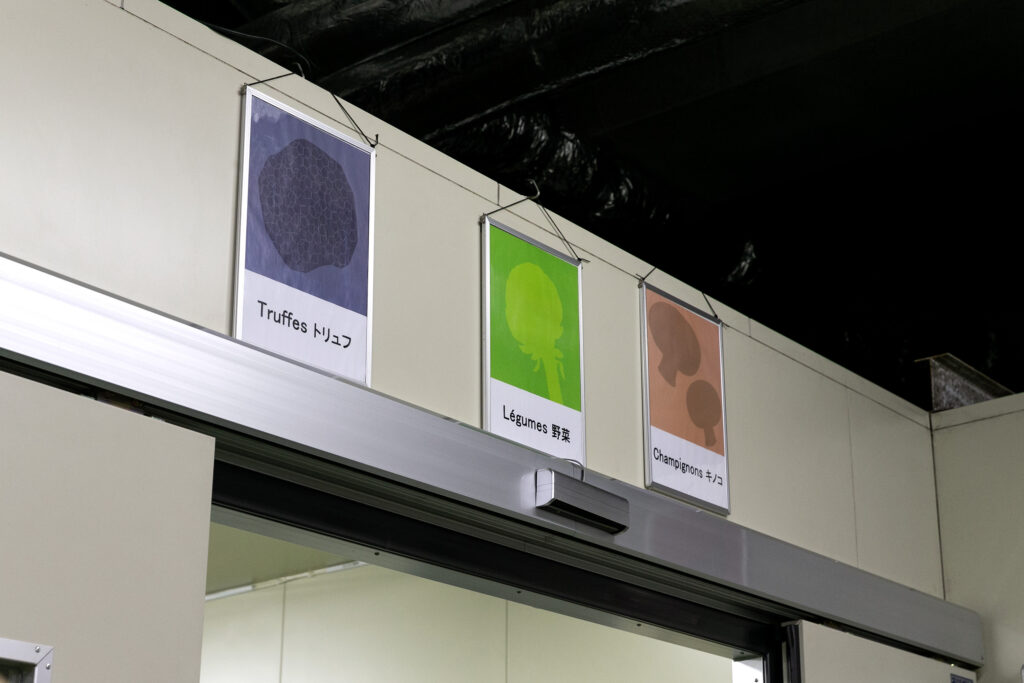




手島純也
1975年、山梨県生まれ。地元のレストランで修業後、2002年渡仏。パリの「ステラマリス」「タイユヴァン」「ルイ・トレーズ」「カンポカフェ」などで研鑽を積み、2007年帰国。東京「芝パークホテル タテルヨシノ」、和歌山「オテル・ド・ヨシノ」の料理長を経て、2022年10月から「シェ・イノ」の料理長へ。

シェ・イノ
東京都中央区京橋2-4-16
明治京橋ビル1F
TEL 03-3274-2020
11:30~13:30LO、
18:00~20:30LO
日曜、月曜に1~2日休
【オーストラリア産黒トリュフお問い合わせ】
アルカン業務食材営業部
TEL 03-3664-5114
text: Shoko Yamauchi photo: Hiroyuki Takeda

